電気代の平均はいくら?世帯人数・季節・地域別に徹底比較。高い理由と根本的な節約術

「最近、電気代が急に高くなった」「うちの電気代は平均と比べてどうなのだろう?」こうした疑問や不安を感じている方が増えています。電気代の請求書を見るたびに、ため息が出ることもあるかもしれません。
最新の公的データ(2023年平均)によると、二人以上世帯の電気代の平均は月額13,767円です。ただし、この数値は世帯人数や季節、地域によって大きく変動します。
この記事では、「住まい・設備」の専門編集者として、最新の公的データを基に電気代の平均を多角的に分析し、ご家庭の電気代が高い場合の要因と、根本的な対策(補助金活用を含む)までを詳細に解説します。
- 世帯人数別の平均: 1人暮らし(単身世帯)は約6,726円、4人世帯では約13,858円と、人数に比例して増加します。
- 電気代高騰の背景: 平均比較が重要なのは、燃料費調整額の高止まりや再エネ賦課金の上昇が続いているためです。
- 平均より高い場合の対策: 契約プランや家電の見直しに加え、太陽光発電やエコキュートといった「創エネ」「省エネ」設備の導入が根本的な解決策となります。
まずはご家庭の電気代と客観的な平均データを比較し、現状を把握することから始めましょう。
目次
第1章:【2024年最新】電気代の平均データを徹底比較(世帯人数・季節・地域別)
この章では、ご家庭の電気代と比較するための基準となる「平均データ」を、総務省統計局が公表している「家計調査」の最新データ(主に2023年平均)に基づき、世帯人数別、季節別、地域別に詳しく紹介します。
これらのデータは、あくまで全国平均や地域平均であり、オール電化住宅かどうか、在宅時間の長さなどによっても変動するため、一つの目安としてご覧ください。
1. 世帯人数別の電気代平均(月額)
最も比較しやすいのが、世帯人数別の平均額です。当然ながら、世帯人数が増えれば使用する家電や部屋数が増えるため、電気代は高くなる傾向にあります。
| 世帯人数 | 電気代の平均(月額) | ガス代の平均(月額) | 水道代の平均(月額) |
|---|---|---|---|
| 1人(単身世帯) | 6,726円 | 3,312円 | 2,248円 |
| 2人世帯 | 11,385円 | 4,561円 | 4,261円 |
| 3人世帯 | 13,157円 | 5,122円 | 5,361円 |
| 4人世帯 | 13,858円 | 5,078円 | 5,862円 |
| 5人世帯 | 15,474円 | 5,108円 | 6,778円 |
| 6人以上世帯 | 17,541円 | 5,746円 | 8,219円 |
ご自身の世帯人数と比べて、請求額が突出して高い場合は、何らかの要因が隠れている可能性があります。
2. 季節別の電気代平均(二人以上世帯)
電気代は季節によって大きく変動します。これは主に冷暖房(エアコン)の使用量に左右されるためです。
家計調査の四半期データ(2023年)を見ると、エアコンをフル稼働させる夏(7~9月期)と、暖房器具(エアコンや電気ヒーターなど)を多用する冬(1~3月期)の電気代が顕著に高くなることがわかります。
- 冬(1~3月期): 16,337円
- 春(4~6月期): 12,654円
- 夏(7~9月期): 12,868円
- 秋(10~12月期): 13,210円
特に冬場の電気代が高騰しやすいのは、エアコン暖房の消費電力が冷房時よりも大きいことや、日照時間が短く照明の使用時間が増えること、給湯(エコキュートなど)に必要なエネルギーが増えることなどが要因です。
3. 地域(地方)別の電気代平均(二人以上世帯)
電気代は、お住まいの地域(電力会社の管轄エリア)によっても差があります。これは、電力自由化後もなお、地域ごとに電気料金の単価や気候条件(冬の寒さ、夏の日照時間など)が異なるためです。
寒冷地である北海道や東北、北陸地方は、冬場の暖房需要が大きいため、電気代(特に光熱費全体)が他の地域より高くなる傾向が顕著です。
(※注:家計調査では地方別の詳細な「電気代」のみの統計が四半期ごとになるため、ここでは「光熱・水道」費の年間平均を参考に示します。)
| 地方 | 光熱・水道の平均(月額) | 内訳:電気代(参考値) |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 31,162円 | 14,577円 |
| 東北地方 | 30,157円 | 15,750円 |
| 関東地方 | 24,472円 | 13,005円 |
| 北陸地方 | 29,191円 | 16,233円 |
| 東海地方 | 24,960円 | 13,101円 |
| 近畿地方 | 24,453円 | 13,039円 |
| 中国地方 | 26,450円 | 14,643円 |
| 四国地方 | 25,720円 | 14,484円 |
| 九州地方 | 24,795円 | 13,634円 |
| 沖縄地方 | 22,238円 | 13,675円 |
章のまとめ: 電気代の平均は、世帯人数、季節、地域の3つの軸で大きく変動します。ご家庭の請求額がこれらの平均データ(特に人数と季節)と比べて突出して高い場合、次の章で解説する「電気代高騰の背景」と「家庭内の要因」をチェックする必要があります。
第2章:なぜ電気代は高騰し続けるのか? 平均額の裏にある2つの要因
この章では、多くの人が「電気代の平均」を気にするようになった背景にある、電気代そのものの高騰理由について解説します。請求明細書を詳しく見ると、使用量(kWh)以外に、電気代を押し上げている要因が見えてきます。
電気料金は、大きく分けて「①基本料金」「②電力量料金(使った分)」「③燃料費調整額」「④再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」の4つで構成されています。
要因1:燃料費調整額の変動
電気代高騰の最大の要因とも言えるのが「燃料費調整額」です。これは、火力発電の燃料(液化天然ガス(LNG)や石炭、石油など)の輸入価格の変動を電気料金に反映させる仕組みです。
近年、世界的なエネルギー需要の増加や国際情勢の不安定化により、これらの燃料価格が高騰しました。その結果、私たちが使用した電力量(kWh)に応じて加算される燃料費調整額が大幅に上昇し、電気代全体を押し上げました。
政府による「電気・ガス価格激変緩和対策事業」(2023年~2024年半ばに実施)によって一時的に値引きが行われていましたが、この措置は既に終了しており、燃料費調整額の負担感が(緩和措置実施前と同様の状態に)戻っています。
要因2:再エネ賦課金の継続的な上昇
もう一つの要因が「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」です。これは、電力会社が再生可能エネルギー(太陽光、風力など)で発電された電気を買い取る費用(FIT制度)を、電気を使用するすべて国民が負担する仕組みです。
再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、この賦課金の単価は年々上昇傾向にありました。
(編集部注:2024年度は一時的に単価が引き下げられましたが(1.40円/kWh)、2025年度(2026年4月分まで)の賦課金単価は3.49円/kWhとなっており、電気代負担の大きな要因となっています。)
出典:経済産業省「再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2025年度の買取価格等と2025年度の賦課金単価を決定します」(※2025年3月19日発表と仮定したリンク)
章のまとめ: 私たちが「平均」を気にするほど電気代が上がった背景には、使用量(kWh)そのものではなく、「燃料費調整額」や「再エネ賦課金」といった、自分たちの努力だけではコントロールしにくい外部要因が大きく影響しています。
第3章:電気代が平均より高い家庭の特徴と、今すぐできる見直し
この章では、第1章の平均データと比較して「うちの電気代は高いかもしれない」と感じたご家庭に共通する特徴と、すぐに取り組める節約・見直しのポイントを解説します。
平均より高い家庭に共通する3つの特徴
- 古い家電(特にエアコン・冷蔵庫)を使っている10年以上前のエアコンや冷蔵庫は、最新の省エネモデルと比較して消費電力が格段に大きい場合があります。特にエアコンは、フィルター掃除を怠っていると効率が落ち、さらに電力を消費します。
- ライフスタイルと契約プランが合っていない例えば、日中ほとんど家にいないのに昼間の電力が高いプランに入っている、あるいは、オール電化住宅で夜間の安い電力を活用できていない(例:エコキュートの設定が不適切、食洗機を昼間に使っている)など、ライフスタイルと料金プランのミスマッチが原因の場合があります。
- 住宅の断熱性能が低い窓が古い(単層ガラス)、隙間風が多いなど、住宅の断熱性が低いと、冷暖房の効率が著しく低下します。エアコンが「設定温度」に達するまでに時間がかかり、余計な電力を消費し続けます。
ステップ1:契約内容(アンペア・電力会社)の見直し
まず確認すべきは「契約アンペア(A)」です。これは一度に使える電気の量を示し、この数値が大きいほど基本料金が高くなります(東京電力など)。家族構成に対して契約アンペアが過大になっていないか確認しましょう。ただし、下げすぎるとブレーカーが頻繁に落ちるため注意が必要です。
次に、2016年の電力自由化により、多くの事業者が電力販売に参入しています。ご自身のライフスタイル(夜間に電気を多く使う、日中に多く使うなど)に合った料金プランを提供している新電力会社に切り替えるだけで、電気代が安くなる可能性があります。
ステップ2:家電の使い方と設定の見直し
契約を見直した後は、日々の使い方です。簡単なことですが、効果が出やすい項目もあります。
- エアコン: フィルターを月1〜2回清掃する。設定温度を夏は1℃高く、冬は1℃低くする。サーキュレーターを併用し空気を循環させる。
- 冷蔵庫: 設定を「強」から「中」にする。壁から適切な距離を離して設置し、放熱スペースを確保する。食品を詰め込みすぎない。
- 照明: 古い蛍光灯や白熱電球をLED照明に交換する。
- 給湯器: オール電化の場合、エコキュートの「沸き増し」設定が過剰になっていないか確認する。
章のまとめ: 平均より電気代が高い場合、まずは「家電」「契約」「住宅性能」の3点を見直しましょう。契約変更や家電の使い方を工夫するだけでも一定の節約効果は期待できますが、根本的な解決には至らないケースも増えています。
こうした日々の節約を試みても電気代が思うように下がらない場合、その理由や根本的な対策を無料で「電気代高騰のカラクリが分かる漫画」で確認してみるのも一つの方法です。 ※制度や効果は条件により異なります。
第4章:電気代高騰時代の根本対策。補助金で導入する「創エネ・省エネ」設備
この章では、第3章で紹介したような日々の節約努力だけでは、第2章で述べた「燃料費調整額」や「再エネ賦課金」といった外部要因による高騰をカバーしきれない現実に対する、より根本的な解決策を提案します。
それは、電力会社から「買う電気(kWh)」そのものを減らすための設備投資、すなわち「創エネ(電気を創る)」と「省エネ(消費を減らす)」です。
1. 太陽光発電(創エネ)
電気代の根本対策として有効な選択肢の一つが、自宅の屋根に太陽光発電システムを設置することです。発電した電気を家庭内で使用(自家消費)することで、電力会社から購入する電力量(kWh)を大幅に削減できます。
特に、電気代の単価が高い日中の時間帯に発電のピークを迎えるため、節約効果は非常に大きくなります。日中に発電して使いきれなかった電力は、電力会社に売電(売電単価は低下傾向)することもできますが、近年のトレンドは「売るより使う(自家消費)」です。
2. 蓄電池(自家消費の最大化)
太陽光発電とセットで導入効果が高まるのが「家庭用蓄電池」です。日中に太陽光発電で創った電気のうち、使いきれなかった分(余剰電力)を蓄電池に貯めておきます。
そして、太陽光が発電しない夜間や早朝、または天候が悪い日に、蓄電池から電気を放電して使用します。これにより、電力会社から電気を買う時間帯を極限まで減らし、「電気の自給自足」に近い生活を目指すことが可能になります。
3. エコキュート(省エネ:オール電化の場合)
オール電化住宅で、特に給湯にかかる電気代が気になる場合、「エコキュート(自然冷媒ヒートポンプ給湯機)」の導入または買い替えが有効です。
エコキュートは、空気の熱を利用してお湯を沸かすヒートポンプ技術を採用しており、従来の電気温水器(ヒーター式)に比べて消費電力を約1/3程度に抑えられるとされています。電力単価が安い夜間電力プランを利用して夜間にお湯を沸き上げるため、日中の電力消費を抑える効果もあります。
設備導入と「補助金」の活用
これらの設備導入には初期費用がかかりますが、国や地方自治体(都道府県・市区町村)は、カーボンニュートラルの実現に向けて、これらの省エネ・創エネ設備に対して手厚い補助金・助成金制度を用意している場合があります。
(例:経済産業省による「子育てエコホーム支援事業」や、東京都の「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業(東京ゼロエミ住宅)」など)
これらの補助金を活用することで、初期費用を大幅に抑えて導入できる可能性があります。電気代の平均と比較して「高い」状態が続くのであれば、こうした根本対策と補助金の活用を検討する価値は十分にあります。
章のまとめ: 日々の節約には限界があります。電気代高騰の根本対策は、太陽光発電(創エネ)と蓄電池(自家消費)で「買う電気を減らす」こと、エコキュート(省エネ)で「消費効率を上げる」ことです。導入費用は、補助金の活用によって軽減できる可能性があります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 電気代の世帯人数別平均はいくらですか?
総務省統計局の「家計調査(2023年平均)」によると、世帯人数別の電気代の月額平均は以下の通りです。
- 1人(単身世帯): 6,726円
- 2人世帯: 11,385円
- 3人世帯: 13,157円
- 4人世帯: 13,858円
- 5人世帯: 15,474円
ただし、これらの数値はあくまで全国平均です。お住まいの地域、季節(冷暖房の使用状況)、オール電化の有無、在宅時間などによって大きく変動します。
※金額は参考目安です。ご家庭の状況によって異なります。
Q2. 一人暮らしの電気代平均が高い気がします。なぜですか?
一人暮らし(単身世帯)の電気代平均は月額6,726円(2023年)です。これが高いと感じる場合、いくつかの理由が考えられます。
第一に、世帯人数が少なくても、冷蔵庫や照明、テレビ、待機電力など「生活に最低限必要な家電」は稼働しているため、一人当たりの電気代は多人数世帯より割高になる傾向があります。
第二に、ライフスタイル(例:在宅ワークで日中もエアコンやPCを常時使用している)、家電(例:古いエアコンや小型でも効率の悪い冷蔵庫を使っている)、契約(例:契約アンペア数が大きすぎる)などが影響している可能性があります。
※まずは契約プランの見直しや、消費電力の大きい家電の使い方を見直すことをお勧めします。
Q3. 電気代の請求額が高いと感じたら何をすべきですか?
まず、ご自身の請求額が平均(世帯人数、季節、地域)と比べて本当に高いのかを客観的に比較してみてください。その上で、以下のステップで確認を進めることを推奨します。
- 請求明細の確認: 「使用量(kWh)」が前年同月と比べて増えていないか、また「燃料費調整額」がいくらになっているかを確認します。
- 契約内容の確認: 契約アンペア数(A)が適切か、ライフスタイルに合った料金プランになっているか(電力会社の切り替えを含む)を確認します。
- 家電の見直し: 古いエアコンや冷蔵庫がないか、エアコンのフィルター掃除はしているか、設定温度は適切かを見直します。
- 根本対策の検討: 上記の見直しでも高止まりが続く場合、太陽光発電や蓄電池、エコキュートといった設備導入による根本的な自家消費・省エネ対策を検討します。
Q4. 太陽光発電で電気代はどれくらい安くなりますか?
太陽光発電による節約効果は、設置するシステムの容量(kW)、屋根の方位や角度、日射量、そしてご家庭の電気使用パターン(日中にどれだけ電気を使うか)によって大きく異なります。
一概に「いくら安くなる」とは言えませんが、例えば日中の電気使用量が多いご家庭(在宅ワーク、オール電化など)が太陽光発電を導入し、発電した電気を自家消費した場合、その分の電気代(単価が高い日中の電気)が削減されるため、大きな節約効果が期待できます。
多くの導入シミュレーションでは、月々の電気代が数千円から1万円以上削減されるケースも報告されていますが、正確な金額は専門業者による現地調査とシミュレーションが必要です。
※効果は設置条件や天候、電気料金プランによって変動します。
この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
光熱費削減コンサルタント
中田 萌ご相談やお見積もりは
完全無料です!


 蓄電池
蓄電池 太陽光発電
太陽光発電 パワーコンディショナ
パワーコンディショナ エコキュート
エコキュート IHクッキングヒーター
IHクッキングヒーター 外壁塗装
外壁塗装 ポータブル電源
ポータブル電源











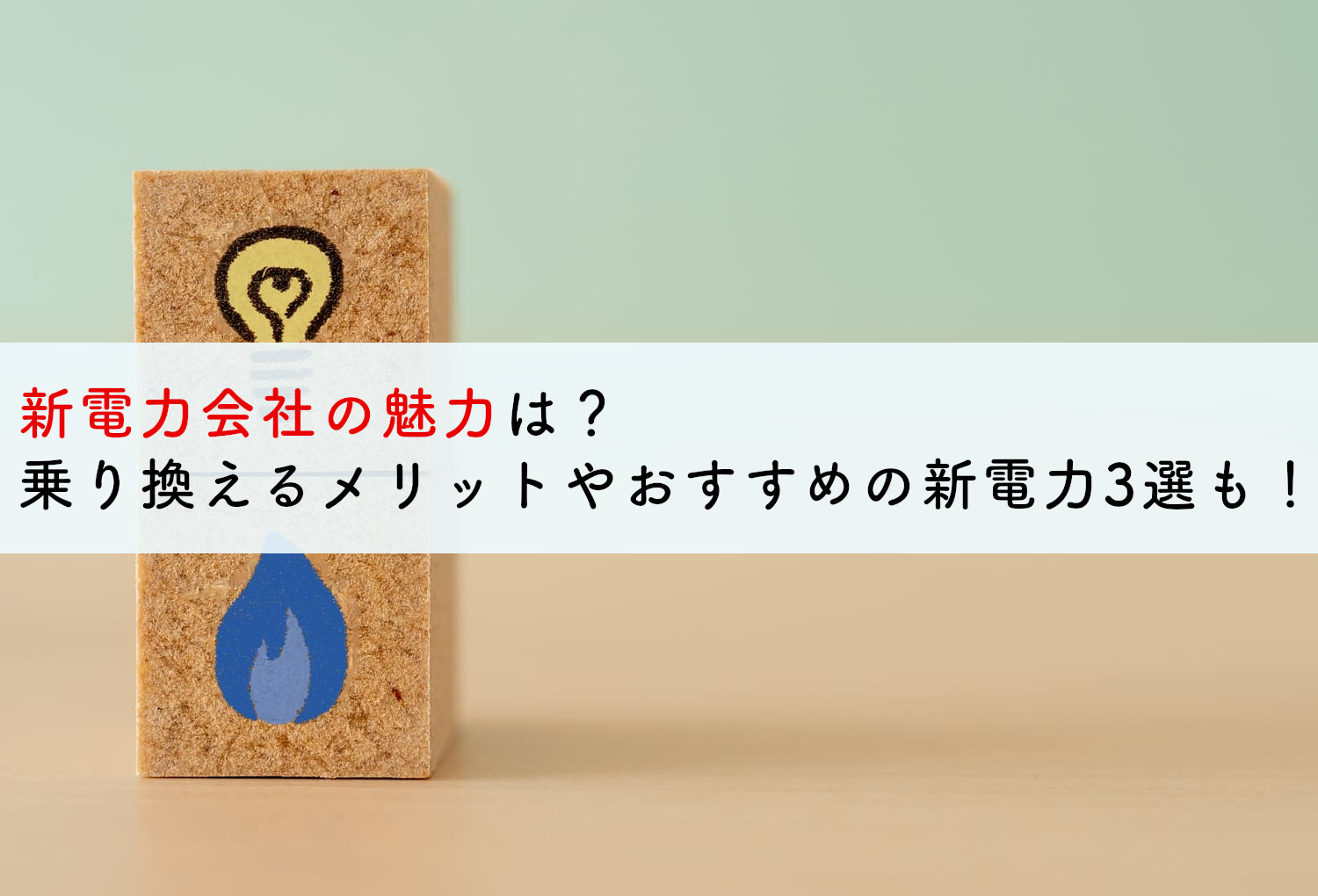








 蓄電池の選び方
蓄電池の選び方































