エコキュートをおすすめしない3つの理由とは?失敗しない選び方も徹底解説!
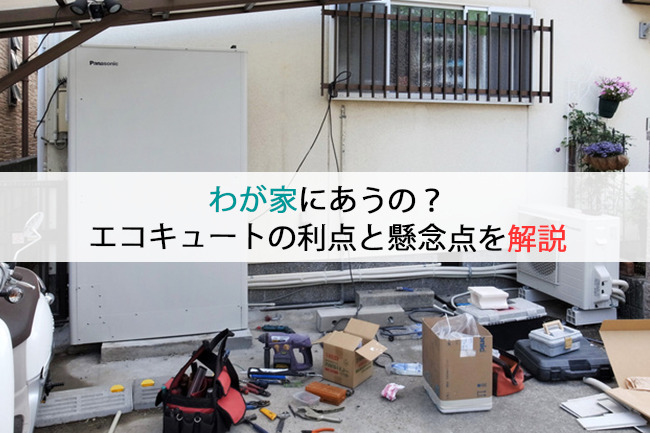
※本記事は、事業者から提供を受けた商品・サービスのPRを含む広告コンテンツです。
「省エネ性能の高さ」や「ガスを使わない安全性」など、数々のメリットで人気のエコキュート。とはいえ、すべての家庭におすすめできる給湯設備とは断言できない要素もあります。
特に、「初期費用の高さ」や「設置スペースの問題」といったデメリットは、購入後に「失敗したかも…」とストレスに感じる可能性がゼロではありません。そのため、設置前にはエコキュートの長所だけでなく、短所もしっかり理解しておくことが大切です。
そこで本記事では、エコキュートを「おすすめしない3つの理由」と、逆に「おすすめできる5つのメリット」、さらに失敗しない選び方まで徹底解説していきます。導入しようか迷っている方は、ぜひ本記事の内容を参考にしてみてください!
目次
エコキュートがおすすめできない「3つの理由」とは?
次世代の給湯設備として、メリットばかりが強調されがちなエコキュート。「思っていたのと違う」といった後悔を避けるためにも、デメリットもしっかり理解したいところ。ここでは、エコキュートはおすすめ!と断言できない「3つの理由」をご紹介していきます。
理由①:ガス給湯器に比べて初期費用が高め
エコキュートの大きなハードルは、導入にかかる「初期費用の高さ」です。一般的なガス給湯器なら工事費用を含めても「20〜30万円」程度で交換できますが、エコキュートの場合は合計で「40〜70万円」ほどが相場といわれています。
国や自治体の補助金を利用しても自己負担はそれなりに残るため、「とにかく初期費用を抑えたい」と考えている人には負担が大きく感じられるでしょう。長期的には節約につながる可能性が高いものの、導入時のコストをどう捉えるかが重要なポイントといえます。
※本項の数値・内容は特定条件に基づく試算であり、実際の結果を保証するものではありません。
理由②:設置には意外と大きなスペースが必要
壁掛け式でコンパクトな機種が多いガス給湯器に比べて、「設置スペースがかさばる」点もエコキュートならではの気になるポイント。エコキュートは「ヒートポンプユニット」と「貯湯タンク」の2つを設置する必要があり、思った以上に大きなスペースを取ります。
特に、貯湯タンクの高さは2メートル前後。幅・奥行きもかなりあるため、戸建て住宅でも庭や通路のスペースが限られていると設置が難しいケースがあります。また、重さも数百キロになるため、設置には基礎工事を伴うことも少なくありません。
マンションや狭小住宅ではそもそも導入ができない場合もあるので、設置条件を事前にしっかり確認しておくことが欠かせません。
理由③:「お湯切れ」するとしばらくお湯が使えない
エコキュートはあらかじめ貯湯タンクにお湯をためて使う仕組みのため、想定以上にお湯を使うと「お湯切れ」を起こすことがあります。特に、来客が多い日や冬場に長めの入浴が重なると、急にお湯が出なくなり不便に感じるケースも少なくありません。
一度お湯切れが発生すると、シャワーやお湯はりに十分なお湯を確保できるまで「約30分〜2時間」ほどかかってしまいます。日常的にお湯を多く使う家庭や、急な使用が多い家庭では、このデメリットをしっかり考慮する必要があります。
エコキュートをおすすめできる「5つの理由」も知っておこう!
初期費用の高さや設置のハードルといったデメリットもあるエコキュート。その一方で「導入して良かった」という声が多いのも事実です。ここでは、「光熱費の節約効果」や「非常時の安心感」など、エコキュートをおすすめできる「5つの理由」を見ていきましょう。
理由①:給湯費を大幅に節約できる
エコキュート最大の魅力は、なんといっても毎月の給湯費を大きく削減できること。電気代の安い深夜の時間帯にまとめてお湯を沸かす仕組みにより、ガス給湯器に比べて光熱費を「約2分の1〜3分の1」程度までカットできるといわれています。
家族の人数が多く、お湯の使用量が多い家庭ほど節約効果は高く、年間で「数万円」単位の違いになることも少なくありません。初期費用はかかるものの、長期的なランニングコストの安さを考えると、エコキュートは家計にやさしい選択肢といえるでしょう。
※本項の数値・内容は特定条件に基づく試算であり、実際の結果を保証するものではありません。
参考:ダイキン工業
理由②:災害時にタンクの水を生活用水として使える
エコキュートのタンクには数百リットルのお湯や水が常に蓄えられており、災害時や断水時には「非常用の生活用水」として活用できます。飲料水としては使えませんが、トイレの流し水や手洗い、簡単な洗い物などには十分に役立ちます。
特に、地震や台風などでライフラインが止まった際、タンクに水が残っているだけで大きな安心につながるでしょう。一般的なガス給湯器にはない大きなメリットであり、防災意識が高い家庭にとっては導入の大きな決め手になります。
理由③:環境に優しく、火災のリスクが少ない
エコキュートは「ヒートポンプ技術」を使って空気の熱を効率よく利用し、電気の力でお湯を沸かす仕組みのため、従来のガス給湯器に比べてCO₂排出量を大幅に削減できます。環境負荷を減らし、地球温暖化対策にも貢献できる点は大きなメリットといえるでしょう。
さらに、エコキュートは環境にやさしい給湯器として国や自治体からも推奨されており、導入時には「豊富な補助金制度を利用できる」点も見逃せないメリット。補助金を利用すれば、高額になりがちな初期費用をある程度抑えることが可能となります。
また、火を使わずにお湯を沸かす構造のため、ガス漏れや引火の心配がなく、安全性の面でも大きな安心が得られます。特に、小さな子どもや高齢者がいる家庭では「火を使わない給湯器」という安心感は非常に大きく、日常の暮らしにおけるリスク軽減につながります。
理由④:快適で便利な最新機能が豊富
最新のエコキュートは、単にお湯を沸かすだけでなく、生活を便利にする機能が充実しています。例えば、予約タイマーで入浴時間に合わせて自動でお湯はりしたり、マイクロバブルによる快適な入浴機能、UV除菌機能で浴槽のお湯を清潔に保ってくれるモデルもあります。
また、スマホで遠隔操作ができる機種も多く、外出先からでもタンクの残り湯量や温度の確認、お湯はりや沸き上げなどを自由に操作できます。こうした快適機能は、忙しい家庭や小さな子ども、お年寄りがいる家庭にとって、毎日の入浴や家事をよりスムーズにしてくれる大きなメリットとなるでしょう。
理由⑤:太陽光発電で作った電気でお湯が沸かせる
エコキュートは「電気」でお湯を沸かす仕組みのため、家庭で太陽光発電を導入している場合、発電した電気を活用してお湯を作ることができます。昼間に発電した電気を活用することで、電力会社から購入する電気代をさらに削減でき、光熱費の節約効果が高まります。
特に、太陽光パネルの設置枚数が多く、昼間に余剰電力が発生する家庭では、そのまま電力会社に売電するより、効率的に再生可能エネルギーを活用できるでしょう。
最近では、太陽光発電との連携を前提に設計された「おひさまエコキュート」も登場しています。発電状況や家庭の消費電力に応じて自動で効率よくお湯を沸かすため、余剰電力をムダなく活用可能です。これにより、光熱費のさらなる節約が期待できる点も、ガス給湯器にはないメリットといえます。
押さえておきたい!失敗しないエコキュートの「3つの選び方」
エコキュートのデメリットとメリットを知ったうえで、導入を決断する方も多いでしょう。しかしながら、「タンク容量」や「業者選び」などの選択を間違えると、設置後の満足度が下がる原因となってしまいます。
ここでは、設置後の失敗を予防するための「3つの選び方」について考えていきましょう。
①:家族の人数やライフスタイルに合った容量を選ぶ
エコキュートを選ぶ際、まずはじめにしっかり決めておきたいのが「貯湯タンクの容量」です。家族の人数やお湯の使用量に合わせてタンク容量を選ばないと、せっかく導入しても「お湯切れ」や「電気のムダ使い」といった問題が発生しやすくなります。
一般的には、3〜4人世帯なら370L、4〜7人世帯なら460Lほどが目安とされていますが、「一人あたりのお湯の使用量が多い」「キッチンが2か所ある」など、状況によっては大きめサイズのほうが無難なケースもあるでしょう。
一方で、家族のお湯の使用量に合わない「大きすぎるタンク」を選ぶと、せっかく沸き上げたお湯を使い切れず、ムダな保温などで余計な電気代が発生してしまいます。お湯切れが起きると加熱に時間がかかるため「迷ったら大きめ」が無難ですが、決められない方は専門業者などに相談してみるのもおすすめです。
②:販売業者は価格だけでなく「信頼性」も重視する
工事費込み費用の安さで選んでしまいがちなエコキュートの販売業者ですが、価格面のメリットだけでなく、「設置工事の品質」や「アフターサポートの充実度」も含めて選ぶことが重要です。
安さだけで業者を決めると、工事の品質が低かったり、トラブル時の対応が遅れたりするリスクがあります。特に、給湯設備は施工ミスや接続不良があるとお湯が使えなくなるだけでなく、水漏れや他の住宅設備が故障する原因にもなるため、信頼できる販売業者や施工業者を選ぶことが安心につながります。
信頼できる販売業者を選ぶためには、口コミや施工実績を確認したうえで、価格とアフターサポートのバランスを考慮して判断するのがおすすめです。長く快適に使うためには、初期費用だけでなく「安心して任せられるか?」という視点も欠かせません。
③:補助金制度を活用して導入のハードルを下げる
ガス給湯器などに比べて、エコキュートは初期費用が高額になりがち。「思ったより高くついた…」といった後悔を避けるためには、国や自治体の補助金制度をフル活用することが大切です。
2025年度は国から「2種類のエコキュート補助金」が出ており、特に「給湯省エネ2025事業」では、「10万円」を超える助成を受けることも難しくありません。販売業者によっては「補助金の申請サポート」を実施しているケースもありますので、契約前にサポートの有無を確認しておくと安心です。
- 「給湯省エネ2025事業」(経済産業省)…6〜21万円
- 「子育てグリーン住宅支援事業」(国土交通省・環境省)…定額3万円
また、市町村などの自治体が独自のエコキュート補助金を実施しているケースも多く、「国の補助金と両方申請できる」場合もあります。自治体の補助金制度は申請条件や期間がまちまちですので、まずは公式ホームページなどで確認してみましょう。
まとめ:エコキュートのデメリットも理解して、納得ゆく買い替えを検討しよう
エコキュートには、省エネ性や快適機能、防災面での安心感など多くのメリットがありますが、初期費用の高さや設置スペースの問題、お湯切れのリスクといったデメリットも存在することも事実です。
しかしながら、「初期費用を補助金で抑える」「設置しやすいコンパクトモデルを選ぶ」「タンク容量に余裕を持つ」などデメリットを解決するアイデアも多々あるため、むしろ比較するとメリットの方が大きい給湯設備といえるでしょう。
導入前には、家族の人数や生活スタイルに合った容量・機能を選び、信頼できる販売業者を選定し、さらに補助金制度も活用することで、後悔のない選択が可能になります。メリット・デメリットをしっかり比較し、納得したうえで選ぶことで、快適で経済的なエコキュートの生活を目指しましょう!
この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
光熱費削減コンサルタント
中田 萌ご相談やお見積もりは
完全無料です!


 蓄電池
蓄電池 太陽光発電
太陽光発電 パワーコンディショナ
パワーコンディショナ エコキュート
エコキュート IHクッキングヒーター
IHクッキングヒーター 外壁塗装
外壁塗装 ポータブル電源
ポータブル電源











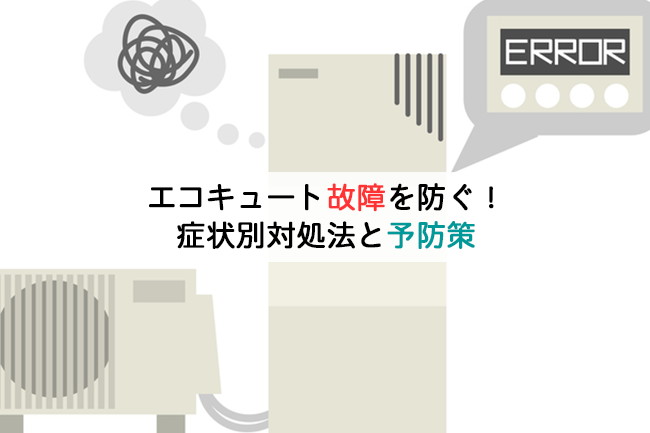
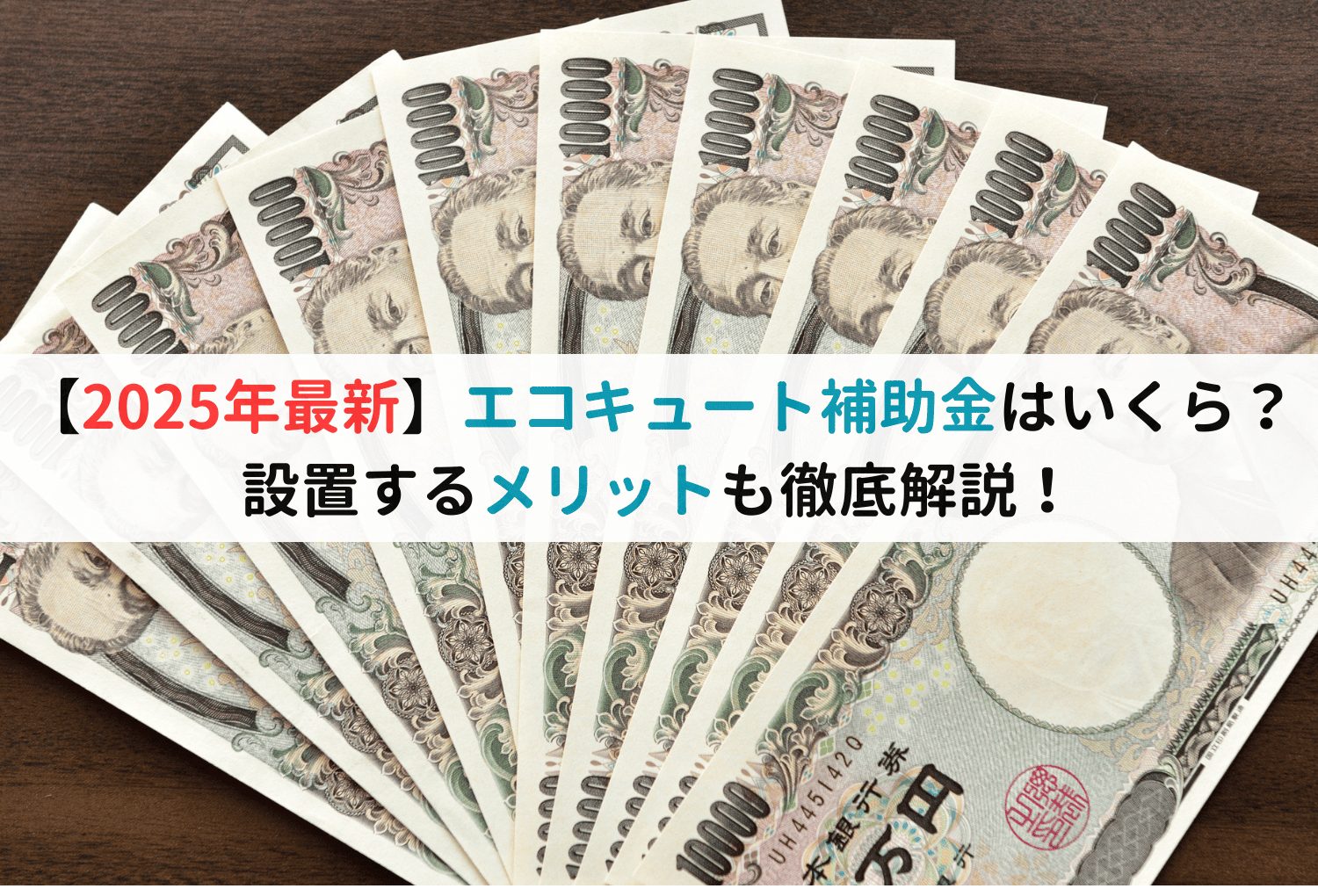







 蓄電池の選び方
蓄電池の選び方































