【2026年最新】再エネ賦課金「おかしい」と言われる納得の理由|負担額と自衛策

毎月の検針票を見て、「再エネ賦課金」という項目が不自然に高く、そもそもなぜ自分たちがこれを払わなければならないのか、と疑問に感じている方が増えています。特に2025年度の単価は過去最高の3.98円/kWhに設定され、一般的な家庭でも年間約2万円もの負担を強いられる事態となりました 。節電を頑張っても勝手に値上がりしていく仕組みや、太陽光パネルを持たない層が持っている層を支える不公平感。こうした「おかしい」と感じる違和感は、制度の構造的な問題に基づいています。
本記事では、専門ライターの視点から再エネ賦課金の理不尽な仕組みを整理し、2026年に向けた家計防衛の具体策を詳しく解説します。まず押さえておくべき結論は以下の3点です。
- 2025年度は過去最大の負担額
単価3.98円により、標準世帯(400kWh/月)で年額19,104円もの支出が発生します 。 - 逆相関が生む「不条理」
燃料価格が下がり電力市場価格が落ち着くと、不足分を補うための賦課金が逆に跳ね上がるという計算式が存在します 。 - 確実な自衛手段は一つだけ
賦課金は「購入する電気量」に課されるため、太陽光発電による自家消費が、賦課金負担を直接的に軽減する現実的な手段となります 。
目次
再エネ賦課金が「おかしい」と言われる納得の理由
脱炭素社会の実現という大義名分を掲げながらも、消費者がこの制度を「おかしい」と感じるのには明確な根拠があります。まず一つ目は、賦課金が全ての電気利用者に一律に課されるにもかかわらず、その恩恵を享受できるのは主に太陽光パネル等を設置した層に限られているという不公平性です 。賃貸住宅やマンションでパネルを設置できない世帯が、戸建てで売電収益を得ている層を金銭的に支えるという「所得の逆再分配」が常態化しています 。
さらに不透明なのが、単価算出の仕組みです。再エネ賦課金は、電力会社が再生可能エネルギーを買い取る費用から、市場で電気を売って得られた「回避可能費用」を差し引いて決定されます 。驚くべきことに、LNGや石炭の価格が安定して電力の市場価値が下がると、差し引く額が減り、その穴埋めとして賦課金単価が吊り上がるという、一般感覚とは逆の計算式になっています 。2025年度の大幅な単価上昇は、この「燃料価格の落ち着き(市場価格の下落)」が主要な原因となっています。
| 年度 | 賦課金単価(1kWhあたり) | 標準家庭の月負担(400kWh) |
|---|---|---|
| 2012年度(導入当初) | 0.22円 | 88円 |
| 2023年度(一時低下時) | 1.40円 | 560円 |
| 2024年度 | 3.49円 | 1,396円 |
| 2025年度(最新) | 3.98円 | 1,592円 |
家計へのダメージを長期的に見ると、制度開始時の2012年と比較して、年間の負担額は約18,000円以上も増加しました。普及すればするほど消費者の首を絞める、FIT制度(固定価格買取制度)の限界が露呈しているといえるでしょう 。
2026年冬の「補助金再開」と2030年に向けた負担のピーク
こうした負担増に対し、政府は一時的な緩和措置として2026年1月から3月にかけ「電気・ガス料金負担軽減支援事業」を実施します 。これは、特に暖房需要が増える冬期の家計を守るための緊急対策です 。
2026年1月・2月の使用分(2月・3月請求分)に対しては1kWhあたり4.5円、3月使用分(4月請求分)には1.5円の補助が適用されます 。標準的な家庭では、3ヶ月合計で約7,000円程度の負担軽減が見込まれますが、これはあくまで「一時的な止血剤」に過ぎません 。2026年4月にこの支援が終了すれば、再び3.98円の高額な賦課金がそのまま電気代に加算されることになります 。
長期的な将来予測に目を向けると、再エネ賦課金の負担はさらに厳しさを増します。環境省や電力中央研究所の分析では、賦課金単価は2030年度頃にピークを迎えるとされており、その水準は4.00円/kWhに達する見通しです 。その後、2012年頃の極めて高い買取単価で契約された設備が20年の買取期間を終える(卒FIT)2032年以降にならないと、賦課金負担が本格的に減少に転じることはないと予想されています 。
今後数年間は、政府の一時的な補助金と、構造的な値上がりが交錯し続ける不安定な状況が続きます。場当たり的な支援を待つのではなく、家計側でコストをコントロールできる仕組みを整える重要性がかつてなく高まっています。
一時的な補助金が終わった後の電気代が不安なら、無料で【電気代×補助金の解説記事】を読み、将来に備えた賢い立ち回り方を確認しておきましょう。 ※2025年度の最新単価と2026年冬の補助額を反映した解説です。
究極の自衛策「自家消費」への転換と悪質営業のリスク
再エネ賦課金の不条理な値上がりから逃れる唯一の論理的手段は、電力会社から電気を買う量を減らす「自家消費」の確立です 。賦課金の算出基礎はあくまで「購入した電力(買電量)」です。自宅の太陽光パネルで発電した電気をそのまま使えば、その分については3.98円/kWhの負担は一切発生しません 。
具体的にどの程度の節約になるのか、一般的な家庭での試算例を見てみましょう。
【シミュレーション】自家消費による電気代削減効果(年間)
(年間発電量 4,500kWh × 自家消費率 80%) × 電気代単価 31円 = 3,600kWh × 31円
⇒ 年間で 111,600円 の削減効果
※再エネ賦課金や燃料調整費を含む単価で試算。実際の削減額は天候や生活スタイルにより変動します。
かつては「売って稼ぐ(売電)」ことが重視されていましたが、現在は「賦課金を含めた高い電気代を払わない(自家消費)」ことで家計を防御する考え方が主流です。特に蓄電池を併用すれば、昼間の余剰電力を夜間に活用できるため、賦課金の回避効果を最大化できます 。また、初期投資が難しい世帯には、事業者が設備を設置するPPA(第三者所有)モデルも有効な解決策として普及しています 。
ただし、こうした電気代への不安を突いた悪質な営業トラブルには厳重な注意が必要です 。最近では「電力会社からの委託」や「点検が義務化された」と嘘をついて訪問し、不要な蓄電池を高額で売りつける手口が後を絶ちません 。特に、消費者センター等には以下のような相談事例が寄せられています 。
- 「市から委託された」と無料点検を装い、正常な装置を「故障している」と偽って蓄電池を勧誘する
- 「再エネ賦課金が完全にゼロになります」と、夜間の買電分を無視した説明をする
- 「国の補助金で実質タダになる」と言い、二重価格や補助金を上乗せした見積もりを提示する
信頼できるパートナーを選ぶためには、即日の契約を避け、必ず複数社からの相見積もりを徹底してください 。営業担当者の主観ではなく、公的なデータに基づいたメリットを提示できるかどうかが、優良業者を見極める鍵となります。
あなたの家の「適正価格」と「補助金」を今すぐチェック
まずは実績豊富な優良施工店による無料診断で、我が家のポテンシャルを確認してみましょう。
※無理な勧誘はありません。安心してご利用ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 再エネ賦課金 おかしいと言われる本当の理由は?
大きな理由は二つあります。一つは「市場の電力価格が下がると賦課金が上がる」という一般消費者には理解しがたい計算式の矛盾です。もう一つは、太陽光パネルを持たない世帯が、持っている世帯の売電益を一律に支える構図が不公平だと感じられるためです 。
※制度の是非については、継続的に国会や経済産業省の委員会で議論の対象となっています。
Q2. 2025年度の家庭での負担額は具体的にいくら?
2025年度の単価は3.98円/kWhです。前年度(3.49円)と比較すると約14%の増加です。標準的な4人世帯(月400kWh使用)であれば、月額1,592円、年間に換算すると19,104円の負担が発生します。制度開始時(2012年)の年額負担が約1,000円程度だったことを考えると、大幅な負担増といえます 。
※負担額は、ご自宅の検針票に記載された「使用電力量(kWh)」に単価を掛けることで正確に算出できます。
Q3. 回収年数はどれくらい?導入する価値はある?
条件によっては10年前後で初期費用の回収を見込めるケースもありますが、設置条件やメンテナンス費用によって異なります。かつてのような「売電」だけで稼ぐのは難しくなりましたが、現在は「賦課金3.98円を含む高い電気代(買電)」を減らす自家消費メリットが回収期間を早める大きな要因となっています 。
※補助金の活用や施工費用の相見積もりによって、さらに期間を短縮できる場合があります。
Q4. 営業担当者に「点検が必要」と言われましたが?
電力会社や自治体が、特定の機器販売や有料点検を民間業者に委託することはありません。また「太陽光発電が義務化されたから蓄電池が必要」といった勧誘も虚偽です。身分証の提示を求め、不審な場合はその場ですぐに契約せず、相見積もりを取るか、家族や専門窓口に相談してください 。
結論:外部要因に振り回されない「エネルギーの自立」が最大の解
再エネ賦課金が「おかしい」と感じるのは、単なる感情論ではなく、制度の構造的な不備や不公平さがデータとして現れているからです 。2030年のピークに向けた負担増は避けられず、2026年冬に再開される補助金もあくまで一時的な緩和に過ぎません 。これからの不透明な時代において家計を守るためには、制度の変更や燃料価格の乱高下に一喜一憂するのではなく、自らエネルギーを創り、賢く使う体制を整えることが最も確実な対策となります 。
太陽光発電や蓄電池の導入は、もはや単なる環境活動ではなく、高騰する家計の固定費に対する「究極の自衛策」です。まずはご自身の家庭でどの程度の対策が可能なのか、信頼できるデータに基づいてシミュレーションを行うことから、本当の意味での家計の防衛を始めてください。
関連記事
【出典・参考資料】
- 経済産業省:2025年度の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を設定しました
- 資源エネルギー庁:再生可能エネルギー発電促進賦課金について
- 国民生活センター:家庭用蓄電池の勧誘トラブルにご注意
- 環境省:再生可能エネルギーの導入に伴う効果・影響分析
この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
光熱費削減コンサルタント
中田 萌ご相談やお見積もりは
完全無料です!


 蓄電池
蓄電池 太陽光発電
太陽光発電 パワーコンディショナ
パワーコンディショナ エコキュート
エコキュート IHクッキングヒーター
IHクッキングヒーター 外壁塗装
外壁塗装 ポータブル電源
ポータブル電源







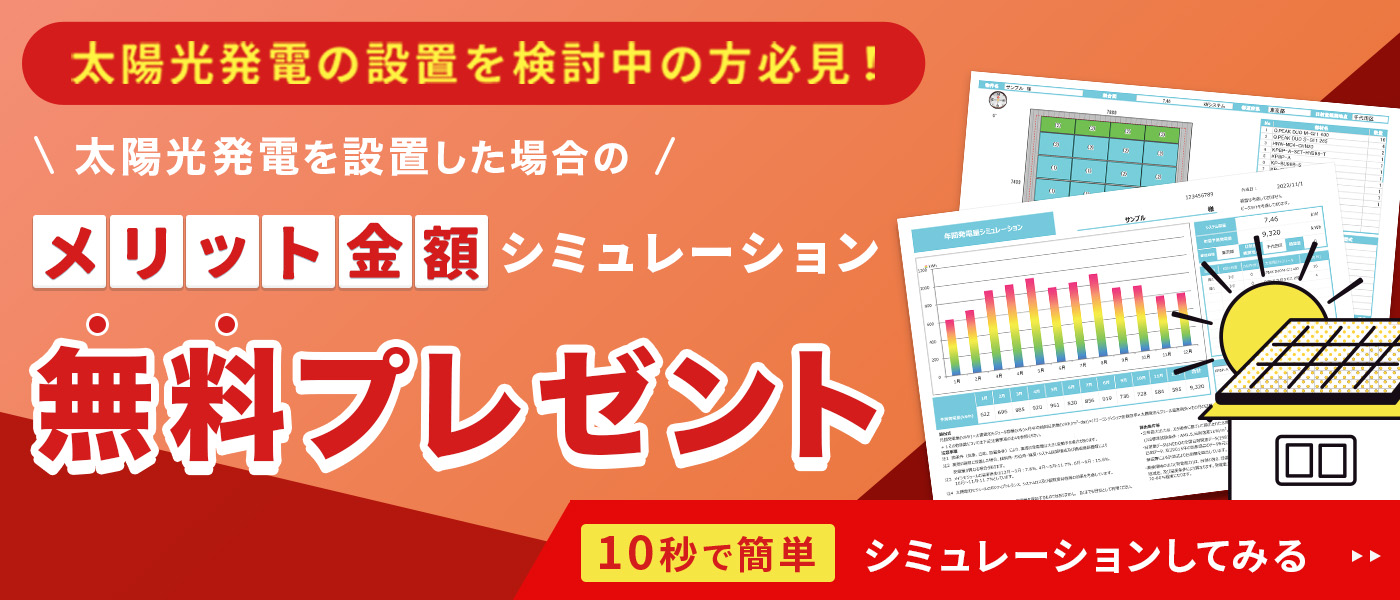













 蓄電池の選び方
蓄電池の選び方































