電気代滞納するとすぐに送電停止?流れを紹介します!
の電気代は高い?主要モデルの消費電力と他社比較、節電術を徹底解説のコピーのコピーのコピーのコピー.jpg)
【2025年版】電気代滞納で送電停止はいつ?回避策と再開までの流れを徹底解説
「電気代の支払いをうっかり忘れてしまった」「今月、支払いが厳しいかもしれない…」そんな時、真っ先に心配になるのが「いつ電気が止められてしまうのか?」ということではないでしょうか。電気は現代生活に不可欠なライフラインであり、送電停止は絶対に避けたい事態です。
結論から言うと、**電気代を滞納しても、支払期日を過ぎてすぐに電気が止められるわけではありません。**電力会社は法律や約款に基づき、段階的な手続きを踏んでから送電停止に至ります。しかし、最終的には必ず供給が停止されるため、早期の対応が不可欠です。
この記事では、電気代滞納による送電停止に関して、知っておくべき重要なポイントを以下の3つに絞って専門家が解説します。
- 送電停止までの具体的な流れと期間:支払期日から実際に電気が止まるまで、どのような通知があり、どのくらいの猶予期間があるのかを解説します。
- 送電停止を回避するための対処法:支払いが困難な場合に、まず何をすべきか、相談先や利用できる可能性のある制度について説明します。
- 送電再開の手続きと根本的な対策:万が一、電気が止まってしまった場合の再開方法と、滞納を繰り返さないための電気代削減策について触れます。
送電停止の仕組みを正しく理解し、万が一の状況に備えるとともに、根本的な家計改善へのヒントを見つけてください。
目次
第1章:電気代滞納から送電停止までの「タイムリミット」
電気代の支払いが遅れた場合、どのようなステップを経て送電停止に至るのでしょうか。電力会社の約款に基づいて定められた一般的な流れと、目安となる期間を解説します。
1-1. 検針日から支払期日まで
まず、毎月「検針日」に電力使用量が計測され、それに基づいて電気料金が確定します。その後、請求書が発行され、「支払期日」が設定されます。この支払期日は、検針日の翌日から起算して30日目が一般的です。(例:検針日が5月10日なら、支払期日は6月9日)
1-2. 支払期日超過後の猶予期間と督促
支払期日を過ぎても、すぐに電気が止められることはありません。電力供給約款には、支払期日を過ぎた場合の猶予期間が定められており、多くの電力会社では**支払期日の翌日から20日間**(「早収期限日」とも呼ばれます)を猶予期間としています。
この猶予期間を過ぎても支払いがない場合、電力会社から「督促状」や「催告状」といった形で、支払いのお願いと、このまま支払われない場合は送電を停止する可能性がある旨の通知が送られてきます。
※猶予期間や通知の名称・タイミングは電力会社によって異なる場合があります。必ずご契約の電力会社の約款をご確認ください。
1-3. 送電停止予告通知(最終通告)と停止実施日
督促状を送付してもなお支払いがない場合、電力会社は「電気料金支払のお願い(電気供給停止のお知らせ)」といった名称の**最終通告**を送付します。この通知書には、最終的な支払期限と、その期限までに支払いがない場合に**送電を停止する具体的な日時**が明記されています。
この送電停止日は、最初の**検針日から起算して約2ヶ月後**(支払期日から起算すると約1ヶ月後)に設定されるのが一般的です。つまり、支払期日から約1ヶ月間が、送電停止を回避するための最終的な猶予期間となります。
出典:東京電力エナジーパートナー「支払期日が過ぎてしまった場合」(※大手電力会社の約款に基づく一般的な流れの参考例)
【章のまとめ】
電気代を滞納した場合、支払期日から約20日間の猶予期間があり、その後、督促状、最終通告(送電停止予告)を経て、最初の検針日から約2ヶ月後に送電が停止されるのが一般的な流れです。
第2章:もし電気が止まったら?送電停止が生活に与える深刻な影響
送電停止は、単に「電気が使えなくなる」だけでは済まされません。現代生活の基盤である電気が失われることで、日常生活のあらゆる側面に深刻な影響が及びます。その具体的な内容を再確認し、事態の重大さを認識しましょう。
2-1. 家電製品の完全停止
家庭内のほぼ全ての家電製品が使用不能になります。
- 冷蔵庫・冷凍庫:中の食品が腐敗し、経済的な損失だけでなく食中毒のリスクも発生します。
- 照明:夜間の活動が不可能になり、転倒などの危険性が増します。精神的な不安も大きくなります。
- エアコン・暖房器具:夏は熱中症、冬は低体温症のリスクが高まります。特に乳幼児や高齢者のいる家庭では命に関わる問題です。
- 給湯器(エコキュート等):お湯が使えなくなり、入浴や衛生管理が困難になります。
- IHクッキングヒーター・電子レンジ:調理ができなくなり、食事の準備に大きな支障が出ます。
- 洗濯機・乾燥機:衣類の洗濯ができなくなります。
- その他、テレビ、パソコン、ドライヤーなど、生活に必要な多くの家電が停止します。
2-2. 情報・通信手段の途絶リスク
停電は情報収集や外部との連絡手段も奪います。
- スマートフォンの充電切れ:家族や知人との連絡、災害情報などの入手が困難になります。
- インターネット回線(光回線など):ONU(回線終端装置)やルーターの電源が落ちるため、Wi-Fiなどが使えなくなります。
- 固定電話(IP電話など):電源が必要なタイプの電話機は使用できなくなります。
2-3. 健康・安全への脅威
特に注意が必要なのが、健康や安全に関わる問題です。
- 在宅医療機器の停止:人工呼吸器や酸素濃縮器など、生命維持に必要な医療機器を使用している場合は、事前に電力会社や医療機関に相談し、非常用電源の確保などの対策を講じておく必要があります。
- マンション設備等の停止:オートロック、エレベーター、自動給水ポンプなどが停止し、生活に大きな支障が出る可能性があります。
【章のまとめ】
送電停止は、食事、衛生、健康、情報収集といった人間の基本的な生活活動を著しく困難にします。経済的な問題だけでなく、命の安全にも関わる重大な事態であることを認識し、絶対に回避しなければなりません。
電気代の不安、根本から解決しませんか?
毎月の電気代の支払いに不安を感じているなら、一時的な対処だけでなく、根本的な見直しが必要です。
あなたの家の電気代が高い原因を無料で診断し、無理なく続けられる効果的な節約プランをご提案します。まずは現状を把握することから始めましょう。
第3章:送電停止を回避するために!支払い困難時の相談先と対処法
「支払期日までにお金を用意できない」「送電停止予告が来てしまった」…そんな危機的な状況に陥った場合でも、諦めずにできることがあります。最も重要なのは、一人で抱え込まずに、適切な相手に相談することです。
3-1. 最優先すべきは「電力会社への相談」
支払いが困難だと分かった時点で、あるいは督促状や停止予告が届いたらすぐに、契約している電力会社のコールセンターや窓口に連絡し、正直に状況を説明して相談しましょう。
電力会社によっては、以下のような対応を検討してくれる場合があります。
- 支払期限の延長:一時的に支払いを待ってもらえる可能性があります。
- 分割払い:滞納分を何回かに分けて支払う相談に応じてくれる場合があります。
ただし、これらの対応は電力会社の判断や契約者の過去の支払い状況などによって異なります。必ず対応してもらえるとは限りませんが、相談しないことには始まりません。無視して滞納を続けるのが最も悪い選択です。
3-2. 公的な支援制度・相談窓口の活用
病気や失業など、様々な事情で電気代を含む生活費全般の支払いが困難になっている場合は、公的な支援制度を利用できる可能性があります。
- 生活困窮者自立支援制度:お住まいの自治体の福祉担当窓口(福祉事務所など)に設置されている相談窓口で、生活全般に関する困りごとの相談ができます。状況に応じて、家計相談支援や住居確保給付金、一時生活支援事業などの利用につながる可能性があります。
- 社会福祉協議会:緊急的な生活費の貸付(緊急小口資金など)を行っている場合があります。
- 消費生活センター:多重債務など、借金に関する問題を抱えている場合は、相談に乗ってもらえます。
これらの窓口に相談することで、電気代の問題だけでなく、生活再建に向けた具体的なアドバイスや支援を受けられる可能性があります。
3-3. 送電再開の手続き:支払いが最優先
万が一、送電が停止されてしまった場合、電気を再び使えるようにするためには、以下の手続きが必要です。
- 滞納料金の支払い:原則として、滞納している電気料金の**全額**を支払う必要があります。支払い方法は、コンビニ払い、銀行振込、クレジットカード払い(対応している場合)などがあります。
- 電力会社への連絡:支払いが完了したら、速やかに電力会社に連絡し、支払い済みであることを伝えます。連絡がないと、支払いを確認できず再開が遅れる場合があります。
- 送電再開作業:電力会社が支払いの確認を取れ次第、送電再開の作業が行われます。通常、連絡後**数時間~当日中**には電気が復旧しますが、時間帯や曜日によっては翌日以降になる場合もあります。
なお、電力会社によっては、送電再開にあたって**保証金(預託金)**の支払いを求められるケースもあります。
【章のまとめ】
電気代の支払いが困難な場合は、まず電力会社へ正直に相談することが重要です。公的な支援制度の活用も視野に入れましょう。送電停止後は、滞納分を支払い、電力会社へ連絡することで再開手続きが進みます。
電気代の悩み、専門家が一緒に考えます
「どこに相談したらいいかわからない」「根本的に電気代を安くする方法はないの?」
そんなお悩みを持つ方のために、電気代削減に関するあらゆる情報や、利用できる可能性のある制度についてまとめた特別レポートをご用意しました。まずは情報収集から始めてみませんか?
第4章:滞納を繰り返さないために!根本的な電気代削減策
送電停止という危機を乗り越えたとしても、根本的な家計状況が変わらなければ、再び滞納のリスクに直面しかねません。ここでは、将来にわたって電気代の負担を軽減するための、より本質的な対策について考えます。
4-1. 無理のない範囲での「省エネ行動」
まずは、日々の生活の中でできることから始めましょう。
- 待機電力のカット(使わない家電のコンセントを抜く)
- エアコンのフィルターをこまめに掃除する
- 冷蔵庫の設定温度を適切に保ち、扉の開閉時間を短くする
- 照明をLEDに交換する
- シャワーの時間を短くするなど、お湯の使い方を見直す
一つ一つの効果は小さくても、積み重ねることで着実な節約につながります。
4-2. 電力料金プランの見直し
現在契約している電力会社の料金プランが、ご自身のライフスタイル(電気を多く使う時間帯など)に本当に合っているか確認しましょう。特にオール電化住宅の場合は、深夜電力の時間帯が生活リズムとズレていると、割高な電気代を払っている可能性があります。電力会社のウェブサイトなどでシミュレーションしてみることをお勧めします。
4-3. 省エネ性能の高い家電への買い替え
古いエアコンや冷蔵庫は、最新の省エネモデルと比較して大幅に多くの電力を消費しています。初期費用はかかりますが、長期的に見れば電気代の削減効果で元が取れる場合も少なくありません。国の省エネ家電買い替え補助金などを利用できる場合もあります。
4-4.【究極の対策】太陽光発電・蓄電池で「電気の自給自足」
電気代の負担や値上げリスクから根本的に解放されるための最も効果的な手段が、**太陽光発電システムと家庭用蓄電池を導入し、電気を自宅で創り、貯めて使う「自家消費」**を最大化することです。
- 電力会社から電気を買う量を最小限に抑えるため、電気代(基本料金や燃料費調整額、再エネ賦課金など)の支払いを大幅に削減できます。
- 日中に発電した電気を蓄電池に貯めれば、夜間も自家発電の電気で生活でき、停電対策としても非常に有効です。
初期費用は高額ですが、国や自治体の補助金を活用すれば負担を軽減できます。これは、将来にわたる電気代の不安に対する最も確実な投資の一つと言えるでしょう。
【章のまとめ】
電気代滞納を繰り返さないためには、日々の省エネ努力に加え、料金プランの見直しや省エネ家電への買い替えが有効です。さらに、太陽光発電と蓄電池による自家消費は、電気代負担と値上げリスクを根本から解決する最も強力な手段となります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 電気代滞納でブラックリスト(信用情報)に載りますか?
一般的に、電力会社は信用情報機関に加盟していないため、電気代の滞納だけでいわゆる「ブラックリスト」に載ることはありません。
ただし、電気代をクレジットカードで支払っている場合、カード会社への支払いが滞ると、その情報が信用情報機関に登録される可能性があります。また、滞納が長期間に及び、訴訟などに発展した場合は、その情報が記録される可能性も否定できません。
Q2. 送電停止は土日や祝日でも行われますか?
電力会社の約款によりますが、一般的に土日祝日や年末年始など、電力会社の休業日には送電停止を行わないケースが多いです。
ただし、停止予定日が休業日にあたる場合は、その翌営業日に実施される可能性があります。停止予告通知に記載された日時を必ず確認してください。
Q3. 電気代を滞納すると延滞利息はかかりますか?
はい、多くの電力会社では、支払期日を過ぎて支払った場合、その日数に応じて**延滞利息(年利10%程度が一般的)**が加算されます。
滞納期間が長引くほど、支払う総額が増えてしまいますので、早めの支払いや相談が重要です。
※延滞利息の利率は電力会社の約款によって定められています。
Q4. 送電停止前に連絡なしで止められることはありますか?
原則として、連絡なしに突然電気が止められることはありません。電力供給約款に基づき、督促状や送電停止予告通知など、段階を踏んで書面での通知が行われます。
これらの重要な通知を見逃さないこと、そして通知を受け取ったら無視しないことが非常に重要です。
Q5. 電気代の支払いがどうしても難しい場合、最終手段はありますか?
生活保護制度の利用も選択肢の一つです。生活保護を受給している場合、電気代は「生活扶助」として支給される費用の中から支払うことになります。
支払いが困難な場合は、担当のケースワーカーに相談することで、電力会社への連絡や支払い方法について助言をもらえる場合があります。まずは、お住まいの自治体の福祉事務所に相談することが第一歩です。
電気代の悩みから解放され、安心できる毎日へ
電気代の滞納や送電停止の不安は、精神的にも大きな負担です。
根本的な解決策として注目される太陽光発電や蓄電池について、導入費用から節約効果、補助金活用まで、あなたの疑問に専門家がお答えします。まずは無料相談で、不安解消の第一歩を踏み出しませんか?
この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
光熱費削減コンサルタント
中田 萌ご相談やお見積もりは
完全無料です!


 蓄電池
蓄電池 太陽光発電
太陽光発電 パワーコンディショナ
パワーコンディショナ エコキュート
エコキュート IHクッキングヒーター
IHクッキングヒーター 外壁塗装
外壁塗装 ポータブル電源
ポータブル電源











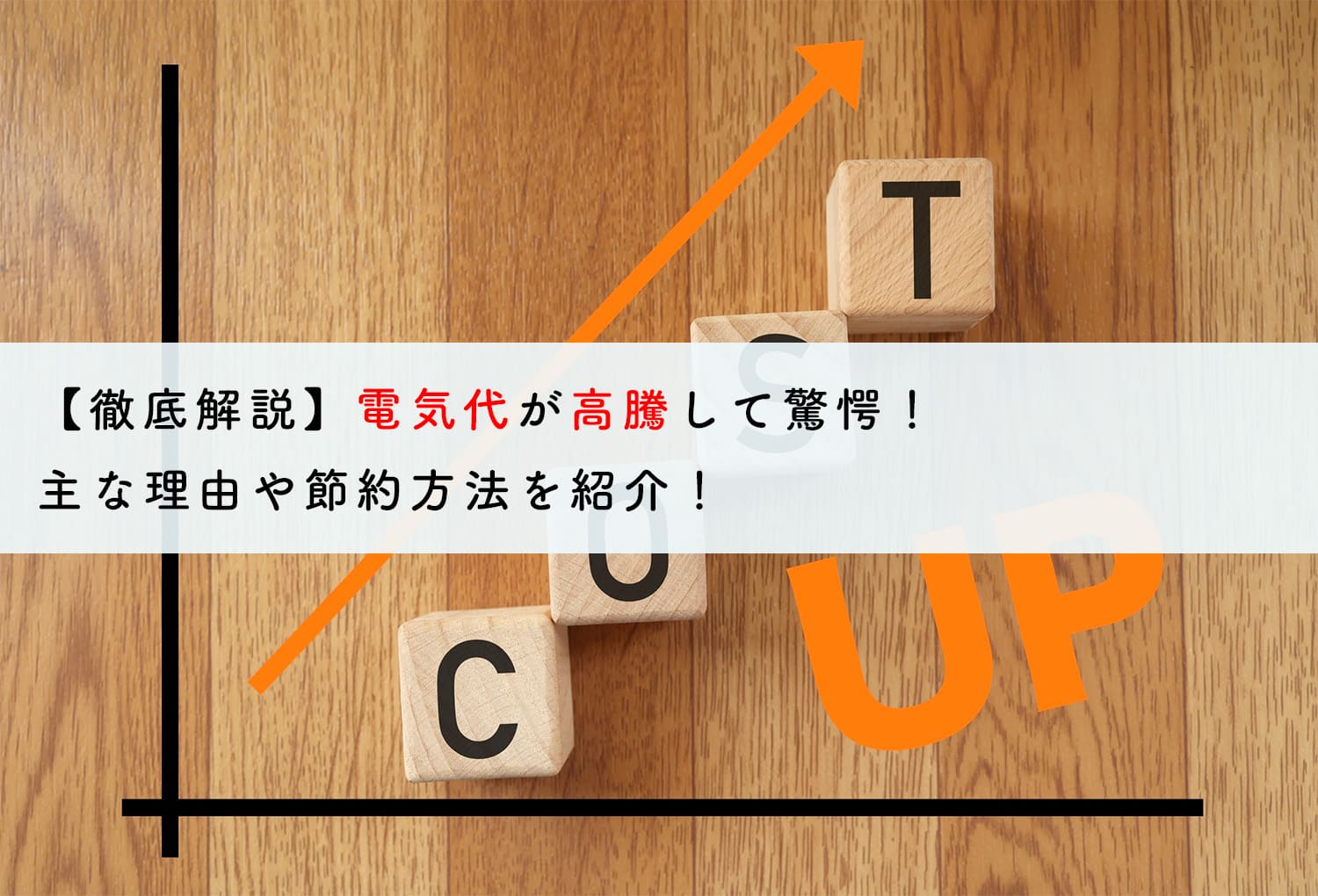








 蓄電池の選び方
蓄電池の選び方































