【2025年版】蓄電池の補助金は打ち切り?国の制度と自治体(東京都など)の最新情報を解説

結論から言うと、過去に実施されていた一部の国の補助金(例:災害時に活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業費補助金など)は打ち切りになりましたが、現在も形を変えた国の補助金や、自治体独自の補助金制度は数多く存在します。
この記事では、蓄電池の導入で損をしないために、以下の3つのポイントを専門家の視点で徹底解説します。
- 国の補助金の最新状況(2025年):打ち切りになった補助金と、現在(または今後)活用が期待できる国の補助金制度(ZEH関連やDER補助金など)について解説します。
- 地方自治体の補助金【東京都の例】:国の補助金がなくても、多くの自治体(特に東京都など)では独自の補助金が継続しています。その具体的な内容と探し方を紹介します。
- 補助金がなくても導入メリットはあるか?:補助金が打ち切りになった場合でも蓄電池を導入すべきか、その判断基準となる「電気代削減」と「災害対策」のメリットを再確認します。
補助金制度は情報戦です。正しい情報を把握し、導入コストを賢く抑える方法を学びましょう。
目次
第1章:【2025年最新】国の蓄電池補助金は打ち切り?現状と今後の見通し
まず、最も気になる「国の補助金」の状況について整理します。過去の制度が終了(打ち切り)になったことで、「国の補助金はもうない」と誤解されがちですが、実際は形を変えて継続されています。
1-1. 打ち切りになった補助金(過去の例)
過去には、家庭用蓄電池そのものを主な対象とした国の補助金が存在しました。代表的なものは以下の通りです。
- 災害時に活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業費補助金:2019年度(令和元年度)に実施され、災害対策としての蓄電池導入を支援しましたが、予算に達し打ち切りとなりました。
- ZEH+実証事業:ZEH(ゼッチ)住宅の普及を目的とし、蓄電池も補助対象に含まれていましたが、この事業も公募を終了しています。
これらの補助金が終了したため、「国の補助金は打ち切り」というイメージが広まりました。
1-2. 現在活用できる国の補助金制度(2025年)
現在、蓄電池「単体」での国の補助金は少なくなっていますが、**他の設備との組み合わせや、特定の目的(ZEH、VPP/DR)**を条件とすることで、引き続き国の補助金を活用できる可能性があります。
- 住宅省エネキャンペーンの後継事業(仮称): 2024年に実施された「子育てエコホーム支援事業」や「給湯省エネ事業」などの後継事業が2025年度も期待されます。これらの事業で、ZEH住宅の要件として蓄電池が補助対象に含まれる可能性があります。
- DER補助金(分散型エネルギーリソース活用実証事業など): VPP(仮想発電所)への参加を前提として、高性能な蓄電池(HEMS連携など)を導入する場合に適用される補助金です。補助単価が高い傾向にありますが、要件が複雑です。
このように、国の補助金は「打ち切り」ではなく、**「より高性能な住宅・設備や、新しい電力システム(VPP)への参加とセットになった補助金」**へとシフトしているのが現状です。
出典:一般社団法人 環境共創イニシアチブ (SII) (※DER補助金などの執行団体)
【章のまとめ】
過去の蓄電池単体を対象とした国の補助金は打ち切りになりましたが、2025年現在もZEH関連やDER補助金(VPP参加が条件)など、形を変えて補助金は継続されています。制度が複雑化しているため、専門家への相談が不可欠です。
【2025年最新版】わが家で使える補助金はいくら?
「国の補助金は複雑でわからない…」「うちの地域(自治体)の補助金は?」
国と自治体の複雑な補助金制度。専門家があなたの状況に合わせて、利用可能な最新の補助金情報を調査し、申請まで含めてトータルでサポートします。損しないための情報収集をお手伝いします。
第2章:【打ち切りではない】地方自治体の蓄電池補助金(東京都の例)
国の補助金が複雑化する一方で、現在、蓄電池導入の大きな柱となっているのが地方自治体(都道府県・市区町村)独自の補助金です。これらは国の制度とは別に設けられており、多くの場合、打ち切りにならず継続しています。
2-1. 【代表例】東京都の手厚い補助金制度
特に手厚い補助金制度を実施しているのが東京都です。「自家消費プラン事業」など、再生可能エネルギーの自家消費促進や災害対策強化を目的とした補助金が充実しています。
- 補助対象:東京都内の住宅に、太陽光発電システムと蓄電池システムを同時に導入(または蓄電池を後付け)する個人など。
- 補助金額(例):蓄電池システムの機器費の1/2など。1戸あたりの上限額が「蓄電容量1kWhあたり10万円」または「60万円」のうち低い方、といった具体的な基準が設けられています。(※年度により変動)
- 予算額:2024年度の例では約43億9,200万円など、大規模な予算が確保される傾向にあります。
2-2. その他の自治体でも多数実施中
東京都以外でも、多くの都道府県や市区町村が独自の補助金制度を実施しています。金額や適用条件は様々ですが、国の補助金と併用できる場合も多く、導入コストを大幅に引き下げられる可能性があります。
探し方:
「(お住まいの市区町村名) 蓄電池 補助金 2025」
「(お住まいの都道府県名) 蓄電池 補助金 2025」
といったキーワードで検索するか、自治体の環境政策課や商工課のウェブサイトを確認するのが確実です。
地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイト:(一社)住宅リフォーム推進協議会
【章のまとめ】
国の補助金が分かりにくくなっている今、蓄電池導入の鍵は「地方自治体の補助金」です。東京都のように手厚い制度も多いため、お住まいの地域の情報を必ず確認しましょう。
【簡単30秒入力】補助金活用後の実質費用はいくら?
「国と自治体、両方使える?」「結局、うちはいくら補助してもらえるの?」
その疑問、専門家が解決します。お住まいの地域やご希望の設備を入力するだけで、利用可能な補助金額と、それを差し引いた実質的な導入費用を無料でシミュレーションいたします。
第3章:補助金が打ち切りでも導入メリットはある?蓄電池の2大価値
「もし補助金が使えなかったら、蓄電池の導入は見送るべき?」と考える方もいるかもしれません。しかし、補助金はあくまで初期費用の負担軽減策の一つです。蓄電池には、それを超える長期的なメリット(価値)があります。
3-1. メリット①:電気代の削減(自家消費・ピークシフト)
蓄電池の最大のメリットは、日々の電気代を削減できることです。特に太陽光発電と組み合わせることで、その効果は最大化します。
- 自家消費率の向上:太陽光発電で発電した電気のうち、昼間に使いきれなかった余剰電力を蓄電池に貯め、夜間に使います。これにより、電力会社から高い電気を買う量を大幅に減らせます。売電単価が下がった現在、この「自家消費」こそが最も経済合理性の高い選択です。
- ピークシフト:オール電化プランなどで夜間電力が安い場合、その電気を蓄電池に貯め、電気代が高い昼間に使うことで、電気代の差額分を節約できます。
3-2. メリット②:災害・停電時の非常用電源(レジリエンス)
地震や台風などの天災で停電が発生した際、蓄電池は「在宅避難」を支える強力な味方になります。
- 最低限の生活維持:照明の確保、冷蔵庫の稼働(食料の保全)、スマートフォンの充電(情報収集)など、停電時でも最低限の生活と安心を維持できます。
- 太陽光との連携で長期化に対応:太陽光発電があれば、停電中も昼間に発電した電気を蓄電池に充電できます。これにより、停電が数日間続いた場合でも、電気を使い続けることが可能です。
3-3. 補助金がない場合の導入ポイント
もし補助金が利用できない、または打ち切りになった場合でも、以下のポイントを押さえることで、導入の費用対効果を高めることができます。
- 業者選びを慎重に行う:複数の業者から相見積もりを取り、価格競争力があり、かつ信頼できる施工業者を選びましょう。
- 自宅に適したスペックを選ぶ:ご家庭の電力使用量や停電時に使いたい家電に合わせて、オーバースペックにならない適切な容量・機能(全負荷型/特定負荷型など)の蓄電池を選びましょう。
【章のまとめ】
補助金が打ち切りになったとしても、蓄電池には「電気代削減」と「災害対策」という2つの大きな導入価値があります。初期費用だけでなく、長期的な安心と経済的メリットを含めたトータルコストで導入を判断しましょう。
蓄電池のメリット・デメリットを詳しく知りたい方へ
「電気代削減」と「停電対策」、蓄電池がもたらす2大メリットの具体的な内容や、導入前に知っておくべきデメリット(寿命・コストなど)を、専門家が基礎から解説した「蓄電池パーフェクトガイド」を無料でプレゼント中です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 蓄電池の国の補助金は、2025年はもう打ち切りですか?
「災害時に活用可能な~」など、過去に実施されていた一部の補助金は打ち切り(終了)となりました。しかし、2025年現在も、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の導入支援や、DER/VPP(分散型エネルギーリソース/仮想発電所)の実証事業に関連する補助金など、蓄電池が対象となる国の制度は形を変えて継続されています。
ただし、補助金を受けるための要件(高性能な機器、VPPへの参加など)が複雑化している傾向にあります。
Q2. 国と自治体の蓄電池補助金は併用できますか?
併用できる場合と、できない場合があります。これは、国と自治体、それぞれの補助金制度の「公募要領」や「交付規程」によって定められています。
「国の補助金(A)と自治体の補助金(B)は併用可」とされる一方、「国の補助金(A)と国の別の補助金(C)は併用不可」といったケースもあります。財源が同じ(例:どちらも国の予算)場合は併用できないことが多いため、申請前に必ず各制度の窓口や専門業者に確認が必要です。
Q3. 東京都の蓄電池補助金はまだ打ち切りになっていませんか?
はい、2025年10月現在、東京都は「自家消費プラン事業」などの名称で、太陽光発電や蓄電池の導入に対する手厚い補助金制度を継続しています。
予算額も大きく確保される傾向にありますが、年度ごとに予算が設定され、上限に達し次第受付終了となるため、導入を検討している場合は早めの情報収集と申請準備が不可欠です。
Q4. 補助金が打ち切りになったら、蓄電池を導入するのは損ですか?
一概に損とは言えません。補助金はあくまで初期費用を軽減する手段の一つです。蓄電池の主なメリットは、①太陽光発電と連携した電気代の削減(自家消費)、②停電時の非常用電源としての安心感、の2点です。
近年の電気代高騰や災害の頻発化を考慮すると、補助金がなくても、これらのメリットを重視して導入する価値は十分にあると考えられます。導入費用と長期的なメリット(電気代削減額+安心)を天秤にかけて判断することが重要です。
この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
光熱費削減コンサルタント
中田 萌ご相談やお見積もりは
完全無料です!


 蓄電池
蓄電池 太陽光発電
太陽光発電 パワーコンディショナ
パワーコンディショナ エコキュート
エコキュート IHクッキングヒーター
IHクッキングヒーター 外壁塗装
外壁塗装 ポータブル電源
ポータブル電源












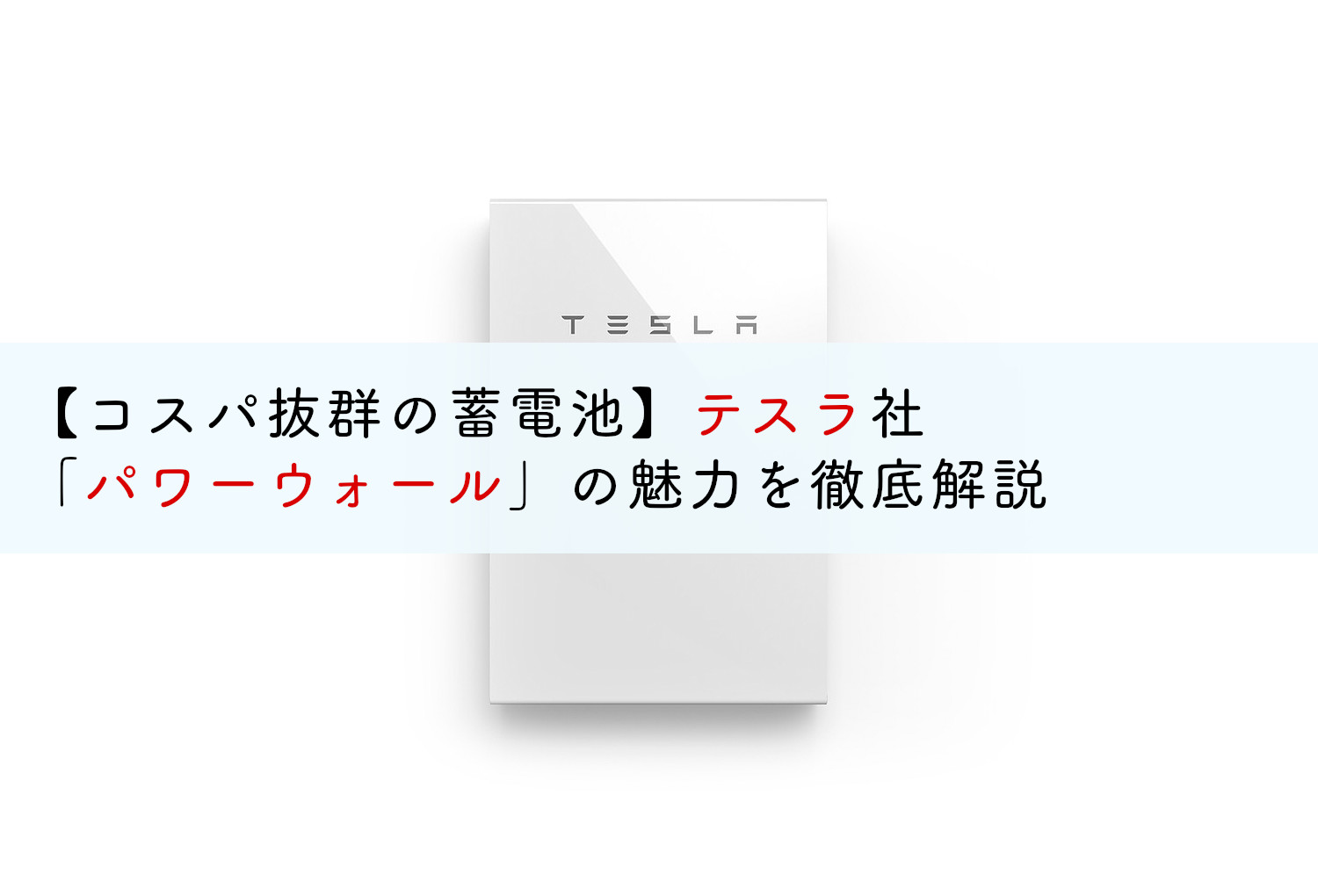







 蓄電池の選び方
蓄電池の選び方































