蓄電池価格推移を徹底解説!今後の予測とベストな買い時【2025年】

目次
はじめに:蓄電池の価格、どう変わってきた?今後はどうなる?
家庭用蓄電池の導入を検討する際、「価格が今後どうなるのか」「いつ買うのが一番お得なのか」といった点は、多くの方が気になるポイントではないでしょうか。特に、蓄電池は高価な設備であるため、その価格推移や将来の動向を把握し、最適なタイミングで導入したいと考えるのは自然なことです。この記事では、家庭用蓄電池の価格がこれまでどのように推移してきたのか、その背景にある要因、そして今後の価格動向に関する予測(2025年4月10日現在)を分かりやすく解説します。価格推移を知ることは、単に安い時期を狙うだけでなく、技術の進化や市場の成熟度を理解し、納得して導入を決断するためにも非常に重要です。
家庭用蓄電池の価格推移:過去から現在まで
家庭用蓄電池の価格は、技術の進化や市場環境の変化とともに大きく変動してきました。その歴史を振り返ることで、現在の価格水準や今後の動向を理解する手がかりが得られます。ここでは、蓄電池市場の黎明期から現在までの価格推移を、主な出来事とともに見ていきましょう。
蓄電池市場の黎明期(~2010年代初頭)
家庭用蓄電池という概念が広まる前の2010年代初頭頃まで、エネルギー貯蔵システムとしての蓄電池は、主に産業用や研究用、あるいは無停電電源装置(UPS)などの特殊な用途が中心でした。当時の主流であった鉛蓄電池は比較的安価でしたが、エネルギー密度や寿命の面で課題があり、家庭での日常的な利用には適していませんでした。リチウムイオン電池も存在しましたが、生産量が少なく、非常に高価であったため、一般家庭への普及は現実的ではありませんでした。この時期は、まさに家庭用蓄電池市場の夜明け前であり、技術開発が進む中で、将来の可能性が模索されていた段階と言えます。価格も現在の水準から見ると非常に高く、一部の先進的な取り組みを除き、一般消費者が気軽に導入できる状況ではありませんでした。
FIT制度開始と普及の加速(2012年~)
家庭用蓄電池の普及における大きな転換点となったのが、2012年に開始された再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)です。この制度により太陽光発電の導入が急速に進み、「発電した電気を貯めて使う」というニーズが高まりました。この需要増に応える形で、各メーカーはリチウムイオン電池を中心とした家庭用蓄電池の開発・生産を本格化させます。技術革新が進み、量産効果によって生産コストが徐々に低下し始め、蓄電池の価格は下落傾向に入りました。また、国や自治体による導入補助金制度も、初期の普及を後押しする重要な役割を果たしました。この時期、蓄電池はまだ高価な設備ではありましたが、太陽光発電との組み合わせによる経済メリットや環境意識の高まりから、一般家庭への導入事例が着実に増え始めたのです。価格はkWhあたり数十万円というレベルから、徐々に低下していきました。
近年の価格動向(2020年~現在)
2010年代を通じて低下傾向にあった蓄電池価格ですが、2020年頃からはそのペースが鈍化し、安定化、あるいは一部で上昇する動きも見られました。この背景には、世界的なEV(電気自動車)シフトによるリチウムなどの原材料価格の高騰、半導体不足、円安の進行といった外部要因が影響しています。一方で、技術開発は継続的に進んでおり、よりエネルギー密度が高く、長寿命な製品が登場しています。また、AIによる最適制御機能やV2H(Vehicle to Home)連携機能など、高付加価値なモデルも増え、製品ラインナップが多様化しました。さらに、頻発する自然災害を受けて、停電対策としての蓄電池の重要性が再認識され、安定した需要が市場を下支えしています。市場の成熟に伴いメーカー間の競争も激化しており、価格の維持・低下圧力とコスト上昇要因がせめぎ合う状況が続いています。資源エネルギー庁のデータによると、家庭用蓄電池システムの価格(工事費込み)は、2020年には1kWhあたり約18.7万円でしたが、その後は横ばいから微増傾向も見られました。
蓄電池の価格を変動させる要因
蓄電池の価格は、単一の理由で決まるわけではありません。技術、原材料、市場、政策といった様々な要因が複雑に絡み合って変動します。これらの要因を理解することで、今後の価格動向を予測する精度を高めることができます。
技術革新と生産コスト
蓄電池の価格低下を牽引してきた最大の要因は、リチウムイオン電池を中心とする技術革新です。エネルギー密度(単位体積・重量あたりに貯められるエネルギー量)の向上や、充放電サイクルの長期化(長寿命化)は、製品の価値を高めると同時に、実質的なコスト削減に繋がります。また、製造プロセスにおける歩留まりの改善や自動化による効率化、そして量産効果によるスケールメリットも、生産コストを引き下げる重要な要素です。将来的には、現在主流のリチウムイオン電池よりもさらに高性能で安価な次世代電池(全固体電池、ナトリウムイオン電池など)の実用化が期待されており、これが実現すれば、価格が大幅に下がるブレークスルーとなる可能性があります。ただし、新しい技術の導入初期には、研究開発費や設備投資がかさむため、一時的に価格が高くなる可能性も考慮する必要があります。
原材料価格の動向
蓄電池、特にリチウムイオン電池の主要な原材料であるリチウム、コバルト、ニッケルなどの国際価格は、価格変動の大きな要因となります。これらの資源は特定の国に偏在しており、採掘国の政情不安や需給バランスの変化によって価格が大きく変動するリスクがあります。近年、世界的なEV(電気自動車)の普及拡大に伴い、これらの原材料需要が急増し、価格が高騰する局面が見られました。こうした原材料価格の上昇は、蓄電池メーカーの製造コストを押し上げ、製品価格に転嫁される可能性があります。一方で、コバルトフリー電池の開発や、使用済み電池からの原材料リサイクル技術の進展は、特定の資源への依存度を下げ、価格安定化に寄与する可能性があります。サプライチェーンの安定性確保や、地政学的リスクも、中長期的な価格動向に影響を与える重要な要素です。
市場の需要と供給バランス
あらゆる製品と同様に、蓄電池の価格も市場における需要と供給のバランスによって影響を受けます。家庭用蓄電池の需要は、電気料金の動向、災害への備え意識、環境意識の高まり、住宅着工件数などに左右されます。また、産業用や電力系統用、そして急拡大するEV(電気自動車)市場での蓄電池需要も、原材料の需給を通じて家庭用蓄電池の価格に間接的な影響を与えます。供給サイドでは、国内外の蓄電池メーカーの生産能力や新規参入企業の動向が重要です.需要が供給を上回れば価格は上昇しやすく、逆に供給過剰になれば価格競争が激化し、価格は下落しやすくなります。政府の再生可能エネルギー導入目標なども、長期的な市場の方向性を左右し、需要と供給のバランスに影響を与えます。
国や自治体の政策・補助金
国や地方自治体による政策や補助金制度は、蓄電池の導入費用(実質価格)に直接的な影響を与えます。例えば、導入時に補助金が支給されれば、消費者の初期費用負担が軽減され、導入のハードルが下がります。補助金制度の予算規模や対象要件、期間は年度ごとに見直されることが多く、その内容変更は市場の需要を大きく変動させる可能性があります。過去には、補助金が手厚い時期に駆け込み需要が発生し、その後需要が落ち込むといった動きも見られました。また、FIT(固定価格買取制度)やその後継であるFIP(Feed-in Premium)制度、あるいはDR(デマンドレスポンス)への参加を促す制度なども、蓄電池導入の経済性を左右し、市場の活性化や価格形成に影響を与えます。税制優遇措置や新たな規制の導入・緩和なども、価格動向に関わる重要な政策要因です。
今後の蓄電池価格はどうなる?専門家の見解と予測
過去の推移と変動要因を踏まえ、今後の蓄電池価格がどのように動くのか、気になるところです。ここでは、短期および中長期的な価格予測に関する一般的な見解と、価格以外の価値の変化について解説します。ただし、これらはあくまで予測であり、不確定要素も多い点にご留意ください。
短期的な予測(~1~2年)
今後1~2年の短期的な価格動向については、多くの専門家が、これまでの急激な価格低下ペースは落ち着き、現状の価格水準が維持されるか、あるいは緩やかな低下にとどまるとの見方を示しています。その理由として、原材料価格がある程度高止まりしていること、高性能化・多機能化による製品単価の上昇、そして安定した需要が見込まれることなどが挙げられます。為替レートの変動も価格に影響を与える可能性があります。一方で、メーカー間の競争は継続しており、新製品の投入や販売戦略によっては、一部で価格が引き下げられる可能性も否定できません。国や自治体の補助金制度が継続されるかどうかも、実質的な導入コストに影響を与える重要なポイントです。全体としては、価格が大幅に下落することは期待しにくいものの、大きく上昇するリスクも限定的と考えられます。
中長期的な予測(~5~10年)
5年から10年といった中長期的な視点では、再び価格が低下していく可能性が高いと予測されています。その最大の推進力となるのが、技術革新です。特に、現在研究開発が進められている全固体電池などの次世代電池が実用化されれば、性能向上とコストダウンが両立し、価格が大幅に下がる可能性があります。また、EV市場の拡大に伴うさらなる量産効果や、リサイクル技術の確立による原材料コストの低減も期待されます。世界的なカーボンニュートラルへの流れの中で、再生可能エネルギーと蓄電池の導入はさらに加速すると考えられ、市場規模の拡大がコスト削減を後押しするでしょう。国際的な競争もより一層激しくなり、価格競争が進む可能性もあります。ただし、技術革新のスピードや地政学的リスクなど、不確実な要素も多く、予測通りに進むとは限りません。
価格以外の価値(機能・サービス)の変化
今後の蓄電池選びにおいては、単純な価格(kWhあたりの単価)だけでなく、製品が提供する付加価値がますます重要になると考えられます。例えば、太陽光発電やEVと連携してエネルギーを最適に制御するV2H(Vehicle to Home)機能や、AIが気象予報や電力使用パターンを学習して充放電を自動で最適化する機能などは、単に電気を貯めるだけではない価値を提供します。また、HEMS(Home Energy Management System)と連携し、家全体のエネルギーを効率的に管理する役割も重要度を増すでしょう。ソフトウェアのアップデートによって機能が向上したり、遠隔での見守りサービスが提供されたりすることも考えられます。将来的には、機器を買い取るだけでなく、月額料金で利用するサブスクリプションモデルのような新しい提供形態が登場する可能性もあります。長期保証や充実したアフターサービスも、価格以外の重要な選択基準となるでしょう。
蓄電池導入のベストな「買い時」はいつ?
「結局、蓄電池はいつ買うのが一番良いのか?」これは非常に悩ましい問題です。価格推移の予測はあくまで一つの判断材料であり、「買い時」は価格だけで決まるものではありません。ここでは、ベストな導入タイミングを見極めるための考え方をご紹介します。
価格推移だけでは判断できない理由
「もう少し待てば価格が下がるかもしれない」と考えるのは自然ですが、価格が下がるのを待つ間にも、失われるメリットがあることを考慮する必要があります。まず、蓄電池を導入すれば、その時点から電気代の削減効果を得られます。電気料金が高騰している状況では、早期導入による経済的メリットは大きくなります。また、停電時の安心感という価値は、価格では測れません。いつ起こるか分からない災害への備えは、早ければ早いほど良いとも言えます。さらに、新築やリフォーム、あるいは太陽光発電のFIT期間満了(卒FIT)といったライフイベントは、導入工事の効率や必要性を高める絶好のタイミングとなり得ます。補助金制度も、予算や期間が限られているため、利用可能なタイミングを逃さないことが重要です。一方で、技術は常に進歩しているため、最新機種を待つという考え方もありますが、技術の陳腐化リスクとのバランスを考える必要があります。
2025年現在の状況を踏まえた考え方
2025年4月現在、蓄電池の価格は一時期の急激な下落からは落ち着き、安定傾向にあります。しかし、原材料価格の高騰などの影響もあり、今後必ずしも大幅に安くなるとは限りません。一方で、国や自治体の補助金制度は依然として実施されており、これを活用すれば初期費用を抑えることが可能です。電気料金は依然として高い水準にあり、太陽光発電の自家消費率を高めることによる経済的メリットは大きいと言えます。また、近年の自然災害の増加を受け、レジリエンス(防災・減災)強化の観点からも、蓄電池の価値は高まっています。最新機種は、AI制御や高効率化など性能も向上しており、導入による満足度も高くなっています。これらの状況を総合的に勘案すると、補助金が利用できる現在のタイミングは、導入を検討する上で非常に有力な時期の一つであると言えるでしょう。
導入タイミングを判断するためのチェックリスト
最終的な導入タイミングは、個々の状況に合わせて判断する必要があります。以下の点をチェックし、ご自身にとっての「ベストタイミング」を見極めましょう。
- 経済性の試算:ご家庭の電気使用状況に基づき、蓄電池導入による電気代削減効果を試算し、初期費用(補助金適用後)が何年程度で回収できるかを確認する。
- 補助金の確認:国およびお住まいの自治体の補助金制度の内容、申請期間、条件、予算状況を最新情報で確認する。申請期限が迫っている場合は、早めの検討が必要。
- 必要性の明確化:なぜ蓄電池を導入したいのか(電気代削減、停電対策、環境貢献など)、目的を明確にし、それに合った容量や機能(全負荷/特定負荷、V2Hなど)を絞り込む。
- 見積もり比較:複数の信頼できる販売・施工業者から、希望する機種・システム構成で見積もりを取り、価格とサービス内容を比較検討する。
- ライフプランとの整合性:近い将来の引っ越しや大規模リフォームの予定はないか、家族構成の変化などを考慮し、長期的に使用できるかを確認する。
まとめ:価格推移を理解し、最適なタイミングで蓄電池を導入しよう
この記事では、家庭用蓄電池の価格推移とその背景、今後の予測、そして導入の「買い時」について解説しました。蓄電池の価格は、技術革新や量産効果により長期的には低下傾向にありましたが、近年は原材料価格の高騰などにより安定化しています。今後は、次世代電池などの技術革新による価格低下が期待される一方で、高機能化による付加価値も重要になってきます。
「買い時」は、単に価格が最も安い時期を待つことだけが正解ではありません。電気代削減効果や停電時の安心といった導入メリットをいつから享受したいか、補助金制度の活用タイミング、ご自身のライフイベントなどを総合的に考慮する必要があります。
2025年現在、価格は安定傾向にありますが、補助金制度が利用できる状況や電気代高騰の背景を考えると、導入を検討するには良い時期とも言えます。価格推移の情報を参考にしつつ、ご自身の状況に合わせてシミュレーションや情報収集を行い、必要であれば専門家にも相談しながら、納得のいくタイミングで蓄電池導入を決定しましょう。
よくある質問(Q&A)
Q1: 蓄電池の価格は、今後もっと安くなりますか?
A1: 中長期的には、技術革新(次世代電池など)や量産効果により、価格が再び低下していく可能性が高いと予測されています。しかし、短期的には原材料価格や為替の影響もあり、現状維持か緩やかな低下にとどまる可能性も指摘されています。大幅な価格低下の時期を正確に予測することは困難です。
Q2: 補助金はいつまで利用できますか?
A2: 国や自治体の補助金制度は、年度ごとに予算や内容が見直されます。予算上限に達し次第、早期に終了する場合もあります。最新の情報は、経済産業省や関連機関、お住まいの自治体のウェブサイト等で確認するか、販売店に問い合わせるのが確実です。2025年度の補助金情報も確認が必要です。
Q3: 価格が下がるのを待つべきでしょうか?
A3: 一概には言えません。価格が下がるのを待つ間に、電気代削減の機会損失や、補助金制度が終了・縮小するリスクもあります。また、停電への備えは早期に行うメリットがあります。価格だけでなく、導入メリット、補助金、ライフプランなどを総合的に考慮して判断することが重要です。
Q4: 蓄電池の価格は容量(kWh)あたりいくらくらいが目安ですか?
A4: 2025年4月現在、工事費込みの目安として、1kWhあたり約15万円~25万円程度がボリュームゾーンと考えられます。ただし、これは機種の機能(ハイブリッド/単機能、全負荷/特定負荷など)、メーカー、容量、工事内容によって大きく変動します。あくまで参考値として捉え、必ず個別に見積もりを取得してください。
Q5: 価格推移を知るために参考にできる公的なデータはありますか?
A5: 経済産業省資源エネルギー庁が定期的に公表している「定置用蓄電システムの普及拡大策の進捗状況」などの資料で、蓄電池システムの平均価格(工事費込み、kWh単価など)の推移データが示されることがあります。これらの公的資料は、市場全体の価格トレンドを把握する上で参考になります。
この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
光熱費削減コンサルタント
中田 萌ご相談やお見積もりは
完全無料です!


 蓄電池
蓄電池 太陽光発電
太陽光発電 パワーコンディショナ
パワーコンディショナ エコキュート
エコキュート IHクッキングヒーター
IHクッキングヒーター 外壁塗装
外壁塗装 ポータブル電源
ポータブル電源











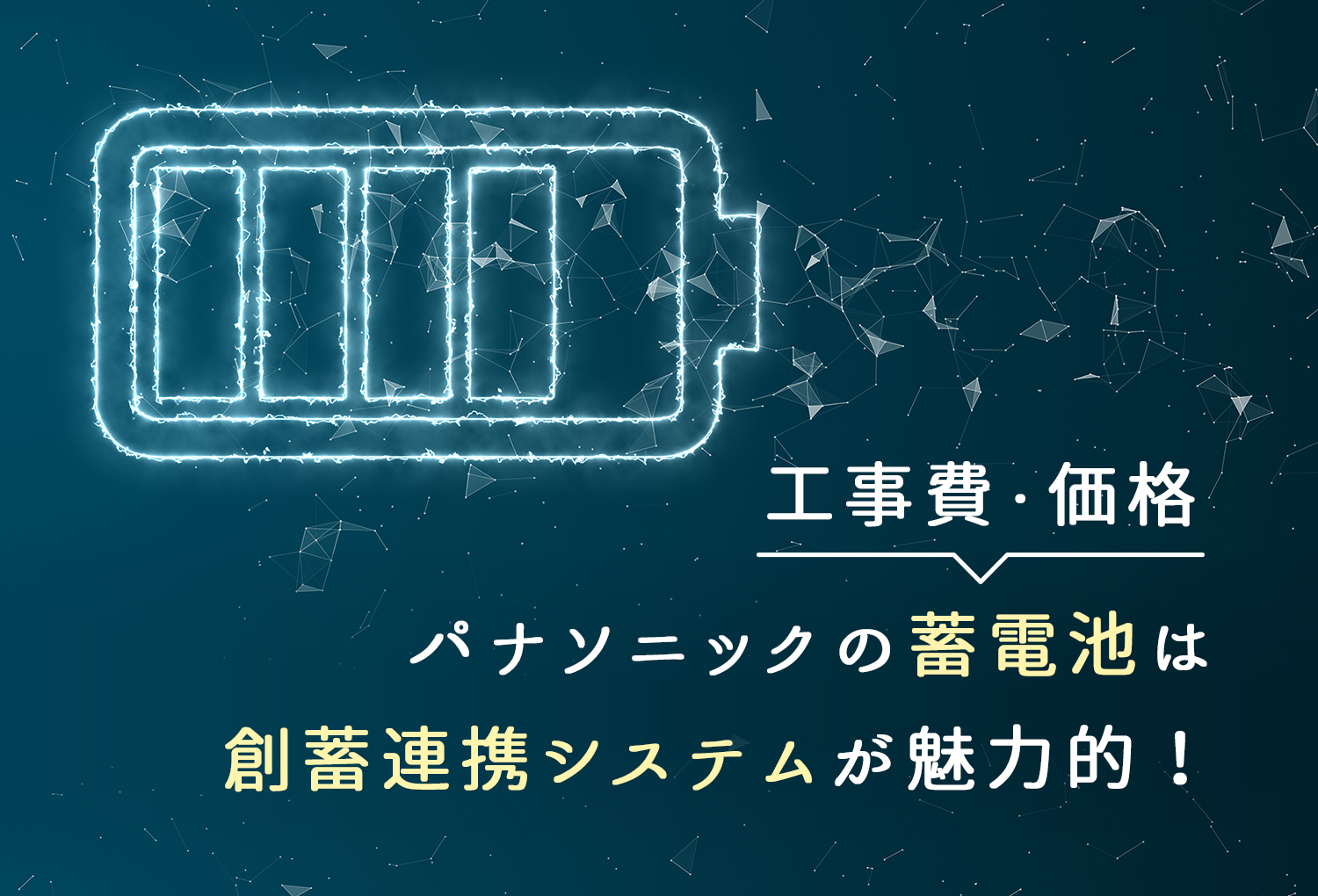








 蓄電池の選び方
蓄電池の選び方































