エコキュート凍結防止ガイド|冬でも安心の予防法・対処法をまとめて徹底解説!
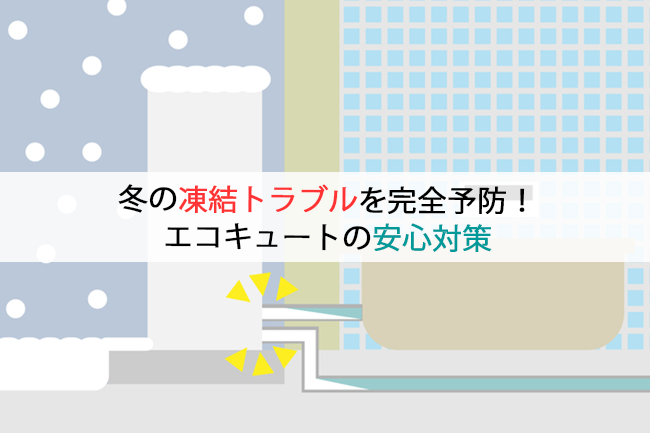
※本記事は、事業者から提供を受けた商品・サービスのPRを含む広告コンテンツです。
冬の寒さが厳しくなるにつれ、エコキュートの「凍結」が心配になる方は多いのではないでしょうか?特に、冬場の気温が「マイナス」まで下がる日の多い地域では、ヒートポンプや貯湯タンク付近の配管や、給湯・給水配管が凍ってお湯が使えなくなるトラブルが起こるケースも少なくありません。
一方で、エコキュートの凍結トラブルは、製造メーカーも推奨している「シンプルな方法」だけで予防できることも多く、万が一凍ってしまっても、「正しい対処法」を実践するだけで、慌てず解決することも可能です。
本記事では、エコキュートを凍結から守る「基本的な予防策」から、凍結した時の「安全な対処方法」、追加で検討したい「凍結予防のアイデア」まで徹底的にまとめています。「寒い冬でも心配せずに、快適にエコキュートを使いたい!」とお考えの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね!
目次
【メーカー推奨】エコキュートを凍結から守る「2つの予防法」
屋外設置が基本のエコキュートは、気温がマイナスを下回る日などに、各部の配管が凍結する可能性が少なからず存在します。「凍結してお湯が出ない…」といったトラブルを予防するために、各メーカーではユーザーがかんたんに実施できる凍結予防策を案内しています。
ここでは、特別な工具なしで日常的に実践できる、「2つのエコキュート凍結予防法」についてわかりやすくご紹介していきます。
予防法①:浴槽に水を張って「凍結予防運転」を作動させる
フルオートもしくはセミオートの機種の「ふろ配管」や「循環ポンプ」の凍結予防策として、各メーカーが推奨している方法は、「お風呂の水を残すか、ある程度水を張っておく」ことです。
多くのエコキュートには、外気温が0℃を下回った際に、自動でお風呂の水を循環させて凍結を防ぐ「凍結予防運転」という機能が搭載されており、特別な操作を行わなくても凍結トラブルを未然に防げます。運転中はリモコンに「凍結防止中」などの表示が出ますので、念のため確認しておくとさらに安心です。
浴槽に残しておく水の量は「循環アダプタから5〜10cm以上」が目安。前日の残り湯でも、新しく水を追加しても、どちらでもOKです。寒波が予想される夜は、浴槽の水を忘れずに残しておきましょう。
予防法②:「お湯側の蛇口」から水を少しずつ出し続ける
エコキュートの給湯タイプに関わらず、「給水配管・給湯配管」の凍結予防策として、各メーカーが推奨している方法は「お湯側の蛇口から水を少しづつ出し続ける」ことです。
具体的には、リモコンの湯温を「水」に設定し、お湯側の蛇口から「1分間に約200ml(コップ1杯分)」を目安に水を出し続けます。この操作により配管の内部に水の流れが生まれ、気温が下がっても凍結するトラブルを予防できるのです。
メーカーや機種により、設定温度が「水」ではなく「低温」という表示だったり、蛇口の開け方が異なるケースもあります。念のため取扱説明書を確認するか、メーカーや販売店に問い合わせてから作業するとより安心です。
うっかり凍結!そんなときに試したい「3つの対処法」
普段からエコキュートの凍結に気をつけていても、ついうっかり配管を凍らせてしまう可能性はゼロではありません。そんなときに焦って無理やりお湯や水を出そうとすると、かえって機器や配管を傷めてしまう危険も。大切なのは、「正しい手順」で安全に解凍することです。
そこで本項では、エコキュートが凍結してお湯が出ない際に試したい「3つの対処法」について解説していきます。
対処法①:急がないなら自然解凍を待つのが無難
エコキュートの配管が凍ってしまったとき、もっとも安全で確実な対処法は、「自然に溶けるのを待つ」ことです。日中に気温が上がれば配管内の氷は少しずつ解け、ふたたびお湯が使えるようになります。
このときにやってはいけないのが、熱湯を直接かけたり、ドライヤーやストーブで無理に温めたりすることです。急激な温度変化は配管や部品にダメージを与え、破損や水漏れにつながる恐れがあります。
すぐにお湯を使う必要がないのであれば、まずは気温の上昇を待ち、自然解凍に任せるのが一番安心な選択肢です。特に早朝に凍結した場合は、昼前には解消するケースも多いので、無理せずに様子を見ることをおすすめします。
対処法②:配管にぬるま湯をかけて溶かす
「自然に解凍するまで待てない」「どうしても今すぐお湯を使いたい」といった状況であれば、配管に「ぬるま湯」をかけて凍結を溶かす方法もあります。作業時に守るべきポイントは、「40℃程度のぬるま湯」を使うことです。
熱湯を直接かけると、急激な温度差で配管や継ぎ目が破損するリスクがあるため絶対に避けましょう。ぬるま湯をかける際には、配管にタオルなどを巻き、その上から少しずつお湯を注ぐと熱がやわらかく伝わり安全性が高まります。タオルが湯を保持することで効率よく解凍できるのもメリットです。
凍結が解けたら、蛇口をゆっくり開けて水が出るか確認してください。以上の対処法はあくまで応急処置であり、自然解凍に比べて少なからずリスクが生じる点は頭に入れておきましょう。
対処法③:自力が不安なら業者に相談するのもおすすめ
凍結を自分で解消するのが不安な方や、前述した対処法を試してもお湯が出ない場合などは、「専門業者へ相談する」方法が安心かつ確実です。特に真冬の寒冷地などでは、日中も氷点下が続き、自然解凍を待っていてもなかなか溶けないケースも考えられます。
無理に自力で解凍しようとして配管を破損させてしまうと、余計な修理費や復旧までの時間が発生し、かえって大きな負担になりかねません。業者に依頼すれば、プロならではの目線で解決方法を模索し、凍結防止の追加工事を提案してもらえることもあるでしょう。
業者に駆けつけ対応を依頼するため費用はかかりますが、エコキュートの凍結を「安全に」「早く」解決したい場合には、もっとも堅実な選択肢といえるでしょう。
エコキュート凍結の可能性をさらに下げたい!検討すべき「3つのアイデア」
多くのエコキュート凍結トラブルは、「凍結予防運転の実施」や「蛇口から水を出し続ける」といった、メーカー推奨の予防策で解決可能です。しかし、寒さが特に厳しい地域や、過去に凍結トラブルを経験した家庭では、「それだけでは不安」という声も少なくないでしょう。
そんなときに役立つのが、「後付けできる凍結防止の工夫」です。ここでは、エコキュートの凍結リスクをさらに下げるために、検討したい「3つのアイデア」をご紹介していきます。
アイデア①:「凍結防止ヒーター」を取り付ける
寒冷地のエコキュート凍結対策として、特に効果的なのが「凍結防止ヒーター」の設置です。凍結防止ヒーターは配管に沿わせて取り付ける電熱ヒーターの一種で、外気温が下がったときに自動で作動し、配管をほんのり温めて凍結を防ぎます。
寒冷地仕様のエコキュートなど、すでに工場出荷時から凍結防止ヒーターが装備されているモデルもありますが、後付けタイプも販売されており、既存のエコキュートの配管にも取り付け可能です。
ヒーター自体の消費電力はわずかであり、特に氷点下の日が続く地域では、基本の予防法と併用することで、冬場でも安定してお湯が使える安心感が大きく高まります。
アイデア②:「脚部化粧カバー」を取り付ける
貯湯タンクの下部に取り付ける「脚部化粧カバー」は、外観デザインの向上や飛来物・雑草などから設備を守るだけでなく、配管や部品を寒さから守る役割もあります。外気に直接さらされるタンク脚部の配管は凍結しやすいため、脚部化粧カバーを付けることで直接冷気が当たるのを防ぎ、凍結リスクを下げられます。
特に冬の夜間に風が強く吹く地域では、脚部化粧カバーを取り付ける効果は大きいでしょう。カバーの取り付けは比較的かんたんであり、工具があれば自分でも取り付け可能です。また、脚部化粧カバーと合わせて「保温材」などを巻くと、さらに凍結防止効果が高まります。
アイデア③:配管に「保温材」「保温カバー」を取り付ける
エコキュートの配管や給水・給湯配管自体に「保温材」や「保温カバー」を巻くことも、冬場の凍結リスクを減らせる有効策のひとつです。給水・給湯配管は外気に触れると凍りやすく、地面近くや外壁沿いの配管は特に注意が必要となります。
市販の保温材はかんたんに巻けるタイプも多く、配管に沿わせて固定するだけで断熱効果が得られます。さらに、配管全体を覆う保温カバーを使えば、風や寒気からの影響を抑えられるでしょう。保温材や保温カバーの取り付け難易度は低いため、専門知識がなくてもDIY感覚で施工が可能です。基本の予防法やヒーター・脚部カバーと組み合わせることで、冬場の安心度は格段に上がります。
これからエコキュートを設置するなら「寒冷地仕様」もおすすめ!
冬場の寒さが厳しい地域にエコキュートを新しく設置するなら、「寒冷地仕様モデル」を選ぶのも非常に有効です。一般地仕様モデルの多くは対応外気温が「-10℃」前後ですが、寒冷地仕様は「-20〜‐25℃」まで対応しており、安心感が違います。
一般地仕様との具体的な違いとして、寒冷地仕様には、給湯配管やヒートポンプ本体に標準で「凍結防止機能」が組み込まれており、外気温が氷点下に下がっても内部配管の凍結を自動で予防します。さらに、屋外に露出する配管には凍結防止ヒーターを標準装備、ヒートポンプの性能向上など、各部に強化が施されています。
寒冷地仕様は「一般地仕様より本体価格が高い」点がデメリットではあるものの、一般地仕様に凍結防止ヒーターなどを後付けする手間やコストを考えれば、設置時点で寒冷地仕様を選ぶほうが長期的には経済的、かつ安全性も高い選択といえるでしょう。
特に、北海道や東北などの一部地域では、本記事でご紹介した基本予防策に加えて、寒冷地仕様のエコキュートを選ぶことで、凍結トラブルの心配を大幅に減らすことができます。
参考:USサービス / 大真エンジニアリング
まとめ:冬場のエコキュート凍結対策は正しい「予防法」「対処法」が肝心!
冬場のエコキュート凍結を防ぐためには、「浴槽に水を残して凍結予防運転を作動させる」「お湯側の蛇口から少量の水を流し続ける」など、メーカーも公式に推奨している「基本的な予防法」を確実に実践することが大切です。
翌日の外気温がマイナスを下回りそうなタイミングで以上の予防策を実施することで、特別な工具や知識がなくても、多くの凍結トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
万が一、配管が凍結してお湯が出なくなってしまった場合は、「自然解凍を待つ」ことが、もっとも安全で確実な対処法です。急ぎの場合は「40℃前後のぬるま湯をタオル越しにかける」方法も一定の効果があります。自力での解決が不安な場合や、自然解凍が望めない極寒地域では、専門業者に相談することも検討しましょう。
凍結のリスクをさらに減らすためには、「凍結防止ヒーター」や「脚部カバー」、「配管保温材」などの取り付けも効果的。これからエコキュートを新しく設置する場合は、寒さや凍結に強い「寒冷地仕様」モデルがおすすめです。「正しい予防策」と「万が一の対処法」を組み合わせて、冬場でも快適にエコキュートを使っていきましょう!
この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
光熱費削減コンサルタント
中田 萌ご相談やお見積もりは
完全無料です!


 蓄電池
蓄電池 太陽光発電
太陽光発電 パワーコンディショナ
パワーコンディショナ エコキュート
エコキュート IHクッキングヒーター
IHクッキングヒーター 外壁塗装
外壁塗装 ポータブル電源
ポータブル電源











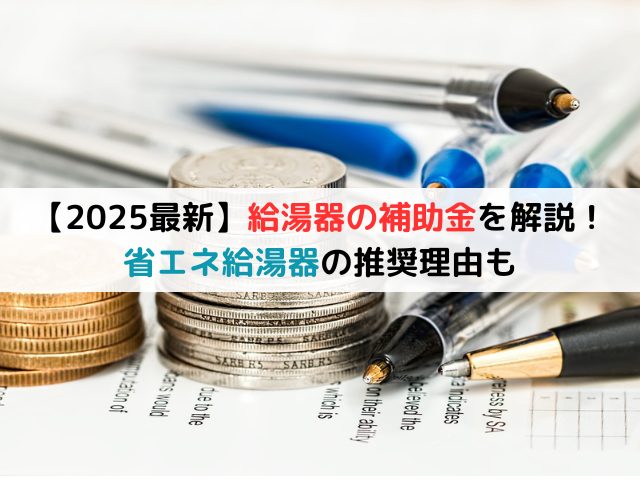
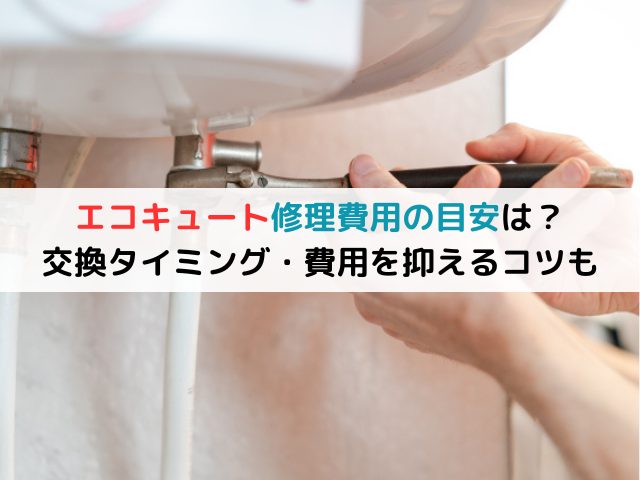







 蓄電池の選び方
蓄電池の選び方































