太陽光発電に蓄電池を後付けする価格と費用の完全ガイド

目次
太陽光発電の蓄電池後付けにかかる価格の基本情報
太陽光発電システムに蓄電池を後付けする際の価格は、蓄電池本体の容量や性能、工事内容によって大きく変動します。一般的な家庭用蓄電池の価格相場は、4kWh程度の小容量タイプで80万円から150万円、7kWh程度の中容量タイプで120万円から200万円、10kWh以上の大容量タイプで180万円から300万円程度となっています。
蓄電池の後付け価格は、本体価格に加えて工事費用も含めて検討する必要があります。工事費用は一般的に20万円から50万円程度かかり、設置環境や配線工事の複雑さによって変動します。また、既存の太陽光発電システムとの連携を考慮した適切な蓄電池選びが重要で、メーカー間の互換性や発電量に見合った容量選択が価格効率を左右します。
近年は蓄電池の技術革新により価格が下降傾向にあり、2025年現在では1kWhあたり15万円から25万円程度が相場となっています。ただし、高性能なリチウムイオン電池や長期保証付きの製品は価格が高めに設定されており、初期投資と長期的なコストパフォーマンスのバランスを考慮した選択が求められます。
蓄電池後付け価格の詳細な内訳
蓄電池本体価格の構成要素
蓄電池本体の価格は主に蓄電容量、電池の種類、インバーター性能、保証期間によって決まります。リチウムイオン電池が主流となっており、エネルギー密度が高く長寿命である反面、鉛蓄電池と比較して価格が高めに設定されています。また、ハイブリッド型インバーターを搭載した製品は、太陽光発電との連携効率が高い分、価格も上昇する傾向があります。
蓄電池の価格設定においては、メーカーの技術力やブランド価値も影響しており、大手メーカーの製品は品質の安定性や充実したアフターサービスを提供する代わりに価格が高めになっています。国内メーカーの製品は海外製品と比較して20%から30%程度価格が高い傾向にありますが、日本の気候条件に適した設計や手厚いサポート体制が価格差の要因となっています。
容量別の価格帯としては、4kWh未満の小容量タイプが70万円から120万円、4kWh以上7kWh未満の中容量タイプが100万円から180万円、7kWh以上の大容量タイプが150万円から280万円程度となっており、容量の増加に伴い1kWhあたりの単価は若干安くなる傾向があります。
工事費用の詳細
蓄電池の後付け工事費用は、設置場所の準備、電気工事、システム連携工事に分けられます。設置場所の準備には基礎工事や搬入経路の確保が含まれ、一般的に5万円から15万円程度の費用がかかります。電気工事は分電盤の改修や配線工事が主な内容で、10万円から25万円程度が相場となっています。
既存の太陽光発電システムとの連携工事が最も重要で、パワーコンディショナーの交換や追加設置が必要な場合は工事費用が大幅に増加します。パワーコンディショナーの交換が必要な場合は追加で20万円から40万円、新規設置の場合は15万円から30万円程度の費用が発生します。
工事費用は設置環境によって大きく変動し、屋外設置の場合は屋内設置と比較して防水工事や耐候性対策が必要となるため、5万円から10万円程度の追加費用がかかります。また、2階建て以上の住宅では高所作業が必要となり、足場設置費用として3万円から8万円程度が追加されることもあります。
付帯費用とその他の経費
蓄電池導入には本体価格と工事費用以外にも様々な付帯費用が発生します。設置前の現地調査費用として2万円から5万円、電力会社への系統連系申請費用として3万円から8万円程度が必要となります。また、建築確認申請が必要な場合は10万円から20万円の追加費用が発生することもあります。
保険料や保証延長オプションも考慮すべき費用項目で、火災保険の保険料増額分として年間5千円から1万円程度、メーカー保証の延長オプションは蓄電池価格の3%から5%程度が相場となっています。10年間の延長保証を付ける場合、総費用の3%から8%程度の追加投資が必要ですが、長期的な安心を得られるメリットがあります。
メンテナンス費用として年間1万円から3万円程度を想定しておく必要があり、定期点検や清掃、消耗品の交換などが含まれます。これらの付帯費用を含めると、蓄電池導入の総費用は表示価格より15%から25%程度高くなることを考慮して予算計画を立てることが重要です。
メーカー別蓄電池価格比較
国内主要メーカーの価格帯
国内の主要蓄電池メーカーとして、パナソニック、シャープ、京セラ、オムロンなどが挙げられ、それぞれ特徴的な価格設定を行っています。パナソニックの創蓄連携システムは5kWhタイプで160万円から200万円程度、シャープのクラウド蓄電池システムは4kWhタイプで120万円から160万円程度が相場となっています。
京セラのEGS蓄電システムは6.5kWhタイプで150万円から190万円程度、オムロンのKPACシリーズは9.8kWhタイプで180万円から220万円程度の価格帯で展開されています。国内メーカーの製品は価格が高めですが、日本の気候条件に最適化された設計と充実したアフターサービスが価格に反映されています。
各メーカーの価格差は主に技術仕様の違いによるもので、パナソニックは高効率のリチウムイオン電池技術により価格が高めに設定されている一方、シャープはコストパフォーマンスを重視した価格設定となっています。また、太陽光発電システムと同一メーカーで統一する場合は、セット割引により5%から15%程度の価格優遇を受けられることもあります。
海外メーカーの価格動向
海外メーカーの蓄電池は国内メーカーと比較して価格競争力が高く、同容量でも20%から40%程度安価に設定されています。テスラのPowerwallは13.5kWhで180万円から220万円程度、LG化学のRESU
シリーズは6.4kWhで100万円から140万円程度となっています。
中国系メーカーのBYDやCATLなどの製品は更に価格が安く、10kWhクラスでも120万円から160万円程度で提供されています。海外メーカーの製品は価格面でのメリットが大きいものの、日本国内でのサポート体制や保証内容を十分に確認する必要があります。
韓国系メーカーのサムスンSDIやLG化学は技術力が高く、価格と性能のバランスが取れた製品を提供しており、国内メーカーと海外メーカーの中間的な価格帯で展開されています。ただし、海外メーカーの製品を選択する際は、国内の電気事業法や建築基準法への適合性を確認し、認証取得済みの製品を選ぶことが重要です。
容量別価格比較
蓄電池の容量別価格比較では、小容量タイプ(4kWh未満)、中容量タイプ(4-7kWh)、大容量タイプ(7kWh以上)に分けて検討することが一般的です。小容量タイプは一人暮らしや電力使用量が少ない家庭向けで、80万円から130万円程度の価格帯となっています。
中容量タイプは一般的な3-4人家族に適しており、120万円から200万円程度が相場となっています。7kWh程度の中容量タイプは価格と実用性のバランスが最も優れており、多くの家庭で導入されている人気の容量帯です。
大容量タイプは電力使用量が多い家庭や停電時の長時間バックアップを重視する場合に選ばれ、180万円から300万円程度の価格帯となっています。1kWhあたりの単価は容量が大きくなるほど安くなる傾向があり、大容量タイプでは15万円から20万円程度、小容量タイプでは20万円から25万円程度が相場となっています。
蓄電池後付け工事の価格要素
設置環境による価格差
蓄電池の設置環境は工事費用に大きく影響する要素で、屋内設置と屋外設置、設置階数、アクセス性などによって価格が変動します。屋内設置の場合は基本的な電気工事のみで済むため、工事費用は15万円から30万円程度に抑えられます。一方、屋外設置では防水工事や基礎工事が必要となり、25万円から45万円程度の工事費用がかかります。
設置場所のアクセス性が悪い場合は、クレーン作業や特殊な搬入方法が必要となり、追加費用として10万円から20万円程度が発生することがあります。2階以上への設置では足場設置や高所作業費用として5万円から15万円程度の追加費用が必要となります。
地盤の状況も工事費用に影響し、軟弱地盤や傾斜地への設置では基礎工事が複雑になるため、追加費用として5万円から15万円程度が必要となることがあります。また、積雪地域では耐雪仕様の基礎工事や防雪対策が必要となり、通常より10万円から20万円程度高くなる傾向があります。
電気工事の複雑さと費用
蓄電池の電気工事は既存の太陽光発電システムとの連携を考慮した設計が必要で、工事の複雑さによって費用が大きく変動します。最も基本的な工事は分電盤からの配線工事で、10万円から20万円程度が相場となっています。パワーコンディショナーの交換や追加設置が必要な場合は、20万円から40万円程度の追加費用が発生します。
既存の太陽光発電システムのメーカーと蓄電池のメーカーが異なる場合は、互換性の確保のための特殊な工事が必要となり、費用が通常より20%から30%程度高くなることがあります。また、古い太陽光発電システムの場合は、安全性確保のための追加工事が必要となることもあります。
系統連系保護装置の設置や電力会社との連系工事も必要で、これらの費用として5万円から15万円程度が追加されます。スマートメーターの交換が必要な場合は電力会社の費用負担となりますが、連系工事の調整費用として2万円から5万円程度が必要となることがあります。
追加工事が必要なケース
蓄電池の後付けにおいて追加工事が必要となるケースは多岐にわたり、事前の現地調査で判明することが一般的です。最も多いケースは分電盤の容量不足で、容量アップのための交換工事として15万円から30万円程度の費用が発生します。配線ルートの変更が必要な場合は、壁の開口工事や配管工事として5万円から15万円程度の追加費用がかかります。
建物の構造上の制約により、補強工事が必要となる場合は20万円から50万円程度の大幅な追加費用が発生することがあります。特に築年数が古い住宅では、現在の建築基準に適合させるための改修工事が必要となることがあり、事前の詳細な現地調査が重要です。
近隣との境界に関する問題で設置場所の変更が必要な場合は、配線工事の追加として10万円から25万円程度の費用が発生します。また、電波障害対策や騒音対策が必要な場合は、防音工事や電波シールド工事として5万円から20万円程度の追加投資が必要となることもあります。
補助金制度を活用した実質価格
国の補助金制度
蓄電池導入に対する国の補助金制度は、再生可能エネルギーの普及促進を目的として実施されており、2025年度も継続されています。経済産業省が所管する「蓄電池等の分散型エネルギーリソースを活用したVPP構築実証事業」では、蓄電池導入費用の一部が補助対象となっており、1kWhあたり3万円から5万円程度の補助金が支給されます。
国の補助金制度を活用することで、蓄電池の導入費用を10%から20%程度削減することが可能です。ただし、補助金の申請には一定の条件があり、VPP(バーチャルパワープラント)への参加や実証実験への協力が必要となる場合があります。
また、環境省が所管する「脱炭素社会の実現に向けた電気自動車の普及促進に関する実証事業」では、V2H(Vehicle to
Home)システムと連携した蓄電池導入に対して追加的な補助金が支給されることがあります。これらの補助金制度は年度ごとに内容が変更されるため、最新の情報を確認して申請することが重要です。
地方自治体の補助金
地方自治体による蓄電池導入補助金は、自治体ごとに異なる制度設計となっており、補助金額や対象要件も多様です。東京都では「家庭における蓄電池導入促進事業」として、蓄電池設置費用の10分の1以内で最大60万円の補助金を支給しています。神奈川県では「分散型エネルギーシステム導入促進事業」として、1kWhあたり2万円の補助金を支給しています。
市区町村レベルでも独自の補助金制度を設けている自治体が多く、国や都道府県の補助金と併用することで更なる負担軽減が可能です。例えば、世田谷区では区独自の補助金として蓄電池導入費用の20%以内で最大20万円を支給しており、東京都の補助金と合わせて活用することができます。
地方自治体の補助金制度は予算の上限に達した時点で受付終了となることが多いため、早期の申請が重要です。また、申請手続きの複雑さや必要書類も自治体によって異なるため、事前に詳細な情報収集を行い、販売業者のサポートを受けながら申請することが推奨されます。
電力会社の優遇制度
電力会社による蓄電池導入優遇制度は、電力の安定供給と需給バランスの改善を目的として提供されています。東京電力エナジーパートナーの「スマートライフプラン」では、蓄電池を導入した家庭に対して特別な電気料金プランを提供し、深夜電力の割引率を拡大しています。
関西電力の「はぴeタイムR」では、蓄電池導入家庭を対象とした時間帯別料金制度により、電気代の削減効果を最大化できる料金プランを提供しています。電力会社の優遇制度を活用することで、蓄電池の導入効果を最大化し、投資回収期間を短縮することが可能です。
九州電力の「太陽光発電余剰電力買取制度」では、蓄電池を導入した家庭に対して余剰電力の買取価格を優遇する制度を設けています。これらの制度は電力会社や地域によって内容が異なるため、居住地域の電力会社に確認し、最適な料金プランを選択することが重要です。
蓄電池後付けの費用対効果
電気代削減効果
蓄電池を後付けすることによる電気代削減効果は、家庭の電力使用パターンや電気料金プランによって大きく異なります。一般的な家庭では、深夜の安価な電力を蓄電し、昼間の高価な電力使用を削減することで、月額3,000円から8,000円程度の電気代削減が期待できます。太陽光発電との組み合わせにより、売電せずに自家消費する電力量を増やすことで、更なる経済効果を得ることができます。
7kWh程度の蓄電池を導入した場合、年間5万円から12万円程度の電気代削減効果が期待でき、10年間で50万円から120万円程度の経済メリットが見込めます。ただし、この効果は電気料金の値上がりや太陽光発電の発電量、家庭の電力使用パターンによって変動するため、個別の試算が重要です。
時間帯別料金制度を活用することで削減効果を最大化できますが、料金制度の変更リスクも考慮する必要があります。近年は電気料金の値上がり傾向が続いており、蓄電池による電気代削減効果も相対的に高まっています。また、電力市場の変動や燃料価格の上昇により、将来的には更なる削減効果の拡大が期待されます。
投資回収期間の計算
蓄電池導入の投資回収期間は、導入費用と年間の経済効果から算出されます。150万円の蓄電池を導入し、年間8万円の電気代削減効果がある場合、単純計算で約19年の投資回収期間となります。しかし、補助金の活用により導入費用を120万円に削減できれば、投資回収期間は約15年に短縮されます。
投資回収期間の計算では、電気代削減効果だけでなく、災害時の経済的価値や電気料金の将来的な上昇も考慮する必要があります。停電時のバックアップ電源としての価値を年間5万円程度と評価した場合、実質的な投資回収期間は2-3年短縮されることになります。
蓄電池の寿命は一般的に10-15年程度とされており、投資回収期間がこの範囲内に収まることが経済的な導入の目安となります。また、蓄電池の性能向上により、将来的にはより短期間での投資回収が期待できます。メンテナンス費用や交換費用も含めた総合的な収支計算を行い、長期的な経済性を評価することが重要です。
災害時の価値
蓄電池の災害時における価値は、経済的な計算だけでは測れない重要な要素です。停電時に冷蔵庫、照明、通信機器などの重要な電気機器を継続使用できることは、生活の質の維持と安全性の確保に直結します。7kWh程度の蓄電池があれば、省エネ機器を使用した場合に2-3日間の電力供給が可能となります。
災害時の蓄電池による経済的価値を年間3万円から5万円程度と評価すると、投資回収期間の計算において無視できない要素となります。特に台風や地震などの自然災害が多い地域では、この価値は更に高く評価されます。
近年の異常気象により停電のリスクが高まっており、蓄電池の災害対策価値は年々上昇しています。また、在宅勤務の普及により、停電時の通信機器やパソコンの電源確保の重要性も高まっています。これらの社会的変化を考慮すると、蓄電池の災害時価値は従来の評価より高く設定することが妥当と考えられます。
蓄電池選びのポイント
容量選択の基準
蓄電池の容量選択は、家庭の電力使用パターンと停電時の必要電力を基準に決定します。一般的な4人家族の場合、1日の電力使用量は10-15kWh程度であり、このうち夜間に使用する電力量は4-7kWh程度となります。太陽光発電システムがある場合は、昼間の余剰電力を蓄電し、夜間に使用するパターンを考慮する必要があります。
停電時の必要最小限の電力として、冷蔵庫、照明、通信機器の使用を想定すると、1日あたり3-5kWh程度の容量が必要となります。3日間の停電に備える場合は、最低でも10kWh程度の容量が推奨されます。ただし、省エネ機器の使用や節電意識により、実際の必要容量は削減可能です。
容量選択においては、蓄電池の実効容量も考慮する必要があります。蓄電池は満充電から完全放電まで使用すると寿命が短くなるため、実際には80-90%程度の容量しか使用できません。表示容量10kWhの蓄電池でも、実効容量は8-9kWh程度となることを前提として選択することが重要です。
メーカー選択の判断基準
蓄電池メーカーの選択は、技術力、品質、保証内容、価格、アフターサービスを総合的に評価して決定します。国内メーカーは日本の気候条件や電力事情に適した製品開発を行っており、品質の安定性と充実したサポート体制が特徴です。パナソニック、シャープ、京セラなどの国内大手メーカーは、長期保証と全国規模のサービス網を提供しています。
海外メーカーの製品は価格競争力が高い一方で、国内でのサポート体制や部品供給の継続性を十分に確認する必要があります。テスラ、LG化学、BYDなどの海外メーカーは技術力が高く、コストパフォーマンスに優れた製品を提供していますが、日本国内での実績や認証取得状況を確認することが重要です。
メーカー選択においては、既存の太陽光発電システムとの互換性も重要な要素となります。同一メーカーで統一することで、システム全体の効率向上と保証の一元化が可能となります。また、将来的な製品サポートの継続性や部品供給の安定性も長期使用を考慮した重要な判断基準となります。
設置場所の検討事項
蓄電池の設置場所は、安全性、効率性、メンテナンス性を考慮して決定する必要があります。屋内設置の場合は、温度管理がしやすく、盗難や天候の影響を受けにくいメリットがあります。ただし、設置スペースの確保と換気設備の整備が必要となります。屋外設置の場合は、設置スペースの制約が少ない反面、防水・防塵対策と温度管理が重要となります。
蓄電池の性能は周囲温度に大きく影響されるため、直射日光や高温多湿を避けた場所への設置が重要です。理想的な設置環境は、温度変化が少なく、通風が良好で、メンテナンスアクセスが容易な場所となります。
設置場所の選定においては、近隣への影響も考慮する必要があります。蓄電池の運転音や設置による日照の影響、外観の変化などについて、事前に近隣への説明と了解を得ることが重要です。また、将来的な住宅の改修や売却時の影響も考慮し、撤去や移設が容易な場所を選択することが推奨されます。
信頼できる業者選びと価格交渉
業者選定のチェックポイント
蓄電池の導入業者選定においては、技術力、実績、価格、アフターサービスを総合的に評価することが重要です。まず確認すべきは、電気工事士の資格を持つ技術者が在籍しているかどうかです。蓄電池の設置には第二種電気工事士以上の資格が必要であり、無資格者による工事は法令違反となります。
業者の実績として、年間の蓄電池設置件数や施工実績、顧客満足度などを確認し、信頼できる業者を選定することが重要です。また、メーカーの認定施工店であることも品質保証の観点から重要な要素となります。認定施工店はメーカーからの技術サポートを受けられ、保証内容も充実しています。
業者選定においては、見積もりの内容が詳細で透明性があることも重要な判断基準となります。工事内容、使用機器、費用内訳が明確に記載されており、追加費用の可能性についても事前に説明がある業者を選ぶことが推奨されます。また、契約後のアフターサービス体制や緊急時の対応についても確認することが重要です。
相見積もりの活用方法
蓄電池導入の価格交渉において、相見積もりは非常に有効な手段です。3-5社程度の業者から見積もりを取得し、価格だけでなく、工事内容、使用機器、保証内容を比較検討することが重要です。見積もり依頼時には、同一条件での比較ができるよう、希望する蓄電池の容量、設置場所、工事内容を明確に伝えることが必要です。
相見積もりの結果を基に価格交渉を行う際は、最安値の業者を選ぶのではなく、価格と品質のバランスを総合的に評価することが重要です。極端に安い見積もりは、工事品質や使用機器のグレードが低い可能性があるため、内容を詳細に確認する必要があります。
価格交渉においては、現金一括払いによる割引や、複数の住宅設備機器の同時導入による割引などの交渉余地があります。また、閑散期の工事や平日の工事により、工事費用の削減が可能な場合もあります。ただし、価格のみを重視するのではなく、長期的な信頼関係を築ける業者との取引を優先することが重要です。
契約時の注意点
蓄電池導入の契約時には、契約内容を詳細に確認し、不明な点は事前に解決することが重要です。まず確認すべきは、工事内容と費用の内訳が明確に記載されているかどうかです。追加工事が必要となった場合の費用負担についても、事前に取り決めておくことが重要です。
保証内容については、メーカー保証と施工保証の両方を確認し、保証期間や保証範囲、保証を受けるための条件を明確にしておく必要があります。特に、蓄電池の性能保証については、容量保持率や充放電回数の保証内容を詳細に確認することが重要です。
契約解除に関する条件も重要な確認事項であり、クーリングオフの適用期間や契約解除時の費用負担についても事前に確認しておく必要があります。また、工事完了後の引き渡し時期や動作確認の方法、操作説明の内容についても契約書に明記されていることを確認することが重要です。
まとめ
太陽光発電システムに蓄電池を後付けする価格は、蓄電池の容量や性能、設置環境、選択する業者によって大きく変動します。一般的な価格相場は、4-7kWhの中容量タイプで120万円から200万円程度、工事費用を含めた総費用は150万円から250万円程度となります。
国や地方自治体の補助金制度を活用することで、導入費用を10-30%程度削減することが可能であり、電力会社の優遇制度と組み合わせることで、経済効果を最大化できます。投資回収期間は一般的に12-18年程度ですが、電気代の上昇や災害時の価値を考慮すると、実質的な回収期間は短縮されます。
蓄電池選びにおいては、家庭の電力使用パターンに適した容量選択と、信頼できるメーカー・業者の選定が重要です。複数業者からの相見積もりを活用し、価格と品質のバランスを総合的に評価して、最適な蓄電池システムを導入することが、長期的な満足度向上につながります。
よくある質問
Q1: 蓄電池の後付け工事にはどのくらいの期間がかかりますか?
A1:
蓄電池の後付け工事期間は、設置環境や工事内容によって異なりますが、一般的には1-3日程度で完了します。屋内設置の場合は1日、屋外設置で基礎工事が必要な場合は2-3日かかることが多いです。ただし、パワーコンディショナーの交換や電力会社との系統連系手続きが必要な場合は、2週間から1ヶ月程度の期間が必要となることもあります。
Q2: 既存の太陽光発電システムと蓄電池の相性が悪い場合はどうなりますか?
A2:
既存の太陽光発電システムと蓄電池の相性が悪い場合、システム効率の低下や正常な動作ができない可能性があります。このような場合は、パワーコンディショナーの交換や変換器の追加設置により対応できますが、追加費用として20-50万円程度が必要となります。事前の現地調査で互換性を確認し、必要な対策を検討することが重要です。
Q3: 蓄電池の寿命が来た場合の交換費用はどのくらいかかりますか?
A3:
蓄電池の寿命は一般的に10-15年程度で、交換時期が来た場合の費用は新規導入時の70-80%程度となることが多いです。7kWhの蓄電池の場合、交換費用は100-150万円程度が見込まれます。ただし、技術革新により価格が下がる可能性もあり、将来的にはより安価な交換が期待できます。また、部分的な交換や性能向上による延命も可能な場合があります。
Q4: 蓄電池導入後の電気料金プランはどのように選べばよいですか?
A4:
蓄電池導入後は、時間帯別料金制度を活用することで経済効果を最大化できます。深夜電力が安価で昼間の電力が高価な料金プランを選び、深夜に蓄電して昼間に使用することで電気代を削減できます。電力会社ごとに蓄電池導入家庭向けの専用プランを用意していることが多いため、居住地域の電力会社に相談して最適なプランを選択することが重要です。
Q5: 蓄電池の設置で固定資産税は上がりますか?
A5:
蓄電池の設置による固定資産税への影響は、設置方法や自治体の判断によって異なります。建物と一体化した設置の場合は固定資産税の対象となる可能性がありますが、据置型の蓄電池は一般的に固定資産税の対象外とされることが多いです。ただし、自治体によって判断が異なるため、設置前に居住地域の税務署や自治体に確認することが推奨されます。
この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
光熱費削減コンサルタント
中田 萌ご相談やお見積もりは
完全無料です!


 蓄電池
蓄電池 太陽光発電
太陽光発電 パワーコンディショナ
パワーコンディショナ エコキュート
エコキュート IHクッキングヒーター
IHクッキングヒーター 外壁塗装
外壁塗装 ポータブル電源
ポータブル電源











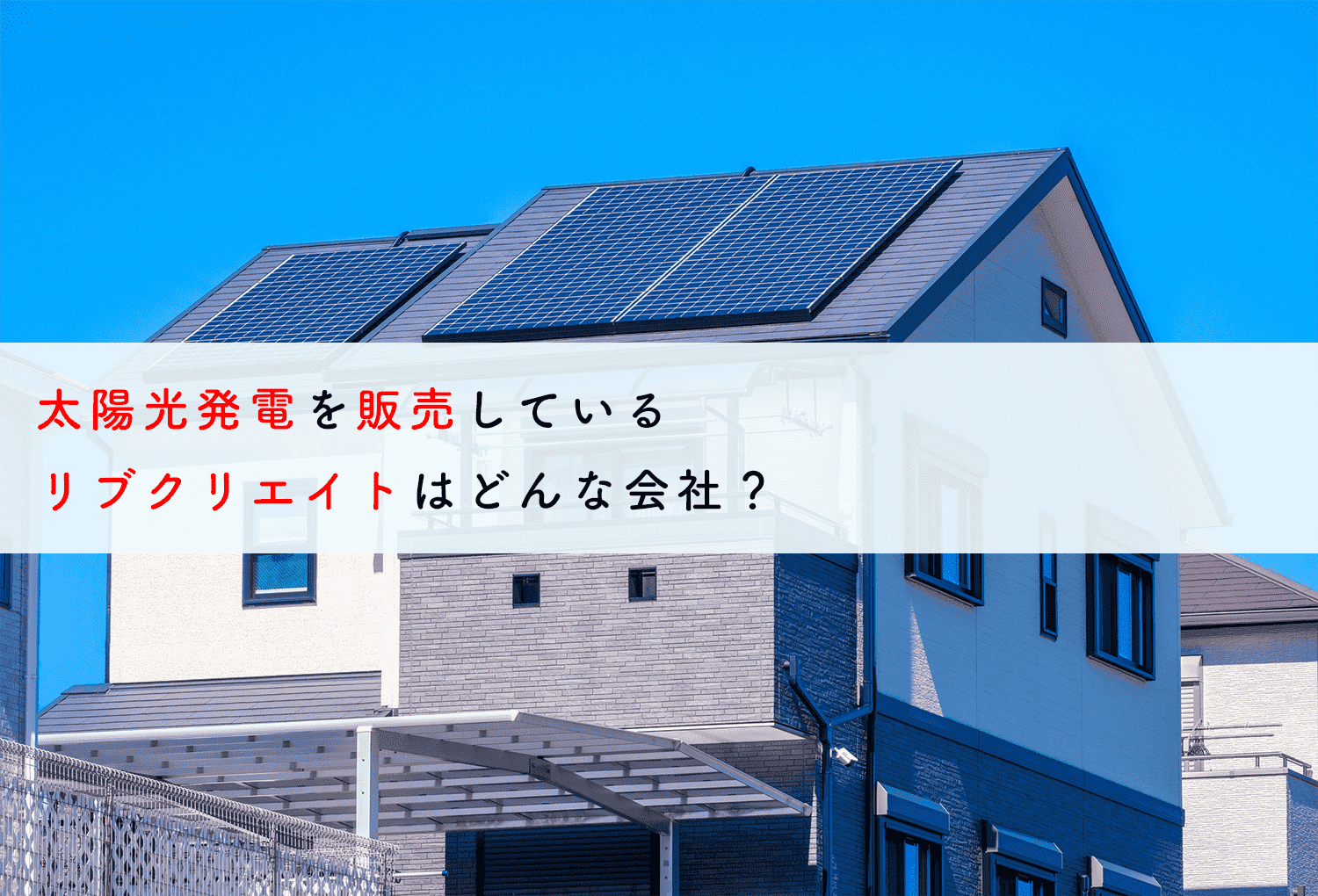








 蓄電池の選び方
蓄電池の選び方































