プロパンガスと電気はどっちが安い?給湯器のコストを徹底比較!
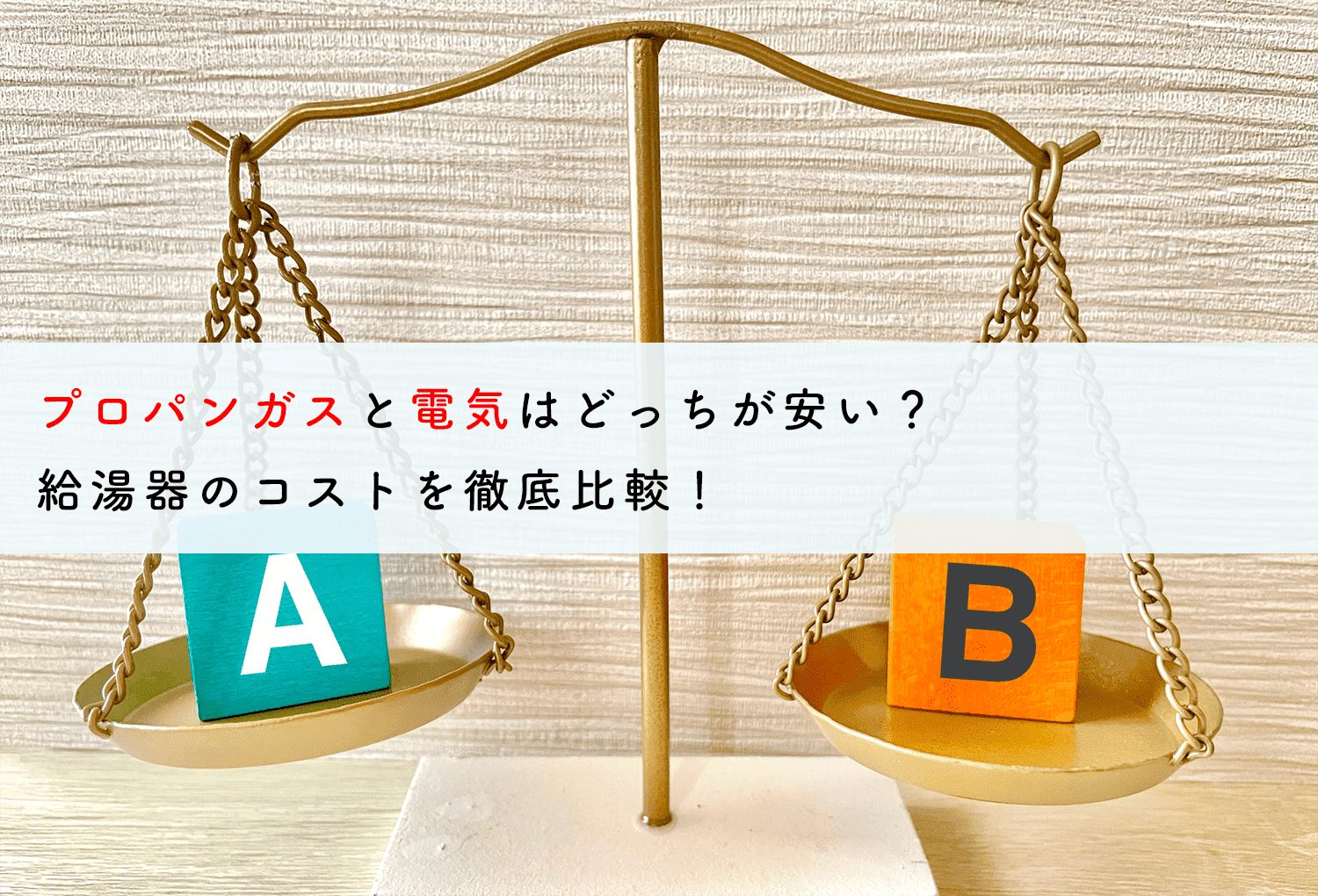
- 料金体系の根本的な違い:プロパンガスと電気では、料金の決まり方が全く異なります。基本料金や単価だけでなく、その構造を理解することが比較の第一歩です。
- 給湯効率がコストを左右する:光熱費の約3分の1を占める給湯コスト。ここをいかに効率化するかが鍵であり、エコキュートのヒートポンプ技術が大きなアドバンテージを持ちます。
- ライフスタイルとの相性:家族構成、お湯の使用量、日中の在宅時間など、暮らし方によって最適なエネルギー源は変わります。トータルコストで判断することが重要です。
目次
第1章: プロパンガスと電気料金の基本比較
まず、プロパンガスと電気の料金がそれぞれどのように決まるのか、その仕組みと平均的な単価を見ていきましょう。なぜ単純な単価比較だけでは「どちらが安いか」を判断できないのか、その理由も解説します。
1-1. 料金体系の違い
プロパンガスと電気の料金は、主に「基本料金」と、使用量に応じて変動する「従量料金(電力量料金)」で構成されていますが、その内訳や性質が異なります。
プロパンガス料金は、ガス会社が自由に価格を設定できる「自由料金制」です。そのため、同じ地域でも会社によって価格が大きく異なることがあります。料金は、毎月固定でかかる「基本料金」と、使用量(m³)に応じた「従量料金」の合計で決まります。
電気料金は、基本料金(または最低料金)と電力量料金に加え、「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」や「燃料費調整額」が加算されます。燃料費調整額は、火力発電に使う燃料の価格変動を電気料金に反映させるもので、毎月変動します。
1-2. 全国平均料金データから見る単価
実際の料金はどのくらいなのでしょうか。公的なデータをもとに、全国の平均的な価格を見てみましょう。
| エネルギー | 平均的な単価 | 出典・補足 |
|---|---|---|
| プロパンガス | 約625円/m³ | 石油情報センター「一般小売価格 LPガス(2024年8月時点, 10m³使用時)」の従量単価を基に算出 |
| 電気 | 約31円/kWh | 大手電力会社の標準的なプランを参考に算出(燃料費調整額・再エネ賦課金を含む) |
この単価だけを見ると、どちらが安いか判断がつきにくいかもしれません。その理由は、それぞれのエネルギーが持つ「熱量」が違うためです。同じお湯を沸かすのに必要なエネルギー量が異なるため、単純な単価比較は意味をなさないのです。
この章のまとめとして、料金比較の際は、表面的な単価だけでなく、料金体系の違いと、実際にエネルギーとして利用する際の「効率」まで考慮する必要があるという点を押さえておきましょう。
第2章: 給湯コストで比較!エコキュート vs プロパンガス給湯器
家庭の光熱費の中で最も大きな割合を占めるのが「給湯」です。ここでは、給湯に絞って「電気(エコキュート)」と「プロパンガス(ガス給湯器)」のコストを比較します。この比較を通じて、なぜオール電化が有利になるケースが多いのか、その核心に迫ります。
2-1. 給湯効率の圧倒的な差を生む「ヒートポンプ技術」
エコキュートがガス給湯器に比べて給湯コストを劇的に下げられる理由は、「ヒートポンプ技術」にあります。これは、エアコンにも使われている技術で、空気中の熱を効率よく集めてお湯を沸かす仕組みです。
具体的には、消費した電気エネルギーの3倍以上の熱エネルギーを生み出すことができます(エネルギー消費効率 COP:3.0以上)。一方、プロパンガス給湯器は、ガスを燃焼させて直接お湯を作るため、投入したエネルギー以上の熱を生み出すことはできません(熱効率は約80〜95%)。
さらに、エコキュートは電力会社の割安な深夜電力プランを利用して、夜間にお湯を沸かして貯めておくのが基本です。この2つの要素が組み合わさることで、日中にプロパンガスでお湯を沸かすよりも圧倒的にコストを抑えることが可能になります。
2-2. 月間・年間の給湯コスト シミュレーション
それでは、具体的な条件下で給湯コストがどれくらい変わるのかをシミュレーションしてみましょう。
| 項目 | プロパンガス給湯器 | エコキュート |
|---|---|---|
| 前提エネルギー単価 | 625円/m³ | 深夜電力 25円/kWh |
| 熱効率/COP | 80% | 3.0 |
| 1日に必要なお湯の熱量 | 約18,000 kcal (4人家族想定) | |
| 1ヶ月あたりの給湯費 | 約8,440円 | 約2,560円 |
| 1年あたりの給湯費 | 約101,280円 | 約30,720円 |
| 年間の差額 | 約70,560円 の削減効果 | |
上記の通り、試算上では年間に約7万円もの差額が生まれる可能性があります。もちろん、これはあくまで一例ですが、エコキュートの導入がプロパンガスエリアの家庭において、非常に大きな光熱費削減効果を持つことがお分かりいただけるでしょう。
まとめると、光熱費の大部分を占める給湯において、エコキュートはヒートポンプ技術と深夜電力の活用により、プロパンガス給湯器に比べてコストを大幅に削減できるポテンシャルがあります。
第3章: オール電化とプロパンガス併用、どちらを選ぶべき?
給湯コストではエコキュートが有利なことが分かりましたが、調理(IHクッキングヒーター vs ガスコンロ)も含めた家全体のエネルギーをどうするか、という視点も重要です。ここでは、オール電化とプロパンガス併用のメリット・デメリットを比較し、ライフスタイルに合った選択肢を探ります。
3-1. オール電化のメリット・デメリット
オール電化は、家庭で使うエネルギーをすべて電気に統一するスタイルです。給湯はエコキュート、調理はIHクッキングヒーターを使用します。
- メリット
- 光熱費の基本料金が電気のみに一本化できる。
- エコキュートと深夜電力プランの組み合わせで、給湯コストを大幅に削減できる。
- 火を使わないため、火災リスクが低減し、キッチンの掃除がしやすい。
- 太陽光発電と非常に相性が良く、発電した電気を有効活用できる。
- デメリット
- 大規模な停電が発生すると、すべての設備が使えなくなるリスクがある。(※蓄電池の導入で対策可能)
- 日中の電気料金単価は割高になる傾向があるため、日中の電気使用量が多い家庭は注意が必要。
- IHクッキングヒーターは、調理器具が限定されたり、ガスコンロの直火に慣れていると使いにくさを感じたりすることがある。
- エコキュートの導入にはまとまった初期費用がかかる。
3-2. プロパンガス併用のメリット・デメリット
ガス併用は、給湯や調理にプロパンガスを使い、それ以外を電気でまかなう従来型のスタイルです。
- メリット
- ガスコンロの強い火力や、直火での調理を好む方には魅力的。
- 停電時でも、乾電池式のガスコンロや一部のガス給湯器は使える場合がある。
- 初期費用はエコキュートに比べてガス給湯器の方が安い傾向にある。
- デメリット
- 電気とガスの両方の基本料金がかかる。
- プロパンガスの単価が高いため、トータルの光熱費が高額になりがち。
- ガス会社によって料金が大きく異なり、価格の透明性が低い場合がある。
特に、太陽光発電システムの導入を検討している、あるいは既に設置しているご家庭では、オール電化との相乗効果が非常に高くなります。日中に発電した電気でエコキュートの沸き増しや家庭の電力をまかない、余った電気を売電することで、光熱費をさらに削減、場合によってはゼロにすることも可能です。
この章の結論として、月々のランニングコストを重視し、太陽光発電なども含めた長期的な経済合理性を考えるならオール電化、調理のこだわりや初期費用を抑えたい場合はガス併用が選択肢になりますが、プロパンガスの料金高騰リスクは常に考慮すべきでしょう。
第4章: 契約前に知るべき注意点と賢い選択のポイント
プロパンガスからオール電化への切り替えや、設備の選定で後悔しないためには、いくつかの重要なポイントを押えておく必要があります。初期費用、メンテナンス、そして活用できる補助金制度について解説します。
4-1. 初期費用と長期的なコスト
エネルギー源を選択する際には、導入時にかかる「初期費用」と、長年使い続ける上での「ランニングコスト」「メンテナンス費用」をトータルで考えることが不可欠です。
| 項目 | エコキュート | プロパンガス給湯器 (エコジョーズ) |
|---|---|---|
| 初期費用(本体+工事費) | 40万円~70万円 | 20万円~40万円 |
| 耐用年数の目安 | 10年~15年 | 10年~13年 |
| メンテナンス | 定期的な点検推奨 | 定期的な点検推奨 |
初期費用だけを見るとガス給湯器の方が安価ですが、第2章でシミュレーションした通り、ランニングコストの差が大きいため、数年〜10年程度で初期費用の差を回収できるケースが多くあります。
4-2. 補助金制度を最大限に活用する
高効率給湯器の導入を促進するため、国や自治体は手厚い補助金制度を用意しています。2024年度であれば、経済産業省が主導する「給湯省エネ2024事業」などがあり、エコキュートの導入に対して大きな補助金が交付される可能性があります。
- 国の補助金: 「給湯省エネ2024事業」では、性能要件を満たすエコキュート1台あたり8万円〜13万円の基本補助額が設定されています。
- 自治体の補助金: お住まいの都道府県や市区町村が、独自に補助金制度を設けている場合があります。国の制度と併用できることも多いので、必ず確認しましょう。
これらの補助金を活用することで、エコキュート導入の初期費用負担を大幅に軽減できます。ただし、補助金には予算があり、申請期間も限られているため、常に最新の情報を確認することが重要です。
補助金制度は少し複雑で、ご自身で調べるのが大変だと感じるかもしれません。迷ったら、無料で【最新の補助金情報と賢い活用法】をチェックして、要点だけ押えておくと判断がしやすくなります。
※費用や制度適用は条件により異なります。
4-3. プロパンガス会社の変更も選択肢に
もし、何らかの理由でオール電化にできない場合でも、プロパンガス料金を見直す方法はあります。プロパンガスは自由料金制なので、現在契約しているガス会社から、より料金の安い会社へ乗り換えることで、月々の負担を軽減できる可能性があります。複数の会社から見積もりを取り、料金体系を比較検討することをおすすめします。
最終的な判断は、初期費用、ランニングコスト、補助金、そしてご自身のライフスタイルを総合的に考慮して行うことが賢明です。目先の費用だけでなく、10年、15年という長いスパンでご家庭の光熱費がどうなるかをシミュレーションしてみましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 結局、プロパンガスと電気はどちらが安いですか?
多くの場合、給湯にエコキュートを利用するオール電化の方が、プロパンガスを使い続けるよりもトータルの光熱費は安くなる傾向にあります。
特に光熱費の約3割を占める給湯コストにおいて、エコキュートは空気の熱を利用するヒートポンプ技術と割安な深夜電力を活用するため、プロパンガス給湯器に比べて大幅に費用を抑えることが可能です。ただし、初期費用はエコキュートの方が高額になるため、ランニングコストでの削減分で何年で回収できるかをシミュレーションすることが重要です。
※ご家庭の人数、お湯の使用量、契約する電力・ガスプランによって差額は変動します。
Q2. オール電化の初期費用はどれくらいかかりますか?
オール電化への切り替えにかかる初期費用は、主にエコキュートとIHクッキングヒーターの本体価格および設置工事費です。一般的な目安としては、合計で60万円~100万円程度を見込むのが一般的です。
- エコキュート: 40万円~70万円(タンク容量や機能による)
- IHクッキングヒーター: 10万円~30万円(機能による)
- その他工事費: 電気工事、配管工事など
ただし、これらの費用は国や自治体の補助金制度を活用することで、負担を大きく軽減できる可能性があります。最新の補助金情報を確認し、賢く利用することをおすすめします。
※金額はあくまで目安です。設置環境や選択する機器のグレードによって変動します。
出典:給湯省エネ2024事業
Q3. 今のプロパンガス料金を安くする方法はありますか?
はい、あります。プロパンガスは自由料金制のため、ガス会社を変更(乗り換え)することで料金が安くなる可能性があります。プロパンガスは公共料金である都市ガスとは異なり、販売店が価格を自由に設定できます。そのため、地域や物件によっては相場より高い料金設定になっているケースも少なくありません。
複数のガス会社から見積もりを取り、料金プランを比較検討してみましょう。その際、基本料金や従量単価だけでなく、契約期間の縛りや解約金の有無なども確認することが重要です。
Q4. 災害(停電)時に強いのはどちらですか?
一概にどちらが優れているとは言えず、それぞれにメリット・デメリットがあります。
オール電化は、大規模な停電が発生すると給湯や調理ができなくなるリスクがあります。しかし、エコキュートは断水していなければタンク内に貯まっているお湯や水を非常用水として利用できます。また、太陽光発電と蓄電池を併設していれば、停電時でもある程度の電力を自給自足することが可能です。
プロパンガス併用の場合、電気が止まっても乾電池で動くタイプのガスコンロは使用できます。ガス給湯器も一部使える場合があります。ただし、ガス管の損傷などがあれば復旧に時間がかかる可能性もあります。
※災害への備えとしては、エネルギー源の選択だけでなく、ポータブル電源やカセットコンロ、備蓄水など多層的な対策が有効です。
まとめ:最適な選択は、ご家庭の状況に合わせたオーダーメイド
本記事では、プロパンガスと電気(オール電化)の料金比較から、それぞれのメリット・デメリット、そして賢い選択のためのポイントまで詳しく解説してきました。
結論として、多くの場合でエコキュートを導入したオール電化が長期的な光熱費削減に繋がりますが、その効果はご家族の人数、お湯の使い方、日中のライフスタイル、さらには太陽光発電の有無など、様々な要因によって変わってきます。
また、国や自治体の補助金制度をいかにうまく活用するかによって、初期費用の負担も大きく変動します。「我が家の場合は具体的にどうなんだろう?」と、より正確な費用対効果や最適な設備を知りたい場合は、専門家のアドバイスを一度聞いてみるのが最も確実な方法です。
※ かんたん60秒入力!しつこい営業は一切ありませんのでご安心ください。
この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
光熱費削減コンサルタント
中田 萌ご相談やお見積もりは
完全無料です!


 蓄電池
蓄電池 太陽光発電
太陽光発電 パワーコンディショナ
パワーコンディショナ エコキュート
エコキュート IHクッキングヒーター
IHクッキングヒーター 外壁塗装
外壁塗装 ポータブル電源
ポータブル電源









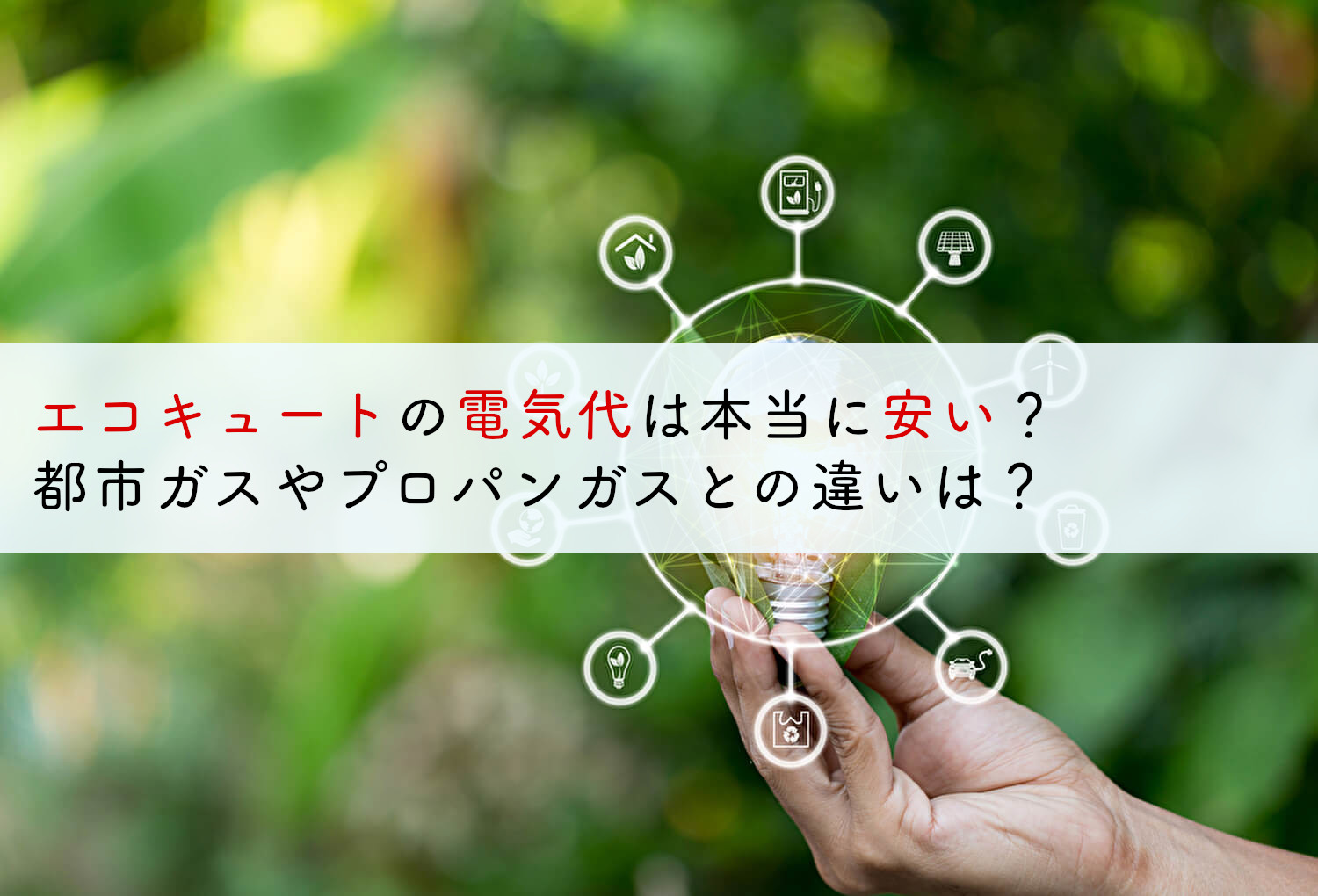







 蓄電池の選び方
蓄電池の選び方































