3人家族の電気代平均は月額いくら?高い原因と節約術を徹底解説

「最近、電気代が上がった気がする」「うちの電気代は3人家族として平均より高いの?」と不安に感じていませんか?電気代は家計の中でも大きな割合を占めるため、平均額を知り、適切に節約したいと考えるのは当然のことです。
結論から言うと、3人家族の電気代平均(2023年)は月額 約13,157円です(※総務省統計局「家計調査」の3人世帯データより)。ただし、この金額はあくまで全国平均であり、季節や地域、ライフスタイルによって大きく変動します。
この記事では、公的データを基にした3人家族の電気代平均、電気代が高くなる原因、そして今日から実践できる具体的な節約術から、太陽光発電のような抜本的な対策まで、専門編集部が詳しく解説します。
- 3人家族の電気代平均(季節別・地域別)
- 電気代が高騰する主な原因と内訳
- 今すぐできる節約術と電力会社の見直し
- 節約の限界を超えるための抜本的対策(太陽光・補助金)
まずはご自宅の電気代が平均と比べてどうなのか、客観的に把握することから始めましょう。
目次
【データで見る】3人家族の電気代平均(2023年・2024年速報)
要旨:
総務省統計局の「家計調査」に基づき、3人家族の電気代平均額を解説します。最新の2023年平均データに加え、季節別・地域別の変動も紹介します。ご自宅の電気代が平均と比較してどの位置にあるのか、客観的な基準として確認しましょう。
電気代の平均額を把握するために、最も信頼性の高い公的データの一つが総務省統計局の「家計調査」です。この調査では、全国の世帯を対象に、家計の収入と支出を毎月調査しています。
2023年(令和5年)の家計調査(二人以上の世帯のうち3人世帯)によると、3人家族の電気代の月平均額は 13,157円でした。これはあくまで年間の平均であり、実際には季節によって大きく変動します。
季節別:3人家族の電気代平均
電気代は、冷暖房(特にエアコン)の使用が増える夏と冬に高くなる傾向が顕著です。
| 調査時期(2023年) | 電気代(3人世帯) | 主な要因 |
|---|---|---|
| 2023年 1月~3月期 | 16,841円 | 暖房(エアコン、ヒーター等)の使用増 |
| 2023年 4月~6月期 | 11,623円 | 冷暖房の使用が少ない時期 |
| 2023年 7月~9月期 | 12,410円 | 冷房(エアコン)の使用増 |
| 2023年 10月~12月期 | 11,754円 | 冷暖房の使用が比較的少ない時期 |
上記のように、最も電気代が高い1〜3月期(冬)と、最も低い4〜6月期(春)では、月に5,000円以上の差が出ています。ご自宅の電気代を確認する際は、「どの季節の請求か」を意識して比較することが重要です。
地域別:電気代の傾向
電気代は、お住まいの地域によっても差が出ます。これは気候(寒冷地か温暖地か)や、契約している電力会社の料金体系が異なるためです。
例えば、北海道や東北などの寒冷地では、冬の暖房(電気暖房や、石油・ガス暖房の送風機など)にかかる光熱費(電気代含む)が他の地域より高くなる傾向があります。一方、九州や沖縄では、夏の冷房使用時間が長くなる傾向があります。
家計調査では10の地方ブロック別にデータが公表されており、例えば2023年平均の「電気代」を見ると、最も高い「北陸」(15,005円)と最も低い「沖縄」(11,399円)では、月3,500円以上の差がありました(※二人以上世帯の平均値)。
簡易まとめ:
3人家族の電気代平均(2023年)は月額約13,157円ですが、これはあくまで目安です。冬場は16,000円を超え、地域によっても差があります。平均額とご自宅の請求額を比較し、「どの季節で」「平均よりどれくらい高いか」を把握することが第一歩です。
なぜ? 3人家族の電気代が高くなる「5つの原因」
要旨:
平均よりも電気代が高い場合、考えられる原因を5つに絞って解説します。消費電力の大きい家電の使い方、家族のライフスタイル、契約プランなど、見直すべきポイントを具体的に整理します。
ご自宅の電気代が平均よりも大幅に高い場合、多くは何らかの原因があります。3人家族で電気代が高騰しやすい主な原因を見ていきましょう。
原因1:消費電力の大きい家電の使用
家庭の消費電力は、特定の家電に集中しがちです。特に以下の家電は消費電力が大きく、電気代を押し上げる主な要因となります。
- エアコン(冷暖房): 家庭の消費電力で最も大きな割合を占めることが多い家電です。特に設定温度と外気温の差が大きいほど電力を消費します。
- 冷蔵庫: 24時間365日稼働しているため、容量が大きい、または古い機種(10年以上前)だと消費電力が大きくなります。
- 給湯器(特に電気温水器・エコキュート): お湯を沸かすエネルギーは非常に大きく、特にエコキュート以外(電気温水器)の場合は電気代が高額になりがちです。
- 照明: 部屋数が多く、点灯時間が長い場合や、白熱電球や古い蛍光灯を使用していると消費電力が増えます。
- その他(乾燥機付き洗濯機、食器洗い乾燥機、電気ヒーター): ヒーター(熱)を使う家電は、総じて消費電力が高い傾向にあります。
原因2:家族の在宅時間が長い
3人家族(例:夫婦+子供1人)の場合、家族のライフスタイルが電気代に直結します。
例えば、夫婦共働きで日中は不在がちな世帯と、夫婦のどちらか(または両方)が在宅ワークで、子供が日中在宅している世帯とでは、後者の方が冷暖房や照明、PCなどの使用時間が長くなり、電気代は高くなります。
原因3:古い家電を使い続けている
「まだ使えるから」と10年以上前のエアコンや冷蔵庫を使っていませんか?家電の省エネ性能は年々飛躍的に向上しています。
資源エネルギー庁の「省エネポータルサイト」によると、例えば2011年製の冷蔵庫(定格内容積401~450L)と2021年製の同クラスの冷蔵庫を比較すると、年間で約40%〜47%も省エネになると試算されています。古い家電は、それだけで電気代を押し上げる大きな要因です。
原因4:電力契約プランがライフスタイルに合っていない
2016年の電力自由化以降、多くの事業者が様々な料金プランを提供しています。もし以前の電力会社の「従量電灯プラン」のまま変更していない場合、損をしている可能性があります。
例えば、日中は不在がちで夜間に電力使用が集中する世帯(エコキュート使用世帯など)は、「夜間割引プラン」が適しています。逆に、在宅ワークなどで日中の電力使用が多い世帯が夜間割引プランに入っていると、割高な日中料金が適用され、かえって電気代が高くなるケースもあります。
原因5:建物の断熱性・気密性が低い
家の断熱性や気密性が低いと、夏は外の熱気が入り込み、冬は室内の暖気が逃げてしまいます。その結果、エアコンが過剰に稼働し続けることになり、設定温度をいくら調整しても電気代は高止まりしてしまいます。
特に窓は熱の出入りが最も大きい場所であり、古いサッシ(アルミサッシや単層ガラス)の場合は対策が必要です。
簡易まとめ:
電気代が高い原因は、消費電力の大きい「家電の使い方」や「古さ」、家族の「在宅時間」、そして「契約プラン」や「家の性能」が複合的に関わっています。まずはどの原因が一番影響しているかを見極めましょう。
今日から実践!3人家族のための電気代節約術
要旨:
電気代高騰の原因が分かったら、次は具体的な節約術です。すぐに取り組める「家電別の対策」と「生活習慣の見直し」、そして「契約の見直し」について、効果の高い順に解説します。
電気代を節約するには、「無駄な電力を減らす」ことが基本です。3人家族で効果が出やすい節約術を紹介します。
1. 家電別の節約術(効果大)
まずは消費電力の大きい家電から対策します。
- エアコン
-
- 設定温度の適正化: 環境省は「冷房時は28℃、暖房時は20℃」を目安として推奨しています。設定温度を1℃変えるだけで、約10%〜13%の消費電力削減効果があるとされています。
- フィルター清掃: 2週間に1度のフィルター清掃で、冷房時約4%、暖房時約6%の消費電力削減効果が期待できます。(出典:資源エネルギー庁「省エネポータルサイト」)
- サーキュレーターの併用: 空気を循環させ、室内の温度ムラをなくすことで、エアコンの効率を上げます。
- 室外機の周囲を整理: 室外機の吹出口を塞ぐと、冷暖房の効率が低下します。
- 冷蔵庫
-
- 設定温度を「中」や「弱」にする: 「強」設定から「中」設定に変えるだけで、年間約61.7kWhの省エネ(約1,910円/年 の節約)が期待できます。(同上出典)
- 詰め込みすぎない: 冷気の循環が悪くなるため、7割程度を目安に。ただし冷凍庫は隙間なく詰める方が効率的です。
- 壁から適切な距離を保つ: 放熱スペースがないと効率が落ちます。
- 給湯器(エコキュート)
-
- 湯量を適切に設定: 家族の人数に合わせ、無駄なお湯を沸かさないようにします。
- 日中の「沸き増し」を避ける: エコキュートは割安な深夜電力でお湯を沸かすのが基本です。日中の高い電力単価での沸き増しは最小限に。
- 照明
-
- LEDへの交換: 白熱電球(54W)からLED電球(9W)に交換すると、年間約82%の省エネ(約2,790円/年 の節約)になります。(同上出典)
- こまめに消灯: 使わない部屋の電気は消すことを家族で徹底します。
2. 生活習慣の見直し
家族全員で取り組むことも重要です。
- 待機電力の削減: 長時間使わない家電(テレビ、PCなど)は、主電源を切るかコンセントから抜く。
- 家族が同じ部屋で過ごす: 3人家族が別々の部屋で冷暖房や照明を使うと、それだけで電気代は2〜3倍になります。できるだけリビングに集まる「ウォームシェア」「クールシェア」を心がけます。
- 家電の買い替え: 10年以上使用しているエアコンや冷蔵庫は、故障していなくても買い替える方が、長期的に見て電気代の節約につながる可能性が高いです。
3. 電力会社・契約プランの見直し
家電や生活習慣の見直しと並行して、必ず確認したいのが「電力契約」です。
2016年の電力自由化により、ライフスタイルに合ったプランを選べるようになりました。「新電力」と呼ばれる様々な事業者が、独自の料金プランやセット割引(ガスや通信とのセット)を提供しています。
「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」や契約先のマイページを見て、以下の点を確認しましょう。
- 契約アンペア数(A)は適切か?(※アンペア契約の場合)
- 現在契約中のプラン名は何か?
- 電力使用量が「日中」と「夜間」どちらに多いか?
現在の使用状況を把握した上で、複数の電力会社のシミュレーションサイトで比較検討することをおすすめします。
簡易まとめ:
節約は「家電」「生活習慣」「契約」の三本柱で進めます。特に効果が大きいエアコン・冷蔵庫・給湯器の対策と、契約プランの見直しは非常に重要です。家族でルールを決めて取り組むことが成功の鍵です。
日々の節約も大切ですが、制度を活用した「抜本的な対策」も知っておくと安心です。無料で「今使える補助金と電気代対策」の全体像をまとめた資料で、賢い防衛策を確認してみませんか?
※国や自治体の最新の補助金制度に関する情報です。
節約術の限界?抜本的な電気代高騰対策
要旨:
日々の節約を徹底しても、電気代高騰の影響を完全に防ぐのは困難です。電気を「買う」から「創る」へ発想を転換する太陽光発電や、国の補助金制度を活用した省エネリフォームについて解説します。
エアコンのフィルター掃除やLEDへの交換など、日々の節約術(=消費を減らす努力)には限界があります。電気料金そのものが高騰し続けた場合、節約努力だけでは家計への負担を吸収しきれなくなるかもしれません。
そこで、長期的な視点に立った「抜本的な対策」として、以下の方法が注目されています。
1. 太陽光発電システムの導入(自家消費)
最も根本的な対策の一つが、自宅の屋根に太陽光発電システムを設置し、電気を自分で創り出すことです(自家消費)。
日中の電力使用量が多い3人家族(特に在宅ワークや日中にお子様が在宅する世帯)の場合、発電した電気をそのまま家庭で使うことで、電力会社から買う電気の量を大幅に減らせます。
メリット:
- 日中の電気代が大幅に削減できる(買う量が減るため)。
- 使いきれなかった電気は売電できる(FIT制度終了後も相対契約などで売電可能)。
- 燃料価格の変動や再エネ賦課金高騰の影響を受けにくくなる。
- 災害による停電時も、自立運転機能で電気(日中)が使える。
2. 蓄電池の併用(夜間・停電対策)
太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、対策はさらに強固になります。
日中に太陽光で発電した電気のうち、使いきれなかった分を蓄電池に貯めておきます。そして、発電できない夜間や、電気代が高い夕方の時間帯に、蓄電池から電気を使うことができます。
これにより、電力会社から電気を買う量を最小限に抑えられ、停電時も蓄電池の電気で夜間を過ごせる安心感が得られます。
3. エコキュート(高効率給湯器)の導入
すでに対策済みの方も多いかもしれませんが、ガス給湯器や古い電気温水器を使用している場合、高効率な「エコキュート」への交換も非常に効果的です。
エコキュートは、空気の熱を利用してお湯を沸かすヒートポンプ技術と、電気代が安い深夜電力の活用を組み合わせることで、給湯にかかる光熱費を大幅に削減できます。
4. 補助金制度の活用
太陽光発電や蓄電池、エコキュートの導入には初期費用がかかります。しかし現在、国や多くの自治体が、脱炭素化推進のためにこれらの省エネ設備に対して手厚い補助金・助成金制度を用意しています。
例えば、国(経済産業省・環境省など)が実施する大規模な補助金事業(「給湯省エネ事業」や「子育てエコホーム支援事業」など)では、エコキュートや高断熱窓、太陽光発電(対象事業による)などが補助対象となる場合があります。
これらの補助金を活用すれば、初期費用を大幅に抑えて導入することが可能です。
簡易まとめ:
日々の節約術と並行し、太陽光発電や蓄電池、エコキュートといった「創エネ」「省エネ」設備を導入することは、将来の電気代高騰に対する最も有効な防衛策の一つです。導入時は補助金制度を最大限に活用しましょう。
3人家族の電気代 よくある質問(FAQ)
Q1. 3人家族で電気代が月2万円は高い?
2023年の3人世帯の電気代平均(月額13,157円)と比較すると、「高い」可能性があります。ただし、いくつかの条件を確認する必要があります。
もし、電気代が2万円を超えたのが冬場(1月〜3月)であれば、平均(16,841円)に近いため、異常な高さではないかもしれません。しかし、春や秋(4月〜6月、10月〜12月)に2万円を超えている場合は、平均(約11,600円台)を大幅に上回っており、何らかの原因(家電の不調、契約プランのミスマッチ等)が考えられます。
- 確認点1: 請求月はいつか?(冬場か、それ以外か)
- 確認点2: 家族構成は?(例:在宅ワーク、乳幼児がいて常時空調が必要など)
- 確認点3: オール電化住宅ではないか?(Q2参照)
※金額は条件により変動します。あくまで家計調査データとの比較です。
Q2. オール電化の3人家族の電気代平均は?
オール電化住宅の場合、家計調査の「電気代」平均(ガス代と分離されている)は直接の参考になりません。オール電化住宅では、調理(IH)と給湯(エコキュート等)も全て電気でまかなうためです。
オール電化の電気代は、ガス代と電気代を合計した「光熱費(電気・ガス・灯油)」と比較するのが適切です。家計調査(2023年・3人世帯)における「光熱・水道」の平均は月額 24,196円(うち電気代 13,157円、ガス代 4,374円、他の光熱 1,213円、上下水道料 5,452円)です。
オール電化住宅(特にエコキュート導入)の場合、深夜電力の活用で給湯費が抑えられるため、電気とガスを併用している世帯の「電気代+ガス代」(平均 17,531円)よりも、トータルの光熱費が安くなるケースも多くあります。オール電化で電気代が月2万円〜2万5千円程度(水道代除く)であれば、平均的な光熱費の範囲内と言える可能性があります。
※オール電化専用の公的統計は少ないため、あくまで家計調査の合算値との比較目安です。
Q3. 賃貸でもできる電気代節約術は?
賃貸住宅の場合、太陽光発電の設置や窓の断熱リフォームなどは困難です。しかし、できる対策は多くあります。
- 電力会社の切り替え: 賃貸でも電力会社は自由に選べます。ライフスタイルに合ったプランに変更するだけで数千円変わることもあります。
- 家電の使い方見直し: 本文で紹介したエアコンのフィルター掃除、冷蔵庫の設定温度変更、LEDへの交換(退去時原状回復)などはすぐに実践できます。
- 窓の簡易断熱: ホームセンターなどで購入できる「断熱シート」を窓に貼ったり、「断熱カーテン」に交換したりするだけでも、冷暖房効率は改善します。
- 契約アンペア数の見直し: 3人家族で30A契約の場合、家電の同時使用でブレーカーが落ちやすいかもしれません。逆に50Aや60Aで余裕がありすぎる場合、40Aなどに下げることで基本料金を節約できます(※電力会社への申請が必要。下げすぎに注意)。
※アンペア数の変更は管理会社や大家さんへの確認が必要な場合があります。
Q4. 節約のためにアンペア数を下げるべき?
契約アンペア数(A)を下げることは、月々の「基本料金」を下げる効果があり、節約につながります。ただし、これは「アンペア制」を採用している電力会社(東京電力、東北電力など)に限られます。
注意点は、下げすぎると頻繁にブレーカーが落ちて不便になることです。3人家族で、エアコン、電子レンジ、ドライヤー、炊飯器などを同時に使用する時間帯がある場合、30Aでは不足し、40Aや50Aが必要なケースが多いです。
まずはご自宅の契約アンペア数(ブレーカーの色で確認可能)と、一度に最も電気を使う時間帯の状況を把握してから、下げるかどうかを判断してください。
出典:東京電力エナジーパートナー「従量電灯B・C」(※契約例)
この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
光熱費削減コンサルタント
中田 萌ご相談やお見積もりは
完全無料です!


 蓄電池
蓄電池 太陽光発電
太陽光発電 パワーコンディショナ
パワーコンディショナ エコキュート
エコキュート IHクッキングヒーター
IHクッキングヒーター 外壁塗装
外壁塗装 ポータブル電源
ポータブル電源











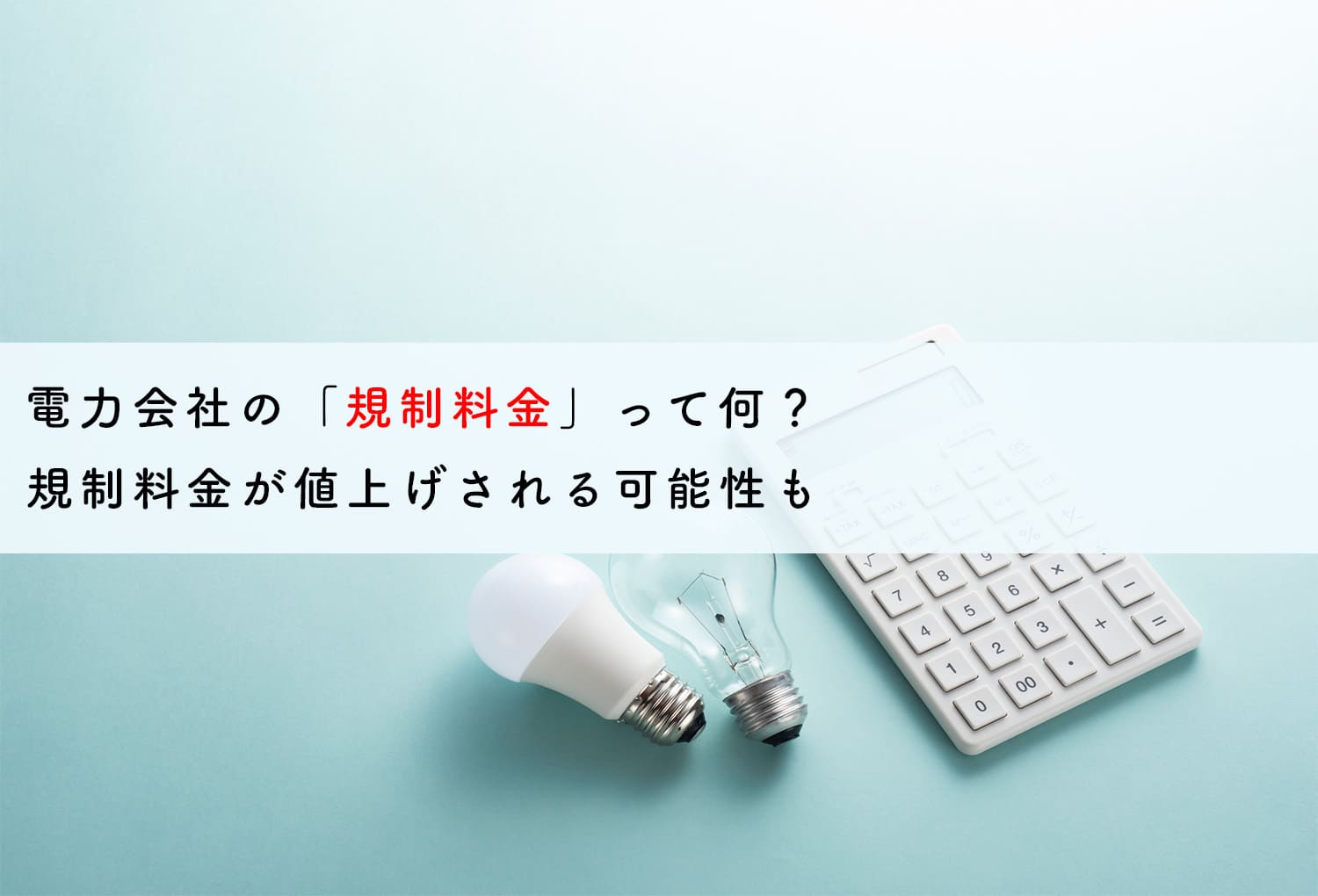








 蓄電池の選び方
蓄電池の選び方































