電気料金、規制料金と自由料金はどっちがお得? 燃料費高騰リスクと選び方を専門家が解説

「電気料金プラン、規制料金と自由料金って結局どっちがいいの?」「新電力に切り替えたけど、最近の値上がりで不安…」
2016年の電力自由化以降、多くの新電力会社(小売電気事業者)が参入し、私たちは電気の契約先を自由に選べるようになりました。しかし、最近の燃料価格高騰により、状況は一変。自由料金プランの値上げや「燃料費調整額」の上限撤廃が相次ぎ、「規制料金のままが良かったのでは?」と迷う方も増えています。
この記事では、住まいとエネルギーの専門家として、規制料金と自由料金の根本的な違いから、それぞれのメリット・デメリット、そして現在の情勢を踏まえた「どっちを選ぶべきか」の判断基準を徹底的に解説します。
結論から言うと、「どちらが絶対にお得」とは言えず、ご家庭の電気使用量やライフスタイル、そしてリスク許容度によって最適解が異なります。
この記事で押さえるべきポイントは以下の3つです。
- 規制料金:国の認可が必要な昔ながらのプラン。急激な値上げリスクは低いが、割安感も限定的(経過措置料金)。
- 自由料金:電力会社が自由に価格設定できるプラン。多様なメニューがあるが、燃料費高騰の影響を直接受けやすい。
- 判断基準:電気使用量、オール電化の有無、燃料費調整額の上限の有無、そしてセット割などの付加価値が鍵。
まずは、二つの料金体系の基本的な違いから詳しく見ていきましょう。
目次
1章:電気料金の基本「規制料金」と「自由料金」の違いとは?
電気料金プランを比較する上で、「規制料金」と「自由料金」の違いを理解することは不可欠です。2016年4月の電力小売全面自由化を境に、電気料金の仕組みは大きく変わりました。この章では、それぞれの定義と特徴、そして両者の根本的な違いを明確にします。
要旨としては、「規制料金」は国の管理下にある旧来の料金体系であり、「自由料金」は電力会社が独自に設定できる新しい料金体系です。この違いが、価格設定の柔軟性や消費者が直面するリスクに直結しています。
1-1. 規制料金(経過措置料金)とは?
「規制料金」とは、2016年の電力自由化以前から存在していた、従来の電気料金プランを指します。具体的には、東京電力エナジーパートナーの「従量電灯B/C」や関西電力の「従量電灯A/B」など、地域の大手電力会社(旧一般電気事業者)が提供する基本的なプランです。
最大の特徴は、料金を設定する際に国の認可(経済産業大臣の認可)が必要である点です。電力会社が自由に料金を決められず、電気の安定供給という公的な側面から、料金の上限や原価計算のルールが厳しく定められています。
現在、これらのプランは「経過措置料金」として存続しています。これは、自由化後も消費者が不利にならないよう、また市場が安定するまで、当面の間は旧来の料金体系も選択肢として残すという国の配慮によるものです。
1-2. 自由料金とは?
「自由料金」とは、2016年の電力自由化以降に登場した新しい料金プランです。大手電力会社が提供する新しいプラン(例:東京電力の「プレミアムS」)や、いわゆる「新電力」と呼ばれる新規参入の小売電気事業者が提供するプランのすべてがこれに該当します。
最大の特徴は、国の認可が不要で、電力会社が自由に料金やサービス内容を設計できる点です。これにより、以下のような多様なプランが生まれました。
- 基本料金が0円のプラン
- 特定の時間帯(夜間など)の電気代が安くなるプラン
- ガスや携帯電話とのセット契約で割引になるプラン
- 再生可能エネルギー由来の電力を供給するプラン
消費者は自身のライフスタイルや価値観に合わせて、最適なプランを自由に選べるようになりました。
1-3. 決定的な違いは「価格設定のルール」と「燃料費調整額」
規制料金と自由料金の最も大きな違いは、前述の「価格設定のルール(国の認可の有無)」ですが、近年、より重要になっているのが「燃料費調整額」の扱いの違いです。
燃料費調整額とは、火力発電に用いる燃料(原油、LNG、石炭)の価格変動を電気料金に反映させるための調整金です。これは、規制料金・自由料金を問わず、ほとんどの電気料金プランに含まれています。
重要なのは、規制料金(経過措置料金)には、この燃料費調整額の「上限」が設定されている点です。燃料価格がどれだけ高騰しても、一定の上限を超えた分は電気料金に転嫁されません(電力会社が負担します)。
一方、多くの自由料金プランでは、この「上限」が撤廃されています。そのため、燃料価格が高騰すると、その分が青天井で電気料金に上乗せされるリスクがあります。2022年以降のエネルギー価格高騰の局面では、この上限の有無が電気代に大きな差をもたらす結果となりました。
| 比較項目 | 規制料金(経過措置料金) | 自由料金 |
|---|---|---|
| 提供事業者 | 大手電力会社(旧一般電気事業者) | 大手電力会社、新電力(小売電気事業者) |
| 料金設定 | 国の認可が必要(上限あり) | 事業者が自由に設定可能 |
| プランの多様性 | 限定的(従量電灯など) | 非常に多様(時間帯別、セット割、再エネなど) |
| 燃料費調整額 | 上限あり | 上限なし(または撤廃)が多い |
| 主なメリット | 急激な価格高騰リスクが低い | ライフスタイルに合えば割安になる、付加価値(ポイント等) |
| 主なデメリット | 料金が割高になる場合がある、プランの選択肢がない | 燃料価格高騰の影響を直接受ける、倒産・撤退リスク |
このように、規制料金と自由料金は、価格の決まり方とリスクの所在が根本的に異なります。仕組みを理解したところで、次は具体的なメリット・デメリットを比較し、「どっちを選ぶべきか」を考えていきましょう。
規制料金と自由料金、どちらが自分の家庭に適しているか判断するには、まず今の電気料金がどのように決まっているかを知ることが第一歩です。
2章:【メリット・デメリット徹底比較】あなたの家はどっち?
規制料金と自由料金の基本的な違いがわかったところで、この章では、それぞれのメリットとデメリットを深掘りし、ご家庭の状況によって「どっち」が適しているかの判断基準を解説します。
要旨としては、規制料金は「安心・安定」を重視する人向け、自由料金は「電気の使い方に工夫ができ、リスクを許容できる」人向けと言えます。しかし、近年の情勢変化により、この前提が崩れつつある点にも注意が必要です。
2-1. 規制料金(経過措置料金)のメリット・デメリット
メリット
- 燃料費調整額に上限がある安心感最大のメリットは、やはり燃料費調整額に上限が設定されている点です。世界的なエネルギー価格高騰時でも、電気料金の急激な上昇が抑えられます。電気使用量が多いご家庭や、予期せぬ出費を避けたい方にとっては大きな安心材料です。
- 事業者の倒産・撤退リスクが極めて低い提供しているのが地域の大手電力会社であり、国の認可事業でもあるため、倒産や電力市場からの撤退といったリスクは実質的にありません。
デメリット
- 料金単価が割高な場合がある自由料金プランのように、電気を多く使うほど単価が安くなる(あるいは時間帯によって安くなる)といった設計にはなっていません。ライフスタイルによっては、自由料金プランを選んだ方が総額で安くなるケースも多くあります。
- プランの選択肢がない基本的に「従量電灯」プランしかなく、オール電化専用プランや、ポイントが貯まるといった付加価値もありません。
- ※注意点:規制料金の値上げ規制料金も「絶対安全」ではありません。燃料費調整額の上限を超えた赤字が電力会社の経営を圧迫した結果、2023年には大手電力会社各社が規制料金そのものの値上げ(原価の見直し)を国に申請し、認可されました。上限があるとはいえ、ベースとなる料金自体が上昇する可能性は常にあります。
2-2. 自由料金のメリット・デメリット
メリット
- 多様な料金プランによる節約の可能性「夜間の電気代が安い」「電気を多く使うほど単価が下がる」「基本料金0円」など、ご家庭の電気の使い方に合わせたプランを選べば、規制料金より大幅に電気代を節約できる可能性があります。
- セット割やポイントサービスガス、水道、携帯電話、インターネット回線など、他のサービスとセットで契約することで割引が適用されたり、ポイント還元が受けられたりする場合があります。
- 再生可能エネルギーの選択「CO2排出実質ゼロ」や「再生可能エネルギー100%」を謳うプランもあり、環境意識の高い消費者にとっての選択肢となります。
デメリット
- 燃料費調整額の上限がない(撤廃された)これが最大のデメリットであり、リスクです。燃料価格が高騰すれば、電気代は際限なく上昇する可能性があります。特に電気使用量が多いご家庭(オール電化、大家族など)は、高騰時の請求額が非常に大きくなる危険性があります。
- 事業者の倒産・撤退リスク新電力は競争が激しく、また燃料価格高騰の直撃を受けたことで、倒産したり、電力小売事業から撤退したりする企業が相次ぎました。契約先が倒産した場合、すぐに電気が止まることはありませんが(救済措置があります)、新たな契約先を短期間で探す手間が発生します。
- 複雑な契約条件と違約金プランが多様な反面、契約内容が複雑で理解しにくい場合があります。また、契約期間の途中で解約すると「違約金」や「解約事務手数料」が発生するプランも多いため、切り替えには慎重さが必要です。
2-3.【簡易診断】規制料金 vs 自由料金 どっちが向いてる?
どちらを選ぶべきか、ご家庭の状況別に簡易的な判断基準を示します。
【規制料金】が向いている可能性が高い人
- 電気使用量が比較的少ない(例:一人暮らし、日中は不在がち)
- 電気料金の急激な変動リスクを絶対に避けたい
- プランを比較検討するのが面倒、または時間がない
- 燃料費調整額の上限撤廃に強い不安を感じる
【自由料金】を検討する価値がある人
- 電気使用量が非常に多い(例:オール電化、大家族、在宅ワーク)
- ※ただし、燃料費調整額の上限がないリスクを十分理解し、高騰時にも対応できる家計体力がある場合に限ります。
- 特定の時間帯に電気使用が集中している(例:夜間、早朝)
- ガスや携帯電話など、セット割の対象サービスを同一事業者でまとめられる
- 契約内容(燃料費調整額の扱い、違約金など)を自分でしっかり確認・理解できる
規制料金と自由料金、それぞれのメリット・デメリットを理解すると、「自分の家計ではどうなるのか」具体的なイメージが湧きにくく、不安になるかもしれません。
文字や表だけではイメージが掴みにくい…という方は、無料で読める「電気代節約のマンガ」で、複雑な制度や対策を直感的に理解するのも一つの手です。 ※制度や家計状況はご家庭により異なります。
3章:注意点とリスク:「燃料費調整額」と「新電力の選び方」
規制料金と自由料金、どっちを選ぶかという議論において、今や「燃料費調整額」の理解は避けて通れません。この章では、電気代高騰の最大の要因となったこの仕組みと、自由料金プラン(新電力)を選ぶ際の具体的な注意点を解説します。
要旨は、「燃料費調整額の上限撤廃」が自由料金の最大のリスクであること、そして新電力の倒産リスクは現実のものとして認識する必要があるということです。
3-1. 燃料費調整額の上限撤廃がもたらした衝撃
前章までで触れた通り、規制料金には「上限」があり、多くの自由料金には「上限がない」のが燃料費調整額です。
2021年秋頃から始まった世界的な燃料価格高騰により、この燃料費調整額は高騰し続けました。規制料金プランでは、上限に達した時点でそれ以上の請求はストップしました(例:東京電力の従量電灯Bの上限は5.13円/kWh)。
しかし、上限のない自由料金プランでは、燃料費調整額が1kWhあたり数十円に達するケースも発生しました。例えば、電気を月400kWh使う家庭の場合、
- 規制料金(上限あり):5.13円 × 400kWh = 2,052円 の調整額
- 自由料金(上限なし・仮に20円):20円 × 400kWh = 8,000円 の調整額
となり、調整額だけで約6,000円もの差がつく事態となったのです。これは、自由料金プランの「基本料金0円」や「電力量料金のわずかな割引」といったメリットを、たやすく吹き飛ばすインパクトでした。
現在は燃料価格も落ち着きを取り戻しつつありますが、国際情勢次第で再び高騰するリスクは常に存在します。自由料金を選ぶ際は、このリスクを許容できるかが最大の焦点となります。
3-2. 新電力の選び方と「倒産・撤退」リスクへの備え
「自由料金」=「新電力」と契約することを選択した場合、どの会社を選ぶかが重要です。しかし、価格競争と燃料高騰のダブルパンチにより、新電力の経営環境は非常に厳しくなっています。
実際に、多くの新電力が倒産、事業撤退、あるいは新規契約の受付を停止しました。もし契約中の新電力が倒産・撤退した場合、どうなるのでしょうか?
結論から言うと、すぐに電気が止まることはありません。
電力の安定供給のため、「セーフティネット」が用意されています。契約先を失った需要家は、一時的に地域の大手電力会社(東京電力や関西電力など)から「最終保障供給」という形で電気が供給されます。ただし、この「最終保障供給」の料金は、標準的なプラン(規制料金など)よりも割高に設定されていることが一般的です。
そのため、倒産・撤退の通知が来たら、速やかに次の契約先を見つけて切り替え手続きを行う必要があります。
新電力(自由料金プラン)を選ぶ際のチェックポイント
- 燃料費調整額の扱い:上限はあるか?ない場合、独自の算定方法(例:市場連動型)ではないか?
- 契約期間と違約金:最低契約期間は?途中で規制料金に戻したくなった場合、違約金はいくらか?
- 会社の信頼性:電力事業の実績は十分か?親会社はどこか?(経営体力)
- 電源構成:自前の発電所を持っているか、JEPX(卸電力取引所)からの調達に依存していないか?(市場価格高騰リスク)
これらのリスクを一般の消費者がすべて見抜くのは困難です。安さだけを追求すると、かえって大きなリスクを抱え込む可能性があるのが、現在の自由料金市場の現実です。
リスクを理解した上で、それでも「電気代を1円でも安くしたい」と考えるのは当然のことです。しかし、自力での情報収集と判断には限界があります。
複雑な料金体系や市場リスクを踏まえた上で、ご家庭に最適な節約方法を知りたい場合、専門家が監修する「電気代の最適化」に関する情報を参照し、客観的な判断材料を得ることも重要です。 ※効果は電気使用量や地域によって異なります。
4章:失敗しないための手続きと確認(切替・見直し)
規制料金と自由料金のどちらかを選ぶ、あるいは現在契約中のプランから別のプランへ切り替える際には、いくつかの手続きと確認事項があります。この章では、スムーズな移行のために知っておくべき点を解説します。
要旨は、切替自体は簡単だが「スマートメーターの有無」と「契約中のプランの違約金」は必ず確認すべき、という点です。また、「規制料金に戻る」際の注意点も説明します。
4-1. 電力会社切り替えの基本的な流れ
電力会社の切り替え(例:A電力の自由料金からB電力の自由料金へ)や、同一会社内でのプラン変更(例:C電力の規制料金からC電力の自由料金へ)は、基本的に以下のステップで完了します。
- 新しい契約先の選定・申し込み新しい電力会社やプランを決め、Webサイトや電話で申し込みます。この際、「お客様番号」や「供給地点特定番号」が必要になるため、現在の電気の検針票(または会員サイト)を手元に用意します。
- スマートメーターの設置(未設置の場合)まだ旧来のアナログメーターを使用している場合、スマートメーターへの交換工事が必要になります。原則として工事費は無料(電力会社の負担)で、立ち会いも不要な場合が多いです。
- 切り替え完了申し込みから数日~数週間で、新しい電力会社・プランでの供給が開始されます。開始日は事前にハガキやメールで通知されます。
重要な点として、現在契約中の電力会社への「解約連絡」は、原則として不要です。新しい電力会社が申し込み手続きの中で、古い電力会社との解約処理を代行してくれます。
4-2. 切り替え・見直し前の重要チェックリスト
手続きは簡単ですが、申し込む前に以下の点は必ず確認してください。これを見落とすと、「切り替えたのに損をした」という事態になりかねません。
- 現在の契約内容の確認今、自分が「規制料金」なのか「自由料金」なのか。プラン名は何か。燃料費調整額の上限はあるか。
- 違約金・解約金の有無(自由料金プランの場合)現在のプランを今解約した場合、違約金や解約事務手数料は発生しないか。発生する場合、いくらか。
- 新しいプランの燃料費調整額切り替え先のプランの燃料費調整額に「上限」はあるか。ない場合、どのような算定方法か。
- 新しいプランの契約条件新しいプランの最低契約期間や、そこでの違約金設定はどうなっているか。
4-3. 自由料金から「規制料金」に戻ることはできる?
「燃料費高騰が怖いので、新電力(自由料金)から、大手電力会社の規制料金(従量電灯)に戻りたい」
これは、2022年以降に非常に多く見られたニーズです。結論から言うと、「戻ることは可能」ですが、注意が必要です。
2023年6月以降、大手電力会社各社は、規制料金(経過措置料金)への新規契約(自由料金からの「出戻り」を含む)の受付を再開しています。
ただし、手続きは「新規契約」と同じ扱いになるため、Webや電話での申し込みが必要です。また、申し込みが殺到した場合、切り替え完了までに時間がかかるケースもありました。
規制料金に戻る最大のメリットは「燃料費調整額の上限」による安心感ですが、前述の通り、規制料金自体が値上げされたため、必ずしも「規制料金に戻れば電気代が安くなる」とは限らない点も理解しておく必要があります。
ご自身のライフスタイルとリスク許容度を天秤にかけ、最適なプランを選択することが重要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 規制料金と自由料金、結局どっちがお得?
一概に「こっちがお得」とは言えません。判断はご家庭の状況と、何を重視するかによって異なります。
2022年~2023年初頭の燃料価格が異常に高騰した時期は、燃料費調整額に上限がある「規制料金」のほうが結果的に安くなるケースが多く見られました。
しかし、燃料価格が落ち着いている時期や、ご家庭の電気使用スタイル(例:オール電化で夜間使用が多い)によっては、「自由料金」の特定のプランが規制料金よりも大幅に安くなる可能性があります。
※「安さ」だけを追求するなら自由料金に可能性がありますが、「価格変動リスク」が伴います。「安心」を追求するなら規制料金が選択肢になりますが、節約効果は限定的です。
Q2. 新電力(自由料金)が倒産したら電気は止まる?
すぐに電気が止まることはありません。
契約していた小売電気事業者が倒産したり、事業から撤退したりした場合でも、電力の供給は継続されます。これは「セーフティネット」の仕組みによるものです。
利用者は、一時的にその地域の大手電力会社(東京電力、関西電力など)が提供する「最終保障供給」という契約に切り替わります。ただし、この最終保障供給の料金は、標準的なプラン(規制料金など)よりも割高に設定されていることが一般的です。
そのため、倒産・撤退の通知を受けたら、ご自身で速やかに新しい電力会社を探し、契約手続きを行う必要があります。
Q3. 燃料費調整額の上限撤廃って何?
「燃料費調整額」とは、火力発電の燃料価格の変動を電気料金に反映させる仕組みです。
「規制料金(経過措置料金)」では、この調整額に「上限」が設定されており、燃料価格がいくら上がっても一定額以上は請求されません。
「上限撤廃」とは、主に「自由料金」プランにおいて、この上限をなくすことを指します。上限が撤廃されると、燃料価格が上昇した分だけ、青天井で電気料金に上乗せされることになります。2022年以降、多くの新電力や大手電力会社の自由料金プランで、この上限撤廃が相次ぎました。
※これが、自由料金プランが規制料金プランより大幅に高くなる「逆転現象」の主な原因となりました。
Q4. オール電化住宅でも自由料金を選べますか?
はい、選べます。 多くの電力会社が、オール電化住宅向けの自由料金プラン(夜間の電気代が安くなるプランなど)を提供しています。
ただし、注意点があります。オール電化住宅は、エコキュート(電気給湯器)やIHクッキングヒーターなどで電気使用量が非常に多くなるため、燃料費調整額の影響を大きく受けます。
もし「燃料費調整額の上限がない」自由料金プランを契約し、燃料価格が高騰した場合、請求額が想定外に高額になるリスクがあります。規制料金のオール電化プラン(※新規受付が終了している場合が多い)と比較し、リスクを理解した上で選択することが重要です。
Q5. 一度、自由料金に変えたら規制料金には戻せませんか?
戻すことは可能です。
以前は、自由料金プラン(新電力を含む)から規制料金(経過措置料金)への「出戻り」契約を停止している大手電力会社もありましたが、2023年6月頃から各社で受付が再開されています。
手続きは、現在契約中の電力会社ではなく、戻りたい大手電力会社(例:東京電力エナジーパートナー、関西電力など)に対して「新規契約」として申し込む形になります。ただし、現在契約中の自由料金プランに違約金や解約金が設定されていないか、事前に必ず確認してください。
まとめ:規制料金と自由料金、どっちを選ぶかは「リスク許容度」が鍵
本記事では、「規制料金」と「自由料金」について、どっちを選ぶべきか、その違いからメリット・デメリット、そして近年の燃料費調整額をめぐるリスクまで詳しく解説しました。
2016年の電力自由化当初は、多様な「自由料金」プランへ切り替えることで電気代が安くなる、というメリットが強調されていました。しかし、その後の世界的なエネルギー価格高騰は、「自由料金」が内包する価格変動リスクを浮き彫りにしました。
最終的な判断基準は、ご家庭の「リスク許容度」に尽きます。
- 安定と安心を最優先し、燃料価格高騰の際にも電気代の急騰を避けたいのであれば、燃料費調整額に上限がある「規制料金(経過措置料金)」が適しています。
- 一方で、ご自身のライフスタイル(オール電化、在宅ワークなど)に合わせてプランを最適化し、リスク(燃料費高騰、違約金)を理解した上で節約効果を追求したいのであれば、「自由料金」にメリットがあります。
どちらを選ぶにせよ、契約内容、特に「燃料費調整額の扱い」と「違約金の有無」をご自身の目でしっかりと確認することが、後悔しないための最大の防御策となります。
この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
光熱費削減コンサルタント
中田 萌ご相談やお見積もりは
完全無料です!


 蓄電池
蓄電池 太陽光発電
太陽光発電 パワーコンディショナ
パワーコンディショナ エコキュート
エコキュート IHクッキングヒーター
IHクッキングヒーター 外壁塗装
外壁塗装 ポータブル電源
ポータブル電源











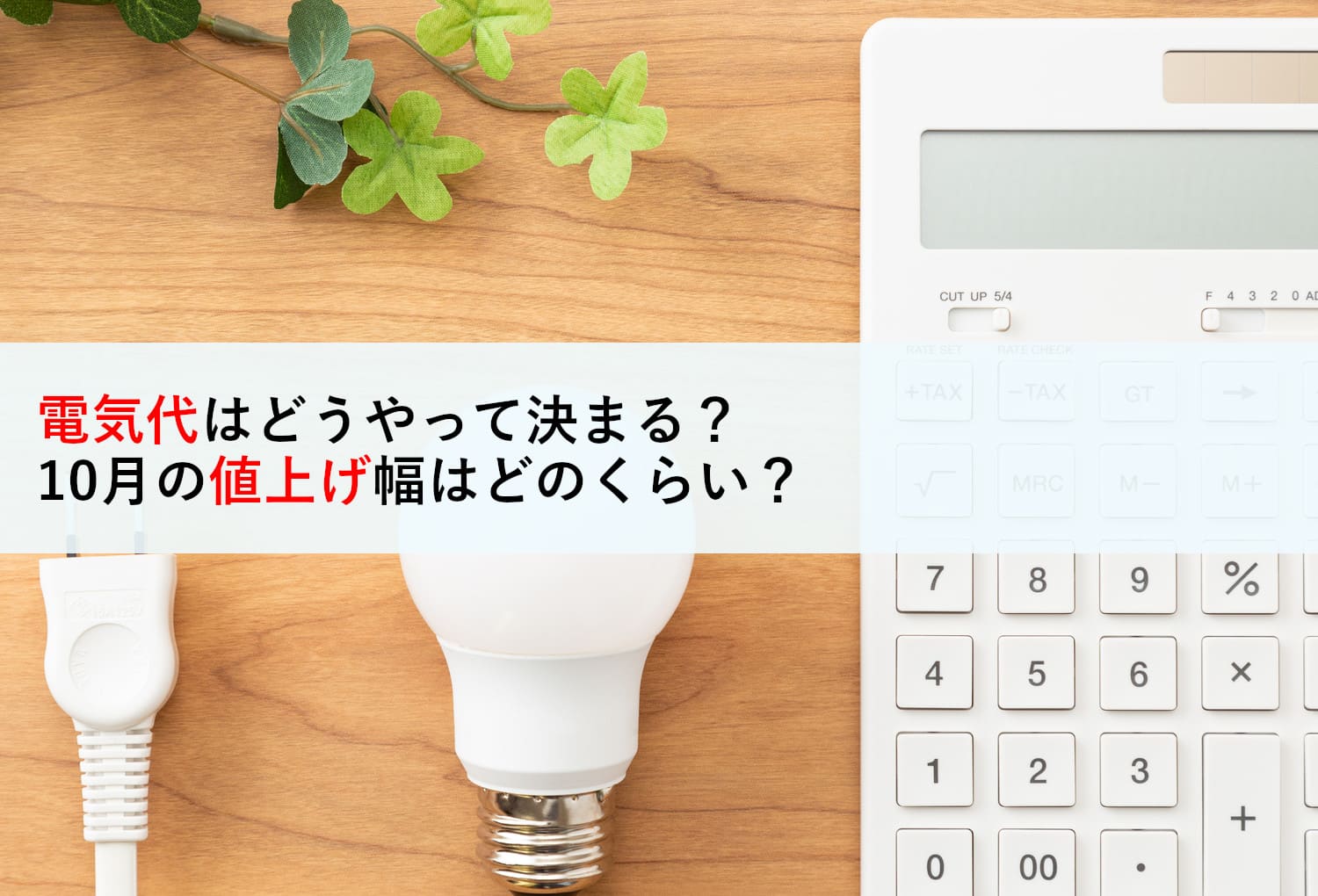








 蓄電池の選び方
蓄電池の選び方































