燃料費調整額が電力会社によって違うのはなぜ?仕組み・上限・電気代対策を専門家が解説

「電気代の明細を見ると、毎月『燃料費調整額』という項目があるけれど、これが電力会社によって違うのはなぜ?」
「最近、電気代が上がったのは燃料費調整額のせいだと聞いた。仕組みはどうなっているの?」
ご家庭の電気代に毎月変動を与えている「燃料費調整額」。実はこの金額、契約している電力会社によって単価が異なります。電気代高騰の要因ともなるこの項目について、仕組みや違いを正しく理解することは、家計の防衛や最適な電力プラン選びに不可欠です。
この記事では、燃料費調整額が電力会社によって違う理由、その計算方法、そして電気代高騰リスクにどう対処すべきかを専門編集者が徹底的に解説します。
【この記事のポイント】
- 燃料費調整額が「電力会社によって違う」根本的な理由(調達コスト・電源構成の違い)
- 燃料費調整単価の計算方法と「上限」の有無が与える影響
- 電気代高騰リスクを根本的に回避するための具体的な対策(自家消費)
燃料費調整額の仕組みを理解し、ご家庭に合った賢い電気の使い方やプランの見直し、さらには太陽光発電などによる根本的な対策を検討するきっかけとしてください。
目次
燃料費調整額とは? なぜ電力会社によって違うのか
【この章の要旨】
燃料費調整額とは、火力発電に用いる燃料(原油・LNG・石炭)の価格変動を電気料金に反映させるための仕組みです。この単価が電力会社によって違う主な理由は、各社が燃料を調達するコストやタイミング、そして発電方法の構成比(電源構成)が異なるためです。特に「上限」の有無が、近年の価格高騰局面で大きな差を生んでいます。
燃料費調整制度の基本的な仕組み
私たちが使う電気の多くは、原油、液化天然ガス(LNG)、石炭などを燃料とする火力発電によって作られています。これらの燃料価格は、為替レートや国際情勢によって常に変動しています。
もし燃料価格が大幅に高騰した場合、電力会社は安定した電力供給が困難になる可能性があります。逆に、価格が下落した場合は、利用者が不当に高い電気代を払い続けることになります。
そこで導入されたのが「燃料費調整制度」です。これは、燃料価格の変動分を、あらかじめ定められた計算式に基づき、電気料金に自動的に上乗せ(または差し引き)する仕組みです。これにより、電力会社は経営リスクを平準化でき、利用者は燃料価格の変動が透明性をもって料金に反映されることになります。
具体的には、3ヶ月間の平均燃料価格(貿易統計に基づく)が、各社が設定した「基準燃料価格」を上回れば単価がプラス(加算)され、下回ればマイナス(減算)されます。この単価に、ご家庭の電気使用量(kWh)を乗じた金額が、毎月の「燃料費調整額」として請求されます。
出典:資源エネルギー庁「電気料金の燃料費調整制度とは?」
「燃料費調整単価」が電力会社によって違う3つの理由
主要KWである「燃料費調整額が電力会社によって違う」のはなぜでしょうか。その答えは、主に以下の3つの要因にあります。
1. 基準燃料価格の設定が違う
燃料費調整額を計算する際のベースとなる「基準燃料価格」は、各電力会社が料金プランを設定した時点の燃料価格に基づいて独自に設定しています。この基準が異なれば、同じ燃料価格の変動があっても、調整単価の計算結果は変わってきます。
例えば、A社が原油価格1バレル=80,000円を基準とし、B社が75,000円を基準としていた場合、同じように90,000円に高騰しても、基準からの「差額」はA社とB社で異なります。
2. 電源構成と燃料調達コストが違う
電力会社によって、電気を作るための「電源構成(どの発電方法をどれくらいの割合で使うか)」が異なります。
- LNG(天然ガス)火力の比率が高い会社
- 石炭火力の比率が高い会社
- 再生可能エネルギーの比率が高い会社
原油、LNG、石炭はそれぞれ価格の変動パターンが異なります。どの燃料への依存度が高いかによって、燃料価格変動が調整単価に与える影響の度合いが変わってきます。
また、燃料を「いつ」「どこから」「どれくらいの量」調達するかという、各社の調達戦略や契約内容の違いも、コストの差として最終的に調整単価に反映されます。
3. 調整単価の「上限」の有無が違う
これが近年、最も大きな差を生んだ要因です。
大手電力会社(旧一般電気事業者)の規制料金プラン(東京電力の「従量電灯B」など、2016年の電力自由化以前から存在するプラン)には、燃料費調整単価に「上限」が設定されていました。これは、基準燃料価格の1.5倍までしか料金に転嫁できないというルールです。
しかし、2022年以降の歴史的な燃料価格高騰により、多くの大手電力会社でこの上限を超える事態が発生しました。上限を超えた分は電力会社が赤字として負担していましたが、経営を圧迫するため、上限の撤廃や見直しが相次ぎました。
一方で、新電力や大手電力会社の自由料金プラン(「スマートライフプラン」など)の多くは、もともとこの「上限」が設定されていません。そのため、燃料価格が高騰した分だけ、青天井で調整単価が上昇しました。
結果として、「上限あり」のプランを契約していた人よりも、「上限なし」のプランを契約していた人の方が、燃料費調整額が著しく高額になるという事態が発生したのです。
(編集部注記:2023年以降、大手電力各社は相次いで規制料金の値上げを行い、その際に上限設定の見直しや基準燃料価格の変更を行いました。2024年現在、多くの会社で上限は事実上撤廃、あるいは非常に高い水準に見直されています。)
【この章のまとめ】
燃料費調整額は、燃料の調達コストや電源構成、そして「上限」設定の有無という3つの大きな要因により、電力会社(およびプラン)ごとに異なります。特に「上限」の有無は、電気代高騰時に家計へ直結する重要なポイントでした。
燃料費高騰に左右されない生活へ。まずは「できること」を知りませんか?
燃料費調整額の仕組みが分かっても、世界情勢で変動する燃料費を個人でコントロールすることはできません。「結局、電気代は上がり続けるの?」とご不安な方も多いはずです。
電気代高騰の根本対策として注目されるのが「太陽光発電」。ご自宅で電気を作り、使うことで、電力会社から買う電気(=燃料費調整額がかかる電気)を大幅に減らせます。 まずは、ご自宅の屋根でどれくらいのメリットが生まれるか、無料でチェックしてみませんか?
電力会社(エリア)別の燃料費調整単価の比較と推移
【この章の要旨】
燃料費調整単価は、電力自由化により旧一般電気事業者(大手電力10社)と新電力で異なる価格設定がされています。特に2022年から2023年にかけては、上限設定の有無により新電力や自由料金プランの単価が著しく高騰しました。現在は政府の「激変緩和措置」により一時的に単価が抑制されていますが、この措置は段階的に終了する予定です。
大手電力10社と新電力の違い
日本の電力市場は、大きく分けて以下の2種類に分類されます。
- 旧一般電気事業者(大手電力10社)北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力。各エリアで長年電力を供給してきた基幹企業です。
- 新電力(小売電気事業者)2016年の電力自由化以降に参入した新しい電力会社。ガス会社、通信会社、石油元売会社など、様々な業種が参入しています。
前章で解説した通り、燃料費調整額が電力会社によって違う最大の要因は「調達コスト」と「上限設定」です。
大手電力会社は、自社で大規模な発電所(火力・水力・原子力など)を保有・運用しており、長期契約に基づいた比較的安定した燃料調達が可能です。一方、新電力の多くは自社で大規模な発電所を持たず、大手電力から電気を仕入れたり、卸電力市場(JEPX)から電気を調達したりしています。
卸電力市場の価格は、燃料価格だけでなく、天候(太陽光発電の出力)や需給バランスによっても激しく変動します。そのため、新電力の燃料費調整額(あるいはそれに代わる「市場価格調整額」など)は、大手電力よりも変動が大きくなる傾向があります。
【注意】激変緩和措置による一時的な抑制
2022年からの急激な電気代高騰を受け、政府は「電気・ガス価格激変緩和措置事業」を実施しています。これは、電力会社に対し、燃料費調整単価から一定額を値引きするための補助金を支給する制度です。
利用者は、この措置により燃料費調整単価が直接値引きされています(例:低圧契約の場合、1kWhあたり-3.5円など ※時期により変動)。
出典:経済産業省 資源エネルギー庁「電気・ガス料金負担軽減支援事業」
この措置のおかげで、2023年以降の電気代明細上の燃料費調整単価は、実際の燃料高騰分よりも低く抑えられています。しかし、この措置は時限的なものであり、2024年5月使用分(6月検針分)から補助が縮小され、その後終了する予定です(※2024年4月時点の情報)。
措置が終了すれば、再び燃料価格がダイレクトに調整単価へ反映されるため、電気代が上昇するリスクがあります。
実際の単価比較(推移の例)
燃料費調整単価が電力会社によってどう違うか、実際の推移を見てみましょう。ここでは例として、東京電力エリアの「大手電力(規制料金)」と「ある新電力(上限なしプラン)」の単価推移(激変緩和措置適用前)を比較します。
| 時期 | 東京電力(従量電灯B・上限適用時) | 新電力A社(市場連動・上限なし) | 差額(1kWhあたり) |
|---|---|---|---|
| 2021年夏頃 | 約 +2.0円 | 約 +2.5円 | -0.5円 |
| 2022年秋頃(高騰ピーク時) | 約 +5.13円(上限到達) | 約 +15.0円 | -9.87円 |
| 2023年夏頃(価格下落・激変緩和除く) | 約 -3.0円 | 約 -2.0円 | -1.0円 |
この表から分かるように、燃料価格が比較的安定している時期は、両者の差はわずかです。しかし、2022年の高騰ピーク時には、上限が適用された大手電力に対し、上限のない新電力の単価が著しく高騰し、1kWhあたり10円近い差が開くケースもありました。
月300kWhを使用する家庭であれば、この差だけで月間約3,000円近い負担増となります。これが「燃料費調整額は電力会社によって違う」ことの最も大きな影響です。
【この章のまとめ】
燃料費調整単価は、大手電力と新電力で仕組みや価格変動リスクが異なります。特に「上限なし」プランは高騰リスクが高く、政府の激変緩和措置が終了した後の動向には注意が必要です。
補助金終了後も安心したい方へ【無料E-BOOK】
政府の補助金がなくなったら、また電気代が跳ね上がるのではないか…。そんな不安をお持ちではありませんか? 燃料費高騰リスクに対する最も効果的な自己防衛策は、電力会社に頼らない「自家消費」です。
太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、電気を「創り」「貯め」「賢く使う」生活が実現します。その具体的な仕組みやメリット、導入費用までを網羅した「パーフェクトガイド」を、今だけ無料でプレゼント中です。まずは情報収集から始めてみませんか?
燃料費調整額の高騰リスクから家計を守る方法
【この章の要旨】
燃料費調整額の違いや高騰リスクから家計を守るには、短期的な対策と中長期的な対策があります。短期的には「電力プランの見直し」が有効ですが、根本的な解決策は「自家消費」です。太陽光発電や蓄電池を導入し、電力会社から買う電気(=燃料費調整額の対象となる電気)を減らすことが、最も効果的な防衛策となります。
短期的な対策:電力会社・プランの見直し
燃料費調整額は電力会社によって違うため、現在契約中のプランを見直すことは、すぐにできる短期的な対策です。
【見直しのチェックポイント】
- 燃料費調整単価に「上限」はあるか?(※ただし、前述の通り、現在大手電力でも上限は見直されているか、上限を超えるほどの高騰は沈静化しています。しかし、今後のリスクヘッジとして確認は必要です。)
- 「市場価格連動型」のプランではないか?新電力の中には、燃料費調整額の代わりに「市場価格調整額」など、卸電力市場(JEPX)の価格に連動する項目を設けている場合があります。このタイプは、市場価格が高騰すると電気代が急激に跳ね上がるリスクがあります。
- 自分のライフスタイル(電気使用時間帯)と合っているか?夜間の電気代が安いプラン、日中の電気代が安いプランなど、ご家庭の電気使用パターンに合ったプランを選ぶことで、トータルの電気代を削減できる可能性があります。
ただし、注意点もあります。2022年の高騰局面では、燃料費調整額の高騰を理由に新電力から大手電力の規制料金プランに戻ろうとする「電力難民」が発生しましたが、大手電力が一時的に規制料金プランの新規受付を停止する事態も起きました。
また、政府の激変緩和措置が適用されている現在は、どの会社も単価が抑えられているため、プラン変更のメリットが出にくい時期でもあります。乗り換えは、措置が終了するタイミングや、各社の新しいプラン内容をよく比較検討してから行うのが賢明です。
中長期的な根本対策:自家消費で「買う電気」を減らす
電力プランの見直しは、あくまで「どの会社から電気を買うか」という選択であり、燃料費調整額の変動リスクそのものから逃れることはできません。
このリスクに対する最も根本的かつ強力な対策は、「電力会社から電気を買う量(kWh)そのものを減らす」ことです。そのための具体的な手段が、太陽光発電と蓄電池の導入による「自家消費」です。
1. 太陽光発電によるメリット
ご自宅の屋根に太陽光パネルを設置すれば、日中の電気を自家発電でまかなうことができます。発電した電気は、当然ながら電力会社から購入するものではないため、燃料費調整額も再生可能エネルギー発電促進賦課金も一切かかりません。
日中に使用する電気が多いご家庭ほど、燃料費調整額の変動リスクを回避できる効果は大きくなります。
2. 蓄電池を併用するメリット
太陽光発電だけでは、発電できない夜間や雨の日は、結局電力会社から電気を買う必要があります。
そこで蓄電池を併用します。日中に太陽光発電で作り、使いきれずに余った電気を蓄電池に貯めておき、夜間や早朝にその電気を使うことができます。これにより、電力会社から電気を買う時間帯を極限まで減らすことが可能になります。
太陽光発電と蓄電池の組み合わせは、燃料費調整額という「外部要因」に家計が左右されるリスクを最小限に抑える、最も確実な防衛策と言えます。
【この章のまとめ】
燃料費調整額の違いに一喜一憂する短期的なプラン見直しも重要ですが、根本的な解決策は「買う電気を減らす」ことです。太陽光発電と蓄電池による自家消費は、電気代高騰リスクそのものから家計を守るための賢明な投資となります。
「うちの屋根だと、いくらかかる?」 専門家が費用対効果を試算します
「自家消費が効果的なのは分かったけれど、導入費用が高そう…」「本当に元が取れるの?」 太陽光発電や蓄電池の導入には、まとまった費用がかかるため、慎重になるのは当然です。
費用対効果は、お住まいの地域の日射量、屋根の形状、現在の電気使用量によって全く異なります。無料シミュレーションをご利用いただければ、専門のアドバイザーがあなたの家の条件に最適な機器を選定し、導入費用から回収期間、そして将来にわたる経済的メリットまで、詳細なシミュレーション結果をご提示します。
燃料費調整額に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 燃料費調整額が電力会社によって違うのは違法ではない?
違法ではありません。2016年の電力自由化以降、電力会社は(一部の規制料金プランを除き)自由に料金を設定できるようになりました。燃料費調整額の計算に用いる「基準燃料価格」や「上限」の有無も、各社の経営判断や料金戦略に基づいています。
燃料調達コストや電源構成が会社ごとに異なるため、調整単価に差が生まれるのは、自由競争下では自然なことです。利用者は、その違いを理解した上で、自分に合った電力会社やプランを選択する権利があります。
※料金設定は、電気事業法などの関連法規を遵守する必要があります。
Q2. 燃料費調整単価の「上限」は復活しない?
大手電力会社が規制料金プランで設定していた「上限」については、2023年の料金改定時に多くが撤廃、または基準価格の大幅な見直し(実質的な上限の引き上げ)が行われました。燃料価格が異常高騰した際に、電力会社の経営が立ち行かなくなるリスクを回避するためです。
今後、国策として制度が変更されない限り、かつてのような低い水準での「上限」が復活する可能性は低いと考えられます。利用者は「上限はない」ことを前提に、電気代高騰リスクに備える必要があります。
出典:各電力会社のプレスリリース(料金改定に関するお知らせ)
Q3. 燃料費調整額がマイナスになることもある?
はい、あります。燃料費調整制度は、燃料価格の変動を料金に反映させる仕組みです。各社が設定した「基準燃料価格」よりも、実際の平均燃料価格が安くなれば、調整単価はマイナス(減算)になります。
実際に、燃料価格が比較的安価だった時期や、2023年のように高騰が一服した時期には、調整単価がマイナスになっている電力会社も多くありました。マイナスの場合は、その分電気代が安くなります。
Q4. 新電力に「燃料費調整額」の項目がないのはなぜ?
新電力の中には、「燃料費調整額」という名称を使わず、別の名称で同様の調整を行っている場合があります。代表的なものが「市場価格調整額」や「電源調達調整費」などです。
これらは、燃料価格だけでなく、卸電力市場(JEPX)の取引価格に連動していることが多いのが特徴です。JEPXの価格は、燃料費以外にも、天候(太陽光の発電量)や電力需給のひっ迫度合いによっても大きく変動します。
※契約中のプランに「燃料費調整額」がない場合でも、必ず料金内訳や契約約款を確認し、どのような変動要因があるかを把握することが重要です。
この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
光熱費削減コンサルタント
中田 萌ご相談やお見積もりは
完全無料です!


 蓄電池
蓄電池 太陽光発電
太陽光発電 パワーコンディショナ
パワーコンディショナ エコキュート
エコキュート IHクッキングヒーター
IHクッキングヒーター 外壁塗装
外壁塗装 ポータブル電源
ポータブル電源











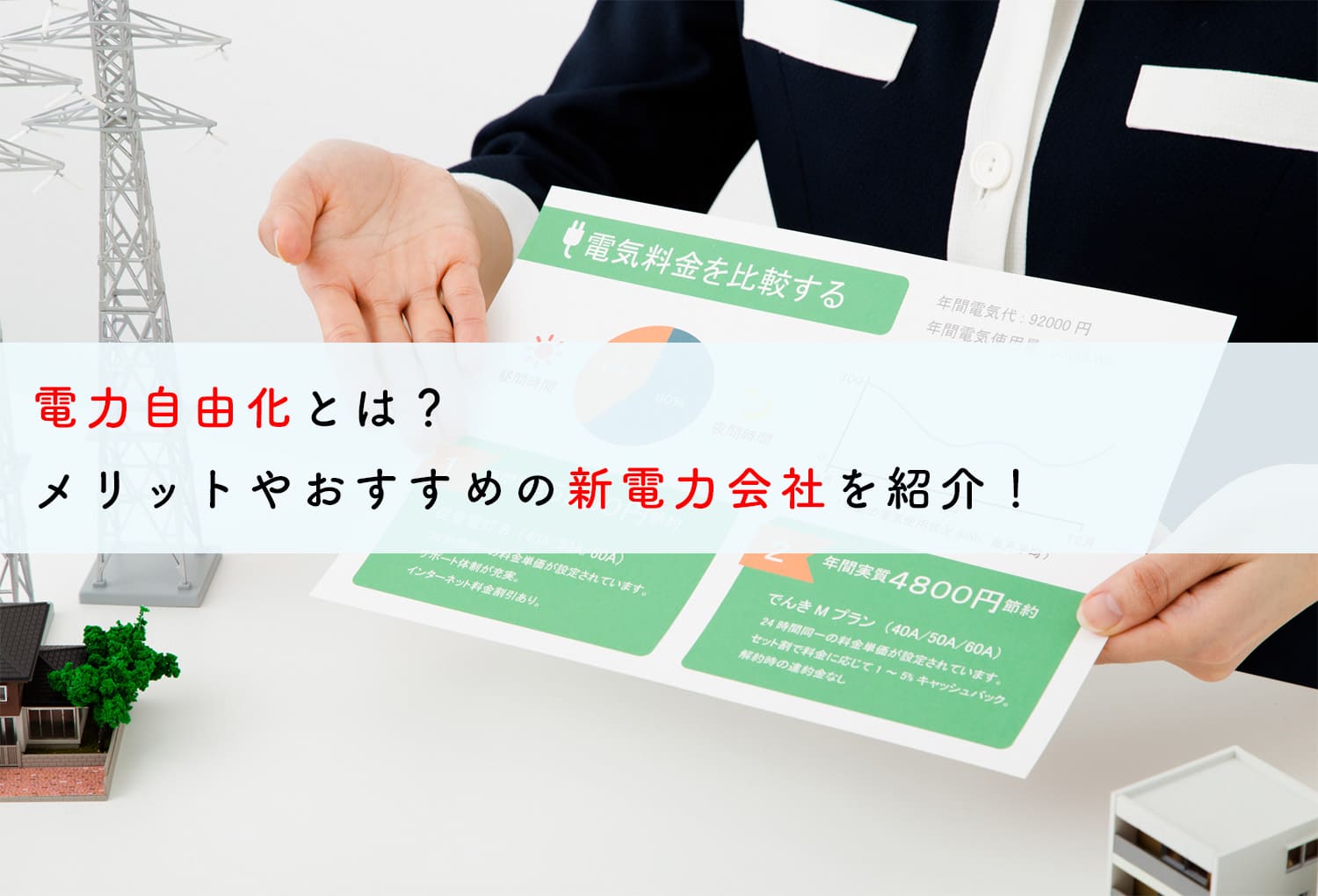
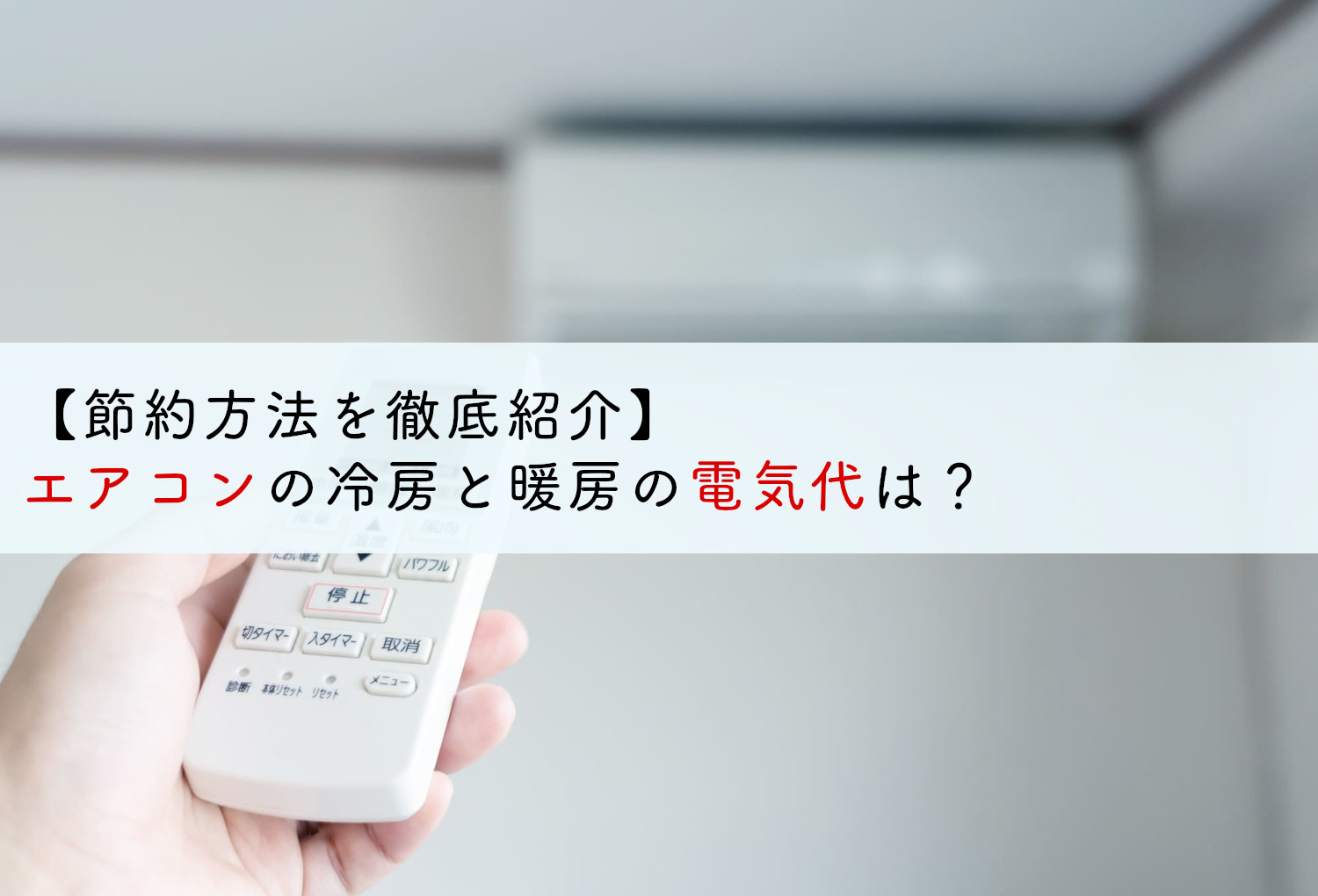







 蓄電池の選び方
蓄電池の選び方































