電気代が高い原因は?太陽光発電や蓄電池を利用した節電対策も紹介!

特に電気の無駄遣いはしていないのに、電気代の請求書を確認すると、思っていたよりも料金が高い、といったことはないでしょうか。
そのため、電気代が高くなった原因について気になる方は少なくないでしょう。
当記事では、電気代が高い原因から太陽光発電や蓄電池を利用した節電対策まで紹介します。 この記事を読むことで、電気代が高くなった原因や、今後の節電対策方法について理解することができます。
目次 [非表示]
我が家の電気代って高いの?使いすぎ?【電気使用量の関係を整理】
そもそもの電気代が高いのか、我が家で電気を使いすぎているかで節電対策の方法は変わってきます。
まずは前提知識として、電気使用量や電気代の計算の仕方について理解しておくことは重要です。 ここでは、電気使用量と電気代の計算方法について詳しく紹介します。
電気使用量とは?
電気使用量とは、月々に家庭電化製品などをどの程度使用したかの総量を指します。 電気使用量は、電力メーターによって知ることが可能です。
電力メーターの数値に基づき、請求書が発行され、電気代を支払う仕組みとなっています。電気メーターは、スマートメーターとも言い、請求書は、検針票と呼ぶこともあります。
電気使用量に使用される単位が、「kWh(キロワットアワー)」です。電気代は「1kWhあたりいくらか」で計算されます。
大手電力会社が公表している料金表や、電気事業者から受け取る検針票に記載されていることが多いため、確認してみることがおすすめです。
電気代の計算方法の紹介
電気代は、「基本料金」「電力量料金」「その他」の足し算で算出が可能です。
その他の中には、「再生可能エネルギーの賦課金」と「燃料費調整費額」が含まれます。その他については後述します。
基本料金は、電気使用量に関係なく固定です。一方、電力量料金は、月々の電気使用量に、電力量単価を掛けることで算出が可能です。
電力量単価は、1kWhあたりいくらかを表します。 つまり、電気使用量が増加するにつれて、電力量料金も増加するため、結果として電気代が増加することになります。
電気代が高いのは使いすぎだけが原因ではない【単価の高騰です】
これまでに、電気代の計算方法について解説しました。 電気を使いすぎたわけではないのに電気代が高いということもあるでしょう。
それは、電気の使いすぎだけが原因ではないからです。 ここでは、電気代が増加している理由について詳しく紹介します。
電力量単価が上昇している
電気代の計算式の中に、電力量単価が含まれていることは先述しました。 近年では、電力量単価が値上がりしていることも、電気代が高くなる要因となっています。
単価が値上がりすると、電気使用量が変わらなくとも、電気代は上昇することになります。単価の値上がりについては、経済産業省が公表している統計データより、原油価格に比例して年々緩やかに上昇する傾向がみられています。(※1)
(参考:日本のエネルギー2020|経済産業省)
再生可能エネルギーの賦課金が上昇している
電気代には、再生可能エネルギー賦課金も含まれています。 再生可能エネルギー賦課金とは、再生可能エネルギーの普及が目的で、電気代を支払うすべての方に一律で課される料金のことです。
再生可能エネルギー賦課金は、電気使用量に独自の単価を掛けることで算出が可能です。再生可能エネルギーの普及にともない、年々単価は上昇しています。導入当時である2012年では、単価が「0.22円」でしたが、2021年では「3.36円」です。
したがって、再生可能エネルギーの賦課金が上昇していることも、電気代が上昇する原因の1つといえるでしょう。
燃料費調整額が上昇している
電気代には、燃料費調整費額も含まれています。 燃料費調整費額とは、燃料費調整制度により、電気使用量に応じて算出される金額のことです。
また、燃料費調整制度とは、燃料費は経済情勢の影響に左右されることから、電力会社の経営効率の成果を明確にするために、燃料費の変動を素早く電気代に反映する制度のことです。
燃料費調整額が上昇している理由は、火力発電の燃料である液化天然ガス・原油・石炭などの資源価格が高騰しているためです。 日本では、これらの資源の大部分は輸入に頼っています。
そのため、資源価格は産出国の政情不安などの影響を受けることが多いです。 実際に、2018年のアメリカによる経済制裁で、主な産出国である中東地域で政情不安が生じて、資源価格の高騰が起きています。
したがって、燃料費調整費額も上昇しているのが、電気代が上昇する原因の1つとなっています。
【高い電気代はコレで対策!】太陽光と蓄電池ってすごい
電気代が高い理由は使いすぎだけが原因ではないことは理解できましたか。ここでは、電気代を安くするための節電対策方法について詳しく紹介します。
太陽光発電を利用
節電するためには、年々上昇している電気代を買わないことが重要です。 そこで、太陽光発電を利用することが注目されています。
ここでは、太陽光発電を利用するメリットを詳しく紹介します。
メリット1:余剰電力の売電
太陽光発電を利用すれば、余剰電力を売電することができます。 余剰電力とは、使い切ることができず、余った電力のことです。
例えば、太陽光発電で2kWh発電している際に、家庭で0.5kWhの電力を自己消費したとします。 そうすると、1.5kWhは余剰電力となりますが、電力会社に余った分の電力を買い取ってもらうことが可能です。
この仕組みは売電とも呼ばれます。 毎月の電力会社が買い取った電力量に、契約上の単価を掛けた料金を電力会社からもらうことができます。
ただし、家庭での太陽光発電の場合では、売電できるのは余剰電力のみであるため、注意が必要です。
メリット2:自己消費
自己消費とは、家庭などで自分たちで消費する電力のことを指します。 一般的に、テレビ・冷蔵庫・洗濯機などの家電製品を稼働させるための電気は、電力会社から購入して利用しています。
一方、太陽光発電を利用して、電気を自分たちで作り出すことによって、電力会社から電気を購入しなくても生活が可能です。
ただし、発電していない場合には、電力会社から電気を購入する必要があります。 電気代が高くなっているため、自己消費の魅力が注目を浴びています。
蓄電池を活用
また、家庭向けの定置型蓄電池も注目されています。
蓄電池は、災害時などの非常な際の電源としてだけではなく、太陽光発電を活用して発電した電気を売電せず、発電できない夜間帯に使用されることもあります。 そうすると、電気自給率の向上が期待できます。
近年では、再生可能エネルギーを利用して発電するコストよりも、電力会社から電気を購入するコストのほうが高いという状態です。 この状態は、グリッドパリティと呼ばれることもあります。
したがって、災害時の保険の意味に加えて、節電対策として蓄電池の導入を検討してみるのもおすすめです。
【まとめ】毎月の電気代が高いなんて悩みは一気に解決!
電気代が高いのは、電気を使いすぎているだけではなく、電力量単価などが上昇していることが理由として挙げられます。 そのため、電力会社から電気を購入すると、必然と電気代が高くなってしまいます。
そこで、注目されているのが再生可能エネルギーです。特に、太陽光発電を活用することで、電気を自分たちで作り出せるだけではなく、売電もできます。蓄電池も並行して活用すれば、電気自給率を高めることも可能です。
したがって、太陽光発電や蓄電池は電気代節約対策の1つとなるので、ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。
この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
光熱費削減コンサルタント
中田 萌ご相談やお見積もりは
完全無料です!



 蓄電池
蓄電池 太陽光発電
太陽光発電 パワーコンディショナ
パワーコンディショナ エコキュート
エコキュート IHクッキングヒーター
IHクッキングヒーター 外壁塗装
外壁塗装 ポータブル電源
ポータブル電源






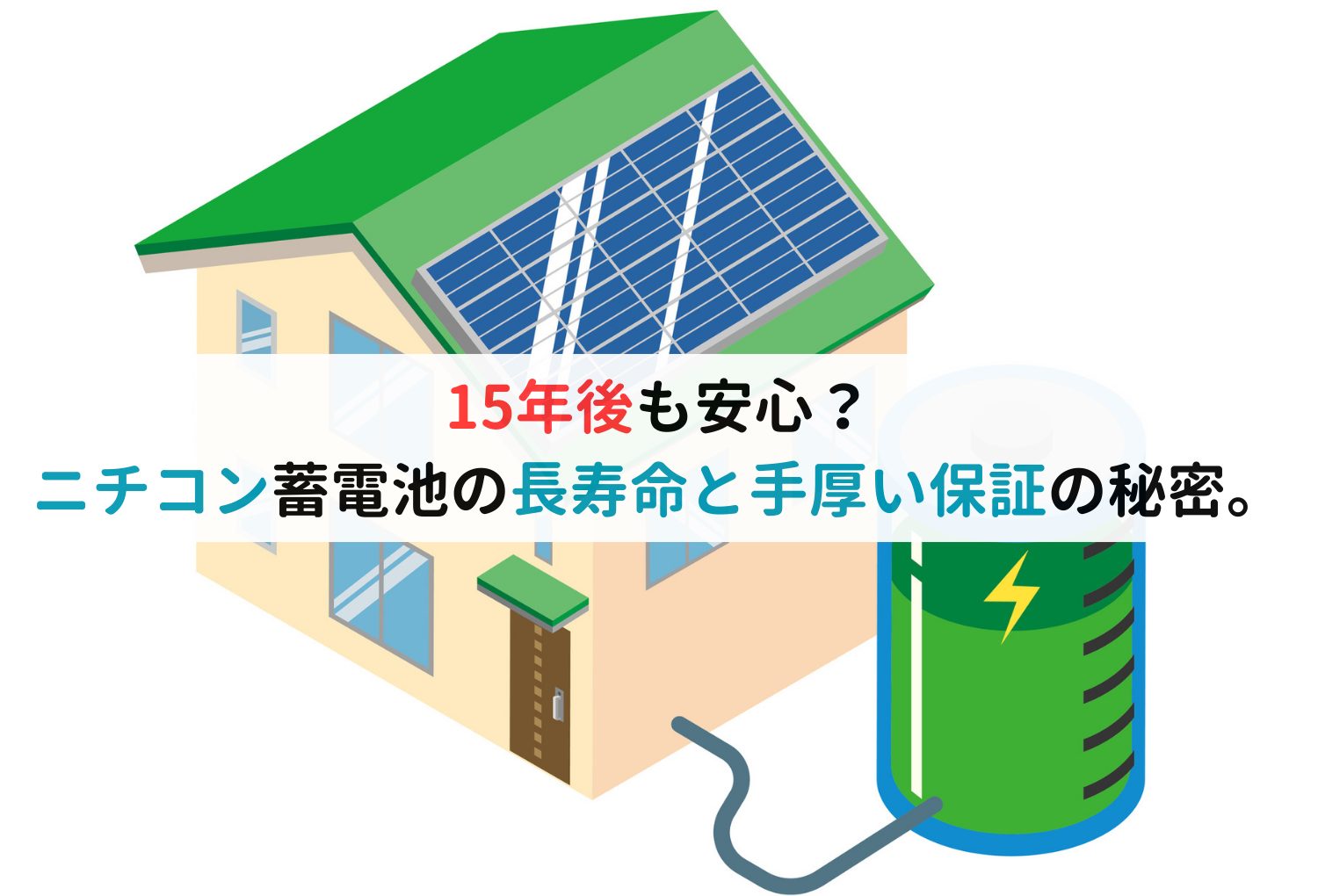
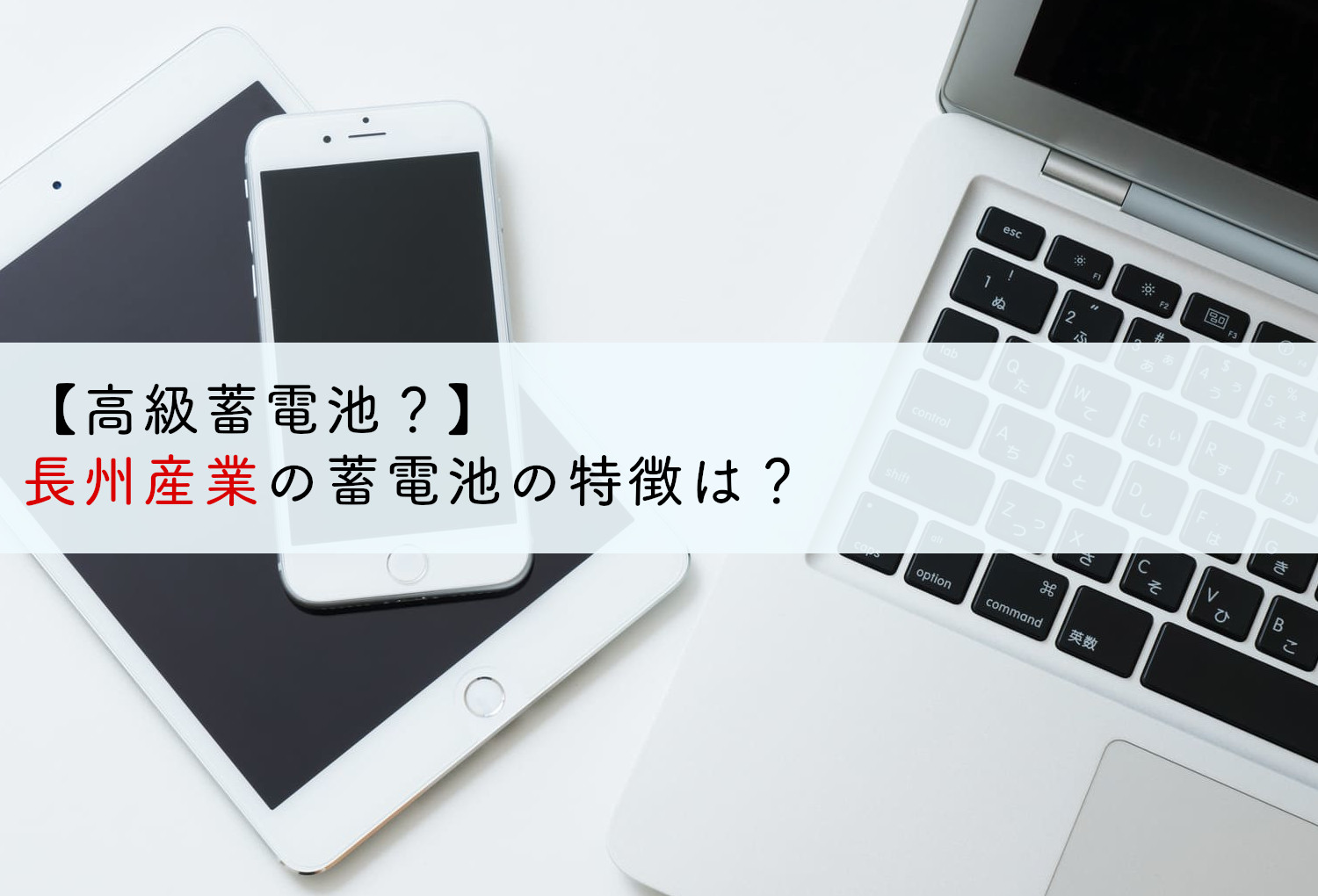







 蓄電池の選び方
蓄電池の選び方






