V2H 補助金 令和6年度情報から探る【2025年度最新動向】
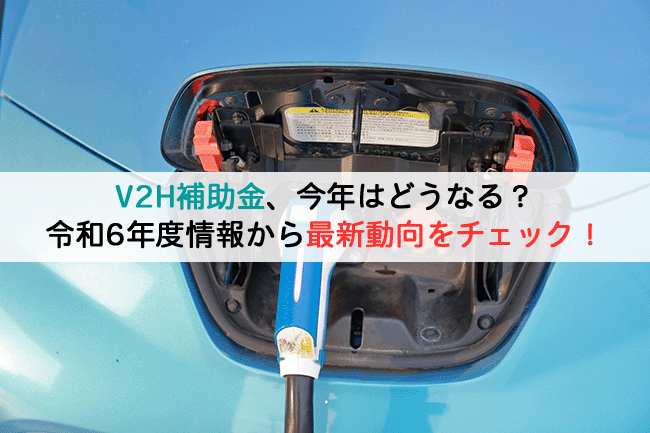
目次
V2H補助金「令和6年度」を振り返り、令和7年度(2025年度)の動向を探る
電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)のバッテリーを家庭用電源として活用するV2H(Vehicle to Home)システム。導入コストの負担を軽減するために、補助金の活用を検討されている方は多いでしょう。「令和6年度(2024年度)のV2H補助金はどうだったのだろう?」「今年度、令和7年度(2025年度)はどうなるの?」という疑問をお持ちかもしれません。このセクションでは、まず昨年度の国の補助金制度を振り返り、それを踏まえて2025年度のV2H補助金の最新動向と情報収集のポイントについて解説します。補助金制度は毎年内容が変更されるため、必ずご自身で最新の公式情報を確認することが最も重要です。
令和6年度(2024年度)のV2H補助金はどうだった?(国の主な例)
昨年度、令和6年度(2024年度)には、国によるV2H導入支援策がいくつか存在しました。これらは今年度の動向を予測する上での参考になります。
CEV補助金:V2H充放電設備への補助概要(令和6年度実績)
令和6年度の代表的な国の支援策として、「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」がありました。この補助金は、主にEV・PHEV・FCV(燃料電池自動車)の車両購入に対する補助が中心ですが、**充電インフラ整備の一環として、V2H充放電設備の設置に対しても補助金が交付されていました。**補助対象となる設備費の上限や工事費の上限が定められ、その一部(例:1/2など)が補助される仕組みでした。
その他の関連補助金:省エネ住宅支援等での扱いは?(令和6年度実績)
CEV補助金以外にも、省エネルギー性能の高い住宅の新築やリフォームを支援する事業(例:子育てエコホーム支援事業など)において、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)化に必要な設備の一つとしてV2Hシステムが間接的に補助対象に含まれるケースがありました。ただし、これはV2H単独の補助金ではなく、住宅全体の性能向上に対する補助の一部という位置づけでした。
令和6年度補助金から見るポイント(補助額・対象機器・期間等)
令和6年度の国の補助金から見えてくるポイントとしては、①V2H機器本体だけでなく、設置工事費も補助対象となる場合が多いこと、②補助対象となるV2H機器が指定されている(リスト化されている)こと、③申請期間が定められており、予算上限に達し次第終了すること、などが挙げられます。補助額の上限は、機器費で数十万円、工事費で数十万円程度が一般的でした。これらの傾向は令和7年度(2025年度)も踏襲される可能性があります。
【最重要】令和7年度(2025年度)のV2H補助金は?(※必ず公式発表を確認!)
さて、最も気になる今年度、令和7年度(2025年度)のV2H補助金はどうなるのでしょうか?現時点(2025年4月21日)では、まだ詳細が発表されていない、あるいは公募が開始されていない補助金が多く、不確定な情報が多い状況です。
国の補助金:令和6年度からの継続・変更・新規の可能性は?
令和6年度に実施されたCEV補助金の後継事業や、省エネ住宅関連事業などが、令和7年度(2025年度)も形を変えて継続される可能性は十分に考えられます。V2Hはエネルギー政策上も重要視されているため、何らかの支援策が講じられる可能性は高いと見られますが、補助額や対象要件、申請方法などが変更される可能性もあります。また、全く新しい補助金制度が登場する可能性もゼロではありません。
現時点(2025年4月)での情報と今後の発表スケジュール予測
例年、国の補助金制度の多くは、新年度(4月)以降、春から夏にかけて詳細が発表され、公募が開始される傾向があります。現時点では具体的な情報が少ないですが、これから数ヶ月の間に、経済産業省や環境省、関連する補助金執行団体(次世代自動車振興センター、SIIなど)から順次情報が出てくると予想されます。アンテナを高く張り、情報収集を続けることが重要です。
補助金情報は流動的!公式情報(省庁・執行団体サイト)の確認が不可欠
**繰り返しになりますが、補助金に関する情報は非常に流動的です。インターネット上の古い情報や不確かな情報に惑わされず、必ず経済産業省、環境省、国土交通省といった関係省庁や、補助金事業の執行団体の公式ウェブサイトで発表される最新の公募要領等を確認してください。**これが最も確実で重要な情報源です。
地域の支援もチェック!自治体(都道府県・市区町村)の補助金も忘れずに!
国の補助金だけでなく、お住まいの自治体(都道府県や市区町村)が独自にV2H導入に関する補助金制度を設けている場合もあります。こちらも忘れずにチェックしましょう。
令和6年度に見られた自治体補助金の傾向
令和6年度(2024年度)においても、多くの自治体、特に東京都などの先進的な自治体では、V2H導入に対する独自の補助金制度が見られました。補助金額や対象要件は自治体によって様々ですが、国の補助金との併用が可能であったり、地域の実情に合わせた手厚い支援が行われたりするケースがありました。
令和7年度(2025年度)の自治体補助金の探し方
令和7年度(2025年度)の自治体補助金についても、まずはお住まいの都道府県、そして市区町村の公式ウェブサイトを確認するのが基本です。「〇〇県(市町村) V2H 補助金」といったキーワードで検索し、環境関連部署やエネルギー政策関連部署のページを探してみましょう。多くの場合、新年度の予算が確定する春以降に情報が更新されます。
令和7年度(2025年度)V2H補助金を活用するための基礎知識
令和7年度(2025年度)のV2H補助金の詳細が発表された際に、スムーズに申請準備を進められるよう、補助金を利用する上での一般的な基礎知識や注意点を押さえておきましょう。
補助対象となる主な要件(一般的な例)
補助金を利用するには、対象となる人、機器、車両に関する要件を満たす必要があります。一般的な例を見てみましょう。
対象者:個人の居住用が基本(自治体により詳細要件あり)
国の補助金の場合、多くは個人が自ら居住する住宅にV2H機器を設置する場合が対象となります。賃貸住宅や事業用での利用は対象外となることが多いです。自治体の補助金では、その自治体の居住者であることが必須要件となります。
対象機器:認定されたV2H充放電設備(リスト確認)
補助対象となるV2H機器は、安全性や性能に関する基準を満たし、補助金事業の事務局等に登録・認定された製品リストに掲載されているものに限られるのが一般的です。導入したいV2H機器が対象リストに含まれているか、必ず事前に確認が必要です。
対象車両:V2H対応のEV・PHEVであること
当然ながら、**V2Hに対応したEVまたはPHEVを所有している(または導入予定である)**ことが前提となります。V2H非対応の車両では補助金は利用できません。どの車種が対応しているかは、自動車メーカーやV2H機器メーカーの情報をご確認ください。
補助金額の考え方と申請プロセス(一般的な注意点)
補助金がいくらもらえるのか、そして申請から受給までの流れはどうなるのか、一般的な考え方と注意点を解説します。
補助金額の決まり方(機器費+工事費の〇分の1、上限額など)
補助金額は、「V2H機器の購入費用」と「設置工事費」を合わせた補助対象経費に対して、一定の補助率(例:1/3、1/2など)を乗じて算出され、かつ上限額が設定されるケースが多く見られます。例えば、「補助対象経費の1/2、上限〇〇万円(機器費上限△△万円、工事費上限□□万円)」といった形です。正確な計算方法は公募要領で確認しましょう。
要注意!申請受付期間と予算上限(早期終了リスク)
**補助金には必ず申請受付期間が設けられています。**そして、**予算の上限額も決まっており、申請額が予算に達した時点で、期間の途中であっても受付が終了(早期終了)してしまいます。**V2H補助金も人気が高いため、公募が開始されたら速やかに申請できるよう、事前の準備が非常に重要です。
申請から受給までの基本的な流れ(交付申請→決定→工事→報告→受給)
一般的な流れは、①補助金の交付申請(契約・工事着手前に行う)、②審査を経て交付決定通知を受領、③V2H機器の設置工事、④工事完了後に実績報告書を提出、⑤報告書審査を経て補助金額の確定通知、⑥指定口座への補助金振込、となります。申請から受給までには数ヶ月単位の時間がかかることを想定しておきましょう。
補助金申請で失敗しないためのチェックポイント3つ
補助金を確実に受け取るために、特に注意すべき3つのポイントをまとめました。申請前に必ず確認しましょう。
チェック1:他の補助金(EV購入補助等)との「併用ルール」を確認
V2H導入と併せて、EVやPHEVの購入補助金、あるいは蓄電池の補助金などを利用したい場合、**それぞれの補助金制度が他の補助金との併用を認めているか、必ず確認が必要です。**併用不可の場合や、併用時に補助額が減額される場合があります。各制度の公募要領等で併用ルールをチェックしましょう。
チェック2:申請は「契約・工事着手前」が原則!順番を守る
**ほとんどの補助金制度では、補助金の交付が正式に決定する前に、設置業者との契約を締結したり、設置工事を開始したりすると、補助対象外となってしまいます。**必ず「①補助金申請 → ②交付決定 → ③契約・工事開始」という順番を守るようにしてください。焦って進めないことが重要です。
チェック3:「必要書類」の準備と提出期限は厳守!
補助金申請には、申請書、見積書、工事契約書(案)、対象機器の仕様書、設置場所の図面や写真、住民票など、多くの書類が必要です。実績報告時にも領収書や保証書、完成写真などが必要になります。必要書類をリストアップし、不備なく、かつ提出期限を厳守して提出することが、スムーズな受給のために不可欠です。
まとめ – 令和7年度(2025年度)のV2H補助金情報をキャッチして賢く活用!
V2H補助金について、令和6年度(2024年度)の実績を参考に、令和7年度(2025年度)の動向と注意点を解説しました。
昨年度は国のCEV補助金などでV2H導入支援がありましたが、令和7年度(2025年度)の国の補助金の詳細は現時点(2025年4月21日)では未確定な部分が多く、今後の公式発表を待つ必要があります。
重要なのは、補助金情報は常に変化するため、経済産業省や環境省、関連執行団体、そしてお住まいの都道府県・市区町村の公式ウェブサイトで、最新かつ正確な情報を必ずご自身で確認することです。
補助金を利用する際は、対象要件、補助金額、申請期間と予算、必要書類、そして他の補助金との併用ルールなどを十分に確認し、契約・工事着手前に申請するという原則を守ることが大切です。
V2Hシステムは、EV/PHEVの価値をさらに高め、エネルギーの効率利用や災害対策に貢献する注目の技術です。最新の補助金情報をしっかりとキャッチし、賢く活用して、お得にV2H導入を実現しましょう。
V2H補助金に関するQ&A
Q1: 令和7年度(2025年度)のV2H補助金はもう始まっていますか?いつ頃発表されますか?
A1: 現時点(2025年4月21日)では、令和7年度の国の主要な補助金の詳細発表や公募開始はまだこれからという状況が多いです。例年、春から夏にかけて情報が出てくることが多いため、経済産業省や関連執行団体のウェブサイトをこまめにチェックすることをお勧めします。自治体の補助金は、各自治体の発表をご確認ください。
Q2: V2H補助金は、EV/PHEVの購入補助金と併用できますか?
A2: **併用できるかどうかは、それぞれの補助金制度のルールによります。**令和6年度のCEV補助金では、車両購入補助とV2H設備補助は同一事業内のため併用可能でしたが、全く別の事業(例:国のV2H補助金と自治体のEV購入補助金)の場合は、各々の規定を確認する必要があります。「併用不可」の場合もあるので注意が必要です。
Q3: 補助金対象となるV2H機器は決まっていますか?
A3: はい、**一般的に補助金の対象となるV2H機器は、安全性や性能基準を満たし、補助金事業の事務局等によって認定・登録された製品リストに掲載されているものに限られます。**導入したい機器がリストに含まれているか、必ず補助金の公募要領や執行団体のウェブサイトで確認してください。
Q4: 賃貸住宅でもV2H補助金は利用できますか?
A4: 国の補助金の場合、多くは申請者自身が所有し居住する住宅への設置が対象となります。そのため、賃貸住宅にお住まいの方が申請するのは難しい場合が多いです。ただし、大家さんが設置する場合や、自治体によっては独自の規定がある可能性もゼロではありません。詳細は各制度の要件をご確認ください。
Q5: 補助金申請は設置業者に代行してもらえますか?
A5: 申請手続きは基本的には申請者本人が行いますが、書類作成のサポートやアドバイス、一部手続きの代行などを設置業者が行ってくれるケースは多いです。補助金申請に慣れている業者に依頼するとスムーズですが、どこまでサポートしてくれるかは業者によります。契約前に確認し、最終的な申請内容の責任はご自身にあることを理解しておきましょう。
この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
光熱費削減コンサルタント
中田 萌ご相談やお見積もりは
完全無料です!



 蓄電池
蓄電池 太陽光発電
太陽光発電 パワーコンディショナ
パワーコンディショナ エコキュート
エコキュート IHクッキングヒーター
IHクッキングヒーター 外壁塗装
外壁塗装 ポータブル電源
ポータブル電源
















 蓄電池の選び方
蓄電池の選び方






