太陽光売電11年目以降の対策完全ガイド

目次
太陽光発電システムの11年目以降とは
太陽光発電システムを導入した多くのご家庭では、10年間の固定価格買取制度(FIT)を利用して安定した売電収益を得てきました。しかし、11年目以降はFIT制度が終了し、売電価格が大幅に下落するという重要な転換点を迎えます。この時期は「卒FIT」と呼ばれ、太陽光発電システムの運用方法を見直す絶好の機会でもあります。
FIT制度下では1kWhあたり24円から48円程度の高い価格で電力を売電できていましたが、11年目以降は一般的に7円から15円程度まで価格が下落します。この変化に対応するためには、事前の準備と適切な対策が不可欠です。現在の電力市場では、卒FIT後の電力を買い取る新たなサービスが多数登場しており、選択肢は以前よりも豊富になっています。
FIT制度終了のタイミング
固定価格買取制度は、太陽光発電システムの運転開始から10年間が対象期間です。2009年にFIT制度が開始されたため、2019年以降順次制度の適用期間が終了しています。2025年現在では、多くのご家庭が既に卒FIT状態となっており、今後も毎年約20万件のペースで卒FIT世帯が増加すると予想されています。
制度終了のタイミングは、太陽光発電システムの系統連系開始日から10年後の応答日となります。例えば、2015年4月15日に系統連系を開始した場合、2025年4月14日まではFIT制度の適用を受け、2025年4月15日から卒FIT状態となります。
11年目以降の売電価格の現実
卒FIT後の売電価格は、各電力会社や新電力会社が独自に設定しており、地域や事業者によって大きく異なります。一般的な買取価格は1kWhあたり7円から15円程度となっており、FIT期間中と比較すると約3分の1から5分の1の水準まで下落します。
大手電力会社の2025年度の卒FIT買取価格を見ると、東京電力エナジーパートナーが8.5円/kWh、関西電力が8円/kWh、中部電力ミライズが7円/kWhとなっています。一方、新電力会社の中には、より高い価格での買取や独自のサービスを提供する事業者も存在します。
11年目以降の売電収益シミュレーション
一般的な家庭での収益変化
4kWの太陽光発電システムを設置した一般的な家庭を例に、11年目以降の収益変化をシミュレーションしてみましょう。年間発電量を4,000kWh、自家消費率を30%と仮定した場合、売電量は年間2,800kWhとなります。
FIT期間中(1kWhあたり28円で計算)の年間売電収益は78,400円でした。しかし、卒FIT後(1kWhあたり8円で計算)の年間売電収益は22,400円となり、年間56,000円の収益減少が発生します。10年間で計算すると、約56万円の収益差が生じることになります。
※これらの数値は特定の条件下での一例であり、効果を保証するものではありません。
地域による収益差
太陽光発電の発電量は地域の日射量によって大きく左右されるため、11年目以降の収益も地域差が生じます。日射量の多い九州地方や四国地方では、関東地方と比較して年間発電量が10%から20%程度多くなる傾向があります。
北海道のような寒冷地では、太陽光パネルの変換効率が高温地域よりも優れている反面、積雪による発電量減少や日照時間の短さが影響します。これらの地域特性を考慮した上で、11年目以降の運用戦略を検討することが重要です。
システム劣化による発電量への影響
太陽光発電システムは経年劣化により、徐々に発電効率が低下します。一般的に、年間0.5%から0.8%程度の出力低下が見られ、11年目には新設時と比較して約5%から8%程度の発電量減少が予想されます。
この劣化を考慮した現実的な収益計算を行うことで、より正確な将来予測が可能になります。メーカーの出力保証期間内であれば、一定の発電量が保証されているため、保証内容も確認しておくことが大切です。
自家消費への転換メリット
電気代削減効果の最大化
11年目以降は売電価格が下落する一方で、電力会社から購入する電気代は上昇傾向にあります。2025年現在の家庭用電力料金は1kWhあたり25円から35円程度となっており、8円程度の売電価格と比較すると3倍以上の価格差があります。
この価格差を活用することで、太陽光発電で作った電力を売電するよりも自家消費に回した方が経済的メリットが大きくなります。例えば、1kWhの電力を8円で売電する代わりに30円の電気代を削減できれば、22円分の経済効果が得られることになります。
自家消費率向上の具体的方法
自家消費率を高めるためには、昼間の電力使用パターンを見直すことが効果的です。洗濯機や食器洗い乾燥機、エコキュートなどの電力消費量の多い機器を、太陽光発電量の多い昼間時間帯に集中して使用することで、自家消費率を大幅に向上させることができます。
タイマー機能を活用した家電の運転スケジュール調整や、HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)の導入により、効率的な電力利用が実現できます。これらの取り組みにより、自家消費率を30%から50%以上まで向上させることも可能です。
電力自給率向上による安心感
自家消費率の向上は経済メリットだけでなく、災害時の備えとしても重要な意味を持ちます。太陽光発電システムには自立運転機能が備わっており、停電時でも昼間の発電中であれば最大1.5kW程度の電力を確保できます。
近年増加している自然災害による停電リスクを考慮すると、電力自給率の向上は家庭の防災対策としても価値があります。特に、医療機器を使用するご家庭や在宅勤務が多いご家庭では、電力の安定確保が重要な課題となっています。
蓄電池導入による収益性向上
蓄電池設置のメリット
11年目以降の太陽光発電システムに蓄電池を組み合わせることで、さらなる経済メリットと利便性の向上が期待できます。蓄電池があることで、昼間に発電した余剰電力を夜間に使用できるようになり、自家消費率を70%から90%程度まで向上させることが可能です。
現在の家庭用蓄電池の費用相場は容量1kWhあたり15万円~25万円程度となっており、4kWh~7kWhの一般的なシステムでは60万円~175万円程度が目安となります。初期投資は必要ですが、長期的な電気代削減効果により投資回収が期待できます。
蓄電池容量の選び方
適切な蓄電池容量を選択するためには、各家庭の電力使用パターンと太陽光発電量を詳細に分析する必要があります。一般的な4人家族の場合、夜間の電力消費量は5kWh~8kWh程度となるため、6kWh~10kWhの蓄電池容量があれば十分な効果が期待できます。
蓄電池の寿命は30年前後とされており、太陽光発電システムの残り稼働期間と合わせて検討することが重要です。また、蓄電池には充放電効率やサイクル寿命などの性能差があるため、単純な容量比較だけでなく、総合的な性能評価を行うことが大切です。
投資回収期間の計算
蓄電池導入による投資回収期間は、設置費用、電気代削減効果、既存の売電収益の変化などを総合的に考慮して計算する必要があります。一般的なケースでは、12年から18年程度での投資回収が見込まれますが、電気料金の上昇や災害時の価値も含めて評価すると、より短期間での回収も期待できます。
国や自治体の補助金制度を活用することで、初期投資負担を軽減できる場合があります。2025年現在では、多くの自治体で蓄電池導入に対する補助金制度が設けられており、設置前に最新の制度情報を確認することをお勧めします。
※これらの数値は特定の条件下での一例であり、効果を保証するものではありません。
新電力会社との契約選択
卒FIT向けプランの比較
卒FIT後の売電先として、大手電力会社以外にも多くの新電力会社が参入しています。各社が提供する買取価格やサービス内容には大きな差があり、適切な選択により年間数万円の収益差が生じる可能性があります。
一部の新電力会社では、卒FIT電力の買取価格を12円/kWh以上に設定している事業者もあります。また、電気の購入契約とセットにすることで、より有利な条件を提供する会社も存在します。契約前には複数社の条件を比較検討することが重要です。
付加サービスの活用
新電力会社の中には、単純な電力買取だけでなく、様々な付加サービスを提供する事業者があります。ポイント還元サービス、家電修理サービス、見守りサービスなど、電力以外の価値を組み合わせたプランも登場しています。
これらの付加サービスを含めた総合的な価値評価を行うことで、単純な買取価格比較では見えないメリットを発見できる場合があります。ただし、契約期間や解約条件などの詳細も必ず確認し、将来的な変更に柔軟に対応できる契約を選択することが大切です。
契約変更時の注意点
売電先を変更する際には、現在の契約内容と新しい契約条件を詳細に比較する必要があります。契約変更には一定の手続き期間が必要な場合が多く、空白期間が生じないよう計画的に進めることが重要です。
また、契約変更に伴う事務手数料や、最低契約期間の設定がある場合もあります。長期的な視点で最適な選択を行うため、契約条件の詳細確認と将来的な事業継続性も考慮した判断が求められます。
その他の活用方法
電気自動車との連携
電気自動車(EV)の普及に伴い、太陽光発電との連携による新たな活用方法が注目されています。昼間の余剰電力でEVを充電し、夜間や電力需要の高い時間帯にEVから家庭に電力を供給するV2H(Vehicle
to Home)システムの導入が可能です。
EVの大容量バッテリーを活用することで、従来の家庭用蓄電池以上の電力貯蔵が可能になります。ただし、V2Hシステムの導入には専用機器が必要で、設置費用も考慮する必要があります。
地域マイクログリッドへの参加
一部の地域では、近隣住民同士で電力を融通し合うマイクログリッドの実証実験が行われています。このシステムでは、余剰電力を地域内で直接取引することで、従来の売電価格よりも高い価格での電力販売が可能になる場合があります。
現在はまだ実証段階の取り組みが多いですが、将来的には地域エネルギーの自給自足システムとして発展する可能性があります。地域の取り組み状況について情報収集を行い、参加機会があれば検討してみることをお勧めします。
太陽光発電システムの増設
既存の太陽光発電システムが設置から11年以上経過している場合、新たに太陽光発電システムを増設するという選択肢もあります。現在の太陽光発電システムの費用相場は1kWあたり35万円~40万円程度となっており、技術進歩により以前よりも効率の良いシステムが導入可能です。
増設による追加発電量は新しいFIT制度や自家消費に活用でき、既存システムとは異なる運用戦略を取ることができます。ただし、屋根の構造や設置可能面積、電力会社との契約容量などの制約を事前に確認する必要があります。
まとめ
太陽光発電システムの11年目以降は、売電価格の大幅な下落により収益性が変化する重要な転換点となります。しかし、適切な対策を講じることで、引き続き経済的なメリットを享受することが可能です。
自家消費率の向上、蓄電池の導入、新電力会社との契約見直し、電気自動車との連携など、多様な選択肢を組み合わせることで、卒FIT後も太陽光発電システムを有効活用できます。各家庭の電力使用パターンや予算、将来的な計画に合わせて、最適な対策を選択することが重要です。
また、技術進歩や制度変更により、今後も新たな活用方法が登場する可能性があります。定期的な情報収集を行い、変化に応じて柔軟に運用方針を見直すことで、長期にわたって太陽光発電システムのメリットを最大化できるでしょう。
よくある質問
太陽光発電の11年目以降はどうなりますか?
固定価格買取制度(FIT)が終了し、売電価格が大幅に下落します。FIT期間中の24円~48円/kWhから、7円~15円/kWh程度まで価格が下がるため、自家消費への転換や蓄電池導入などの対策が必要になります。新電力会社への契約変更により、より有利な条件で売電を継続することも可能です。
卒FIT後の売電先はどこを選べばよいですか?
売電先の選択は、買取価格だけでなく、付加サービスや契約条件を総合的に評価して決めることが重要です。大手電力会社の買取価格は7円~8.5円/kWh程度ですが、新電力会社の中には12円/kWh以上で買い取る事業者もあります。ポイント還元や家電修理サービスなどの付加価値も考慮して選択しましょう。
蓄電池を設置するメリットはありますか?
蓄電池の設置により、自家消費率を70%~90%程度まで向上させることができ、電気代削減効果が大幅に増加します。容量1kWhあたり15万円~25万円程度の初期投資は必要ですが、12年~18年程度での投資回収が見込まれます。災害時の非常用電源としての価値も含めて評価すると、より短期間での回収も期待できます。
自家消費率を高める方法を教えてください
昼間の電力使用パターンを見直すことが最も効果的です。洗濯機、食器洗い乾燥機、エコキュートなどの消費電力の大きい機器を、太陽光発電量の多い10時~14時頃に集中して使用しましょう。タイマー機能の活用やHEMSの導入により、自動的に最適な運転スケジュールを組むことも可能です。
太陽光発電システムの寿命はどのくらいですか?
太陽光パネル自体の寿命は25年~30年程度とされており、多くのメーカーが20年~25年の出力保証を提供しています。年間0.5%~0.8%程度の出力低下は見られますが、適切なメンテナンスを行うことで長期間の発電が可能です。パワーコンディショナーは10年~15年程度で交換が必要になる場合があります。
この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
光熱費削減コンサルタント
中田 萌ご相談やお見積もりは
完全無料です!



 蓄電池
蓄電池 太陽光発電
太陽光発電 パワーコンディショナ
パワーコンディショナ エコキュート
エコキュート IHクッキングヒーター
IHクッキングヒーター 外壁塗装
外壁塗装 ポータブル電源
ポータブル電源








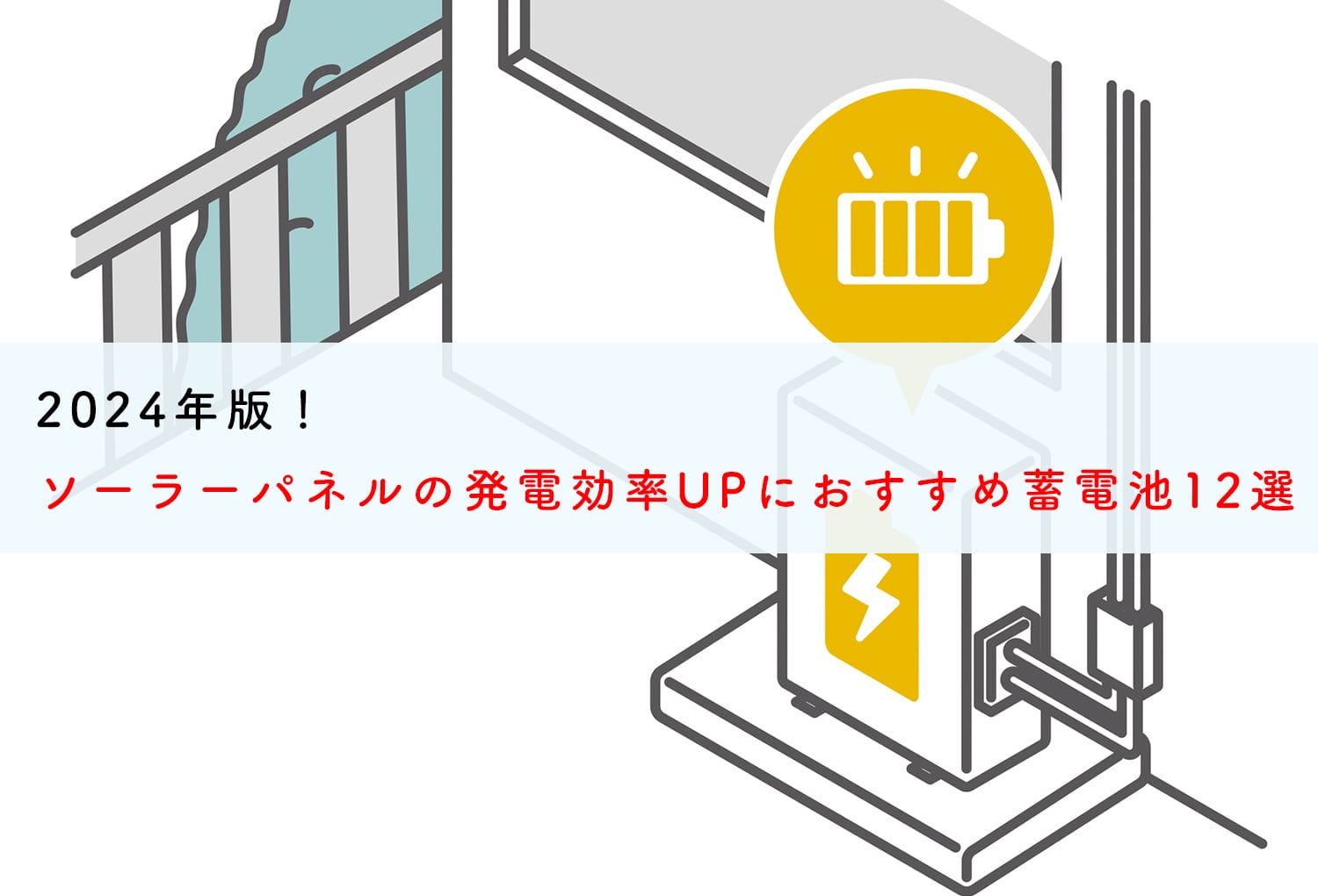







 蓄電池の選び方
蓄電池の選び方






