蓄電池の「鉛」を解説!リチウムイオンとの違いと選び方のコツ
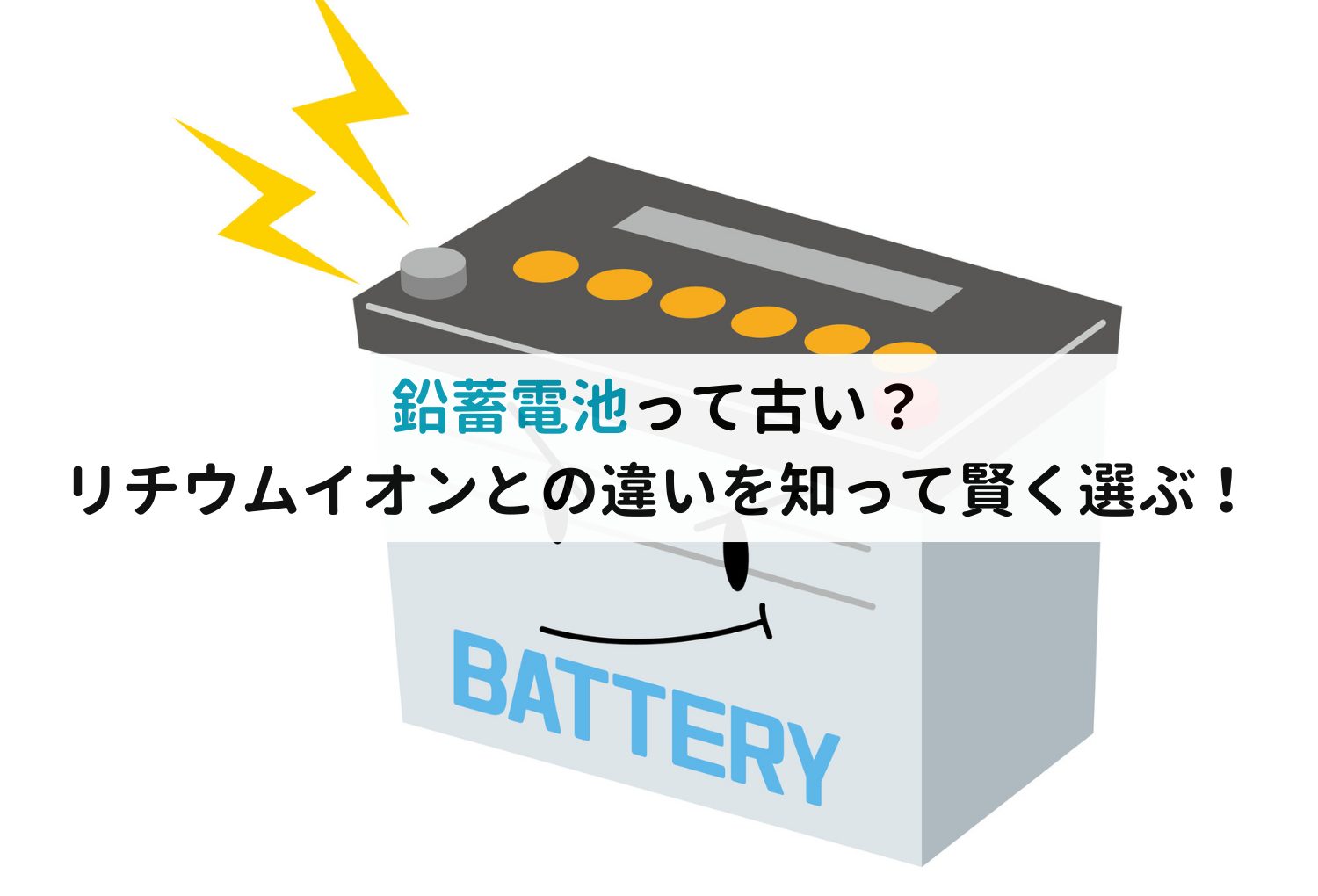
家庭用蓄電池の導入を検討する際、多くの方が「リチウムイオン電池」という言葉を耳にするかと思います。しかし、蓄電池には古くから使われている「鉛蓄電池」という種類も存在します。自動車のバッテリーとしてお馴染みの鉛蓄電池ですが、家庭用蓄電池としてはどのような特徴を持っているのでしょうか?この記事では、「蓄電池 鉛」というキーワードで検索されているあなたへ、鉛蓄電池の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、そして現在主流のリチウムイオン電池との違いについて、2025年4月現在の情報を踏まえ、分かりやすく解説していきます。
目次
鉛蓄電池とは?基本を押さえよう
まずはじめに、鉛蓄電池がどのようなものなのか、その基本的な仕組みと歴史、そして種類について理解を深めましょう。古くから利用されている技術だからこその特徴があります。
鉛蓄電池の仕組みと歴史
鉛蓄電池は、1859年にフランスのガストン・プランテによって発明された、**最も歴史の古い二次電池(充電して繰り返し使える電池)**です。その基本的な仕組みは、電解液である希硫酸(薄めた硫酸)の中に、二酸化鉛(PbO$_2$)を正極、鉛(Pb)を負極として浸した構造になっています。放電時には、両極が硫酸鉛(PbSO$_4$)に変化することで電気エネルギーを取り出し、充電時には外部から電気エネルギーを与えることで、元の二酸化鉛と鉛に戻る化学反応を利用しています。160年以上の歴史を持ち、その間に改良が重ねられ、信頼性の高い技術として確立されてきました。自動車のバッテリーをはじめ、様々な分野で長年にわたり使用され続けている実績があります。
鉛蓄電池の種類(開放型、制御弁式など)
鉛蓄電池には、その構造やメンテナンス方法によっていくつかの種類があります。代表的なものとしては、「開放型(液式)」と「制御弁式(VRLA:Valve Regulated Lead Acid)」の2つが挙げられます。
開放型鉛蓄電池は、従来からあるタイプで、充電中に発生するガス(水素ガスと酸素ガス)を外部に放出する構造になっています。電解液である希硫酸が電気分解によって減少するため、定期的に精製水を補充するメンテナンスが必要です。比較的安価ですが、設置場所の換気や液補充の手間がかかります。
一方、制御弁式鉛蓄電池は、充電中に発生するガスを電池内部で再結合させて水に戻す仕組み(ガス再結合反応)を取り入れたものです。これにより、電解液の減少が抑えられ、原則として補水メンテナンスが不要(メンテナンスフリー)となっています。密閉構造に近く、安全性が向上しているため、UPS(無停電電源装置)や家庭用蓄電池の一部としても利用されています。制御弁式には、電解液をガラスマットに吸着させたAGM(Absorbent Glass Mat)タイプと、ゲル状にしたGELタイプがあります。
家庭用蓄電池における鉛蓄電池の位置づけ
鉛蓄電池は長い歴史と実績を持つ技術ですが、現在の家庭用蓄電池市場においてはどのような位置づけにあるのでしょうか。主流となっている技術と比較しながら見ていきましょう。
現在の主流はリチウムイオン電池
2025年現在、家庭用蓄電池の市場では、リチウムイオン電池が主流となっています。その理由は、リチウムイオン電池が鉛蓄電池に比べてエネルギー密度が高く、同じ容量でも小型・軽量化が可能であること、寿命が長いこと、充電効率が良いことなどが挙げられます。特に、設置スペースが限られる日本の住宅事情においては、コンパクトなリチウムイオン電池のメリットは大きいと言えます。また、太陽光発電システムとの連携やスマートホーム機能など、多機能化が進んでいるのもリチウムイオン電池搭載モデルが中心です。
鉛蓄電池が選ばれるケースとは?
リチウムイオン電池が主流であるものの、鉛蓄電池が全く使われなくなったわけではありません。特定の条件下や用途においては、鉛蓄電池が選択されるケースもあります。例えば、初期費用を極力抑えたい場合です。鉛蓄電池はリチウムイオン電池に比べて、同じ容量あたりの価格が安価な傾向にあります。また、設置スペースに十分な余裕があり、重量が問題にならない場合や、低温環境下での使用が想定される場合なども、鉛蓄電池の特性が活かせる可能性があります。さらに、UPS(無停電電源装置)のバックアップ電源など、常に満充電に近い状態で待機し、停電時に短時間だけ電力を供給するような用途では、コストパフォーマンスの高さから鉛蓄電池が採用され続けています。
鉛蓄電池のメリット:なぜ今も使われるのか
鉛蓄電池が長い間使われ続け、現在でも特定の分野で活躍しているのには理由があります。ここでは、鉛蓄電池が持つ主なメリットについて解説します。
コストパフォーマンスの高さ(初期費用)
鉛蓄電池の最大のメリットの一つは、リチウムイオン電池と比較して初期導入費用が安価である点です。蓄電池システムの導入には大きなコストがかかりますが、鉛蓄電池を選択することで、初期投資を抑えることが可能です。特に、限られた予算内でバックアップ電源を確保したい場合などには、コストパフォーマンスの高さが魅力となります。長年の製造実績があり、材料である鉛も比較的安価で調達できることが、低価格を実現している要因です。
高い安全性と信頼性(実績、過充電・過放電への耐性)
160年以上の長い歴史を持つ鉛蓄電池は、その安全性と信頼性において確固たる実績があります。基本的な構造がシンプルであり、異常発生時の挙動に関する知見も豊富に蓄積されています。リチウムイオン電池で懸念されることがある熱暴走のリスクも、鉛蓄電池では極めて低いとされています。また、ある程度の過充電や過放電に対しても、リチウムイオン電池よりは耐性があると言われています。これらの実績と安定性が、自動車のバッテリーや重要なインフラのバックアップ電源など、高い信頼性が求められる分野で今なお採用され続けている理由です。
リサイクル技術の確立
鉛蓄電池は、非常に高いリサイクル率を誇ることも大きな特徴です。使用済みの鉛蓄電池は、その大部分が回収され、適切に処理された上で、鉛やプラスチックなどが新しい蓄電池の材料として再利用されています。日本国内においても、鉛蓄電池のリサイクルシステムは高度に確立されており、資源の有効活用と環境負荷の低減に貢献しています。持続可能な社会を目指す上で、リサイクル性の高さは重要なメリットと言えるでしょう。
低温環境での性能安定性
鉛蓄電池は、比較的低温の環境下でも性能が安定しているという特徴があります。リチウムイオン電池は、低温になると性能が低下しやすい(特に放電性能)という弱点がありますが、鉛蓄電池はその影響を受けにくい傾向にあります。そのため、寒冷地での使用や、温度管理が難しい場所での利用においては、鉛蓄電池が有利となる場合があります。自動車のバッテリーとして、冬場の厳しい寒さの中でもエンジンを始動させることができるのは、この特性による部分も大きいと言えます。
鉛蓄電池のデメリット:家庭用として考える際の注意点
多くのメリットがある一方で、鉛蓄電池にはデメリットも存在します。特に家庭用蓄電池として導入を検討する際には、以下の点に注意が必要です。
エネルギー密度が低い(重くて大きい)
鉛蓄電池の最大のデメリットは、エネルギー密度が低いことです。これは、同じ量の電気を蓄えるために、リチウムイオン電池よりも体積が大きく、重量も重くなってしまうことを意味します。家庭用の限られたスペースに設置する場合、この大きさや重さが制約となる可能性があります。特に、小型・軽量化が求められる用途には不向きと言えるでしょう。設置場所の確保や、床の耐荷重などを事前に確認する必要があります。
寿命が比較的短い(充放電サイクル数)
鉛蓄電池は、充放電を繰り返すことによる劣化がリチウムイオン電池よりも早く進む傾向があります。製品によって異なりますが、一般的に鉛蓄電池のサイクル寿命(充放電を繰り返せる回数)は、リチウムイオン電池の数分の一程度とされています。そのため、毎日充放電を繰り返すような家庭用蓄電池としての使い方では、リチウムイオン電池に比べて交換時期が早く訪れる可能性があり、長期的なコスト(交換費用)を考慮する必要があります。
充電効率がやや低い
鉛蓄電池は、充電効率(投入した電力に対して、実際に蓄えられる電力の割合)がリチウムイオン電池に比べてやや低いというデメリットもあります。一般的に、鉛蓄電池の充電効率は80~90%程度とされるのに対し、リチウムイオン電池は95%以上と比較的高効率です。これは、充電時にエネルギーの一部が熱として失われたり、副反応に使われたりするためです。充電効率が低いと、同じ量の電気を蓄えるためにより多くの電力が必要となり、電気代や太陽光発電の自家消費効率に影響を与える可能性があります。
定期的なメンテナンスが必要な場合も(特に開放型)
鉛蓄電池の中でも、特に開放型の場合は、定期的なメンテナンスが必要となります。前述の通り、充電中に電解液(希硫酸)中の水分が電気分解されて減少するため、定期的に精製水を補充(補水)しなければなりません。また、端子の清掃なども必要になる場合があります。制御弁式(VRLA)であれば、基本的にメンテナンスフリーですが、それでも全く手入れが不要というわけではありません。メンテナンスの手間やコストも考慮に入れる必要があります。
鉛蓄電池とリチウムイオン電池の徹底比較
家庭用蓄電池を選ぶ上で、鉛蓄電池とリチウムイオン電池のどちらが良いのか迷われる方も多いでしょう。ここでは、両者の主な違いを項目別に比較してみます。
価格(初期費用 vs トータルコスト)
初期費用だけで見れば、一般的に鉛蓄電池の方がリチウムイオン電池よりも安価です。しかし、寿命が短い傾向があるため、交換頻度が高くなる可能性があります。長期的な視点(ライフサイクルコスト)で考えると、寿命が長く、メンテナンスの手間が少ないリチウムイオン電池の方が、トータルコストでは有利になる場合もあります。導入時の予算だけでなく、ランニングコストや交換費用も含めて比較検討することが重要です。
サイズと重量
エネルギー密度の違いから、同じ蓄電容量であれば、鉛蓄電池はリチウムイオン電池よりも大きく、重くなります。設置スペースが限られている場合や、見た目のコンパクトさを重視する場合は、リチウムイオン電池が有利です。鉛蓄電池を選ぶ場合は、十分な設置スペースと、重量に耐えられる設置場所を確保できるかを確認する必要があります。
寿命と性能(エネルギー密度、充放電効率)
寿命(サイクル寿命)やエネルギー密度、充電効率といった性能面では、総じてリチウムイオン電池の方が優れています。より多くの電気をより小さなスペースに蓄え、より効率的に充放電でき、より長く使用できるのがリチウムイオン電池の特徴です。頻繁な充放電を伴う家庭用蓄電池としての利用には、リチウムイオン電池の方が適していると言えるでしょう。
安全性
安全性に関しては、鉛蓄電池は長い歴史と実績があり、技術的に成熟しているため、高い安全性が確立されています。一方、リチウムイオン電池も厳しい安全基準に基づいて製造され、安全対策が施されていますが、過去には発火事故なども報告されています(ただし、近年は安全性が大幅に向上しています)。どちらのタイプも、信頼できるメーカーの製品を選び、適切な設置・使用方法を守ることが重要です。
適した用途
これらの比較を踏まえると、家庭用蓄電池として、日常的な充放電による電気代削減や太陽光発電の自家消費率向上を主目的とする場合は、性能面で優れるリチウムイオン電池が一般的に推奨されます。一方、初期費用を抑えたい場合や、停電時のバックアップ電源としての利用が主目的で、設置スペースや重量に制約が少ない場合には、鉛蓄電池も選択肢となり得ます。
鉛蓄電池の主な用途
鉛蓄電池は、その特性を活かして、現在でも様々な分野で重要な役割を担っています。家庭用蓄電池以外での主な用途を見てみましょう。
自動車用バッテリー(スターター)
鉛蓄電池の最も代表的な用途は、自動車のスターターバッテリーです。エンジンを始動させる際に、短時間で大きな電流を供給する必要があり、この要求に鉛蓄電池の特性が適しています。また、コストパフォーマンスの高さや低温環境での安定性も、自動車用バッテリーとして広く採用されている理由です。ハイブリッド車や電気自動車の補機バッテリーとしても使用されています。
産業用バックアップ電源(UPS)
ビルや工場、データセンターなどの重要施設における無停電電源装置(UPS)のバックアップ電源としても、鉛蓄電池は広く利用されています。停電が発生した際に、コンピューターシステムや通信機器、防災設備などが停止しないように、短時間から数時間、電力を供給し続ける役割を担います。高い信頼性とコストパフォーマンスが求められるこの分野では、依然として鉛蓄電池の需要は高いです。
フォークリフトなどの動力源
工場や倉庫などで使用される電動フォークリフトの動力源としても、鉛蓄電池が使われています。大きなパワーを必要とし、比較的稼働時間が予測しやすいフォークリフトには、大容量でコストの安い鉛蓄電池が適している場合があります。ただし、近年ではエネルギー効率やメンテナンス性の観点から、リチウムイオン電池搭載のフォークリフトも増えています。
一部の小規模オフグリッドシステム
電力会社の送電網が届かない山小屋や離島などで、**太陽光発電と組み合わせて使用される小規模な独立電源システム(オフグリッドシステム)**において、コストを抑える目的で鉛蓄電池が利用されることがあります。ただし、メンテナンスの手間や寿命を考慮すると、近年ではリチウムイオン電池が選択されるケースも増えています。
まとめ:鉛蓄電池の特徴とリチウムイオン電池との違いを理解し、最適な蓄電池選びを
この記事では、鉛蓄電池の基本からメリット・デメリット、そしてリチウムイオン電池との比較について解説してきました。
鉛蓄電池は、長い歴史に裏打ちされた高い信頼性と安全性、そしてコストパフォーマンスの高さが魅力の蓄電池です。リサイクルシステムが確立されている点も、環境負荷低減の観点から重要です。一方で、エネルギー密度が低く大型で重いこと、寿命が比較的短いこと、メンテナンスが必要な場合があることなどがデメリットとして挙げられます。
現在の家庭用蓄電池の主流は、小型・軽量で高性能、長寿命なリチウムイオン電池ですが、導入目的や予算、設置環境によっては、鉛蓄電池が適しているケースも存在します。特に、初期費用を抑えたい場合や、非常用電源としての利用が主目的であれば、検討の価値があるでしょう。
最終的にどちらのタイプの蓄電池を選ぶかは、それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、ご自身のライフスタイル、設置場所の条件、予算、そして蓄電池に求める役割などを総合的に考慮して判断することが重要です。この記事が、あなたにとって最適な蓄電池選びの一助となれば幸いです。
鉛蓄電池に関するQ&A
Q1: 家庭用の鉛蓄電池の価格はどれくらいですか?
A1: 家庭用の鉛蓄電池システムの価格は、容量やメーカー、機能によって大きく異なりますが、一般的にリチウムイオン電池システムよりも初期費用は安価な傾向があります。ただし、具体的な価格は設置工事費なども含めて変動するため、複数の販売・施工業者から見積もりを取って比較検討することをお勧めします。
Q2: 鉛蓄電池の寿命はどれくらいですか?
A2: 鉛蓄電池の寿命は、種類や使用状況(充放電の頻度や深さ、温度環境など)によって大きく左右されますが、一般的にサイクル寿命は数百回~数千回、期待寿命は数年~10年程度と言われています。これは、リチウムイオン電池(数千回~1万回以上、10年~15年以上)と比較すると短い傾向にあります。
Q3: 鉛蓄電池は安全ですか?
A3: はい、鉛蓄電池は160年以上の歴史を持つ成熟した技術であり、安全性は高いとされています。過充電や過放電に対する耐性も比較的あり、熱暴走のようなリスクも極めて低いです。ただし、開放型の場合は水素ガスが発生するため換気が必要であり、電解液(希硫酸)の取り扱いには注意が必要です。制御弁式はより安全性が高められています。
Q4: 今でも家庭用として鉛蓄電池を選ぶメリットはありますか?
A4: 主なメリットは初期費用の安さです。予算を抑えて非常用電源を確保したい場合などには選択肢となり得ます。また、低温環境での性能安定性を重視する場合にも有利なことがあります。ただし、サイズ、重量、寿命、性能面ではリチウムイオン電池に劣る点が多いため、総合的な判断が必要です。
Q5: 使い終わった鉛蓄電池はどうすればいいですか?
A5: 鉛蓄電池はリサイクルが義務付けられています。自動車用バッテリーはガソリンスタンドやカー用品店、整備工場などで引き取ってもらえます。産業用や家庭用の蓄電池システムの場合は、購入した販売店や専門の処理業者に回収・処分を依頼するのが一般的です。不法投棄は絶対にやめましょう。
この記事の監修者

『お客様に寄り添うこと』をモットーに日々の業務に取り組んでおります。
太陽光発電の活用方法や蓄電池の導入などのご相談は年間2000件以上頂いており、真摯に問題解決に取り組んできました。
光熱費削減に関するお悩み等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
光熱費削減コンサルタント
中田 萌ご相談やお見積もりは
完全無料です!



 蓄電池
蓄電池 太陽光発電
太陽光発電 パワーコンディショナ
パワーコンディショナ エコキュート
エコキュート IHクッキングヒーター
IHクッキングヒーター 外壁塗装
外壁塗装 ポータブル電源
ポータブル電源







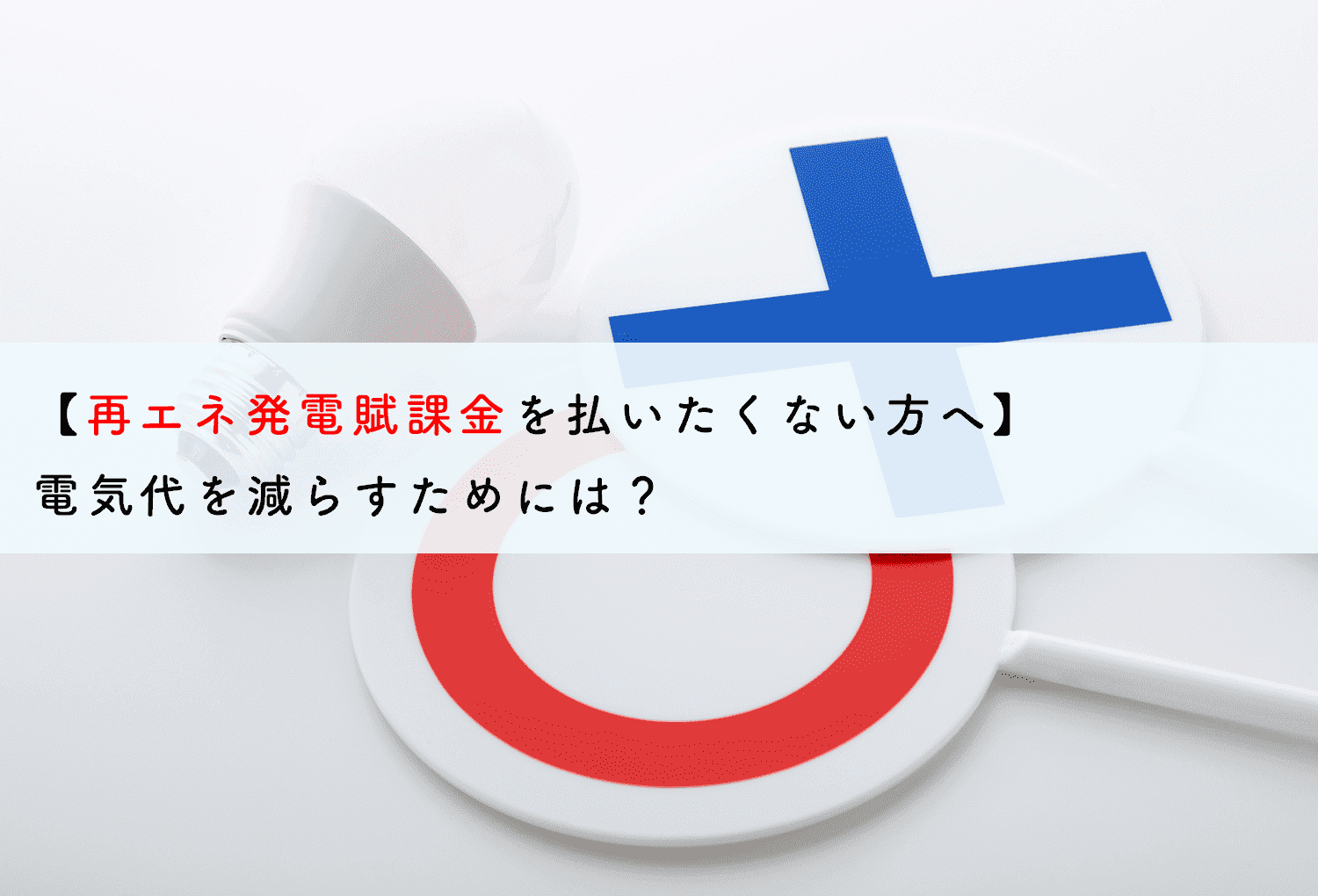
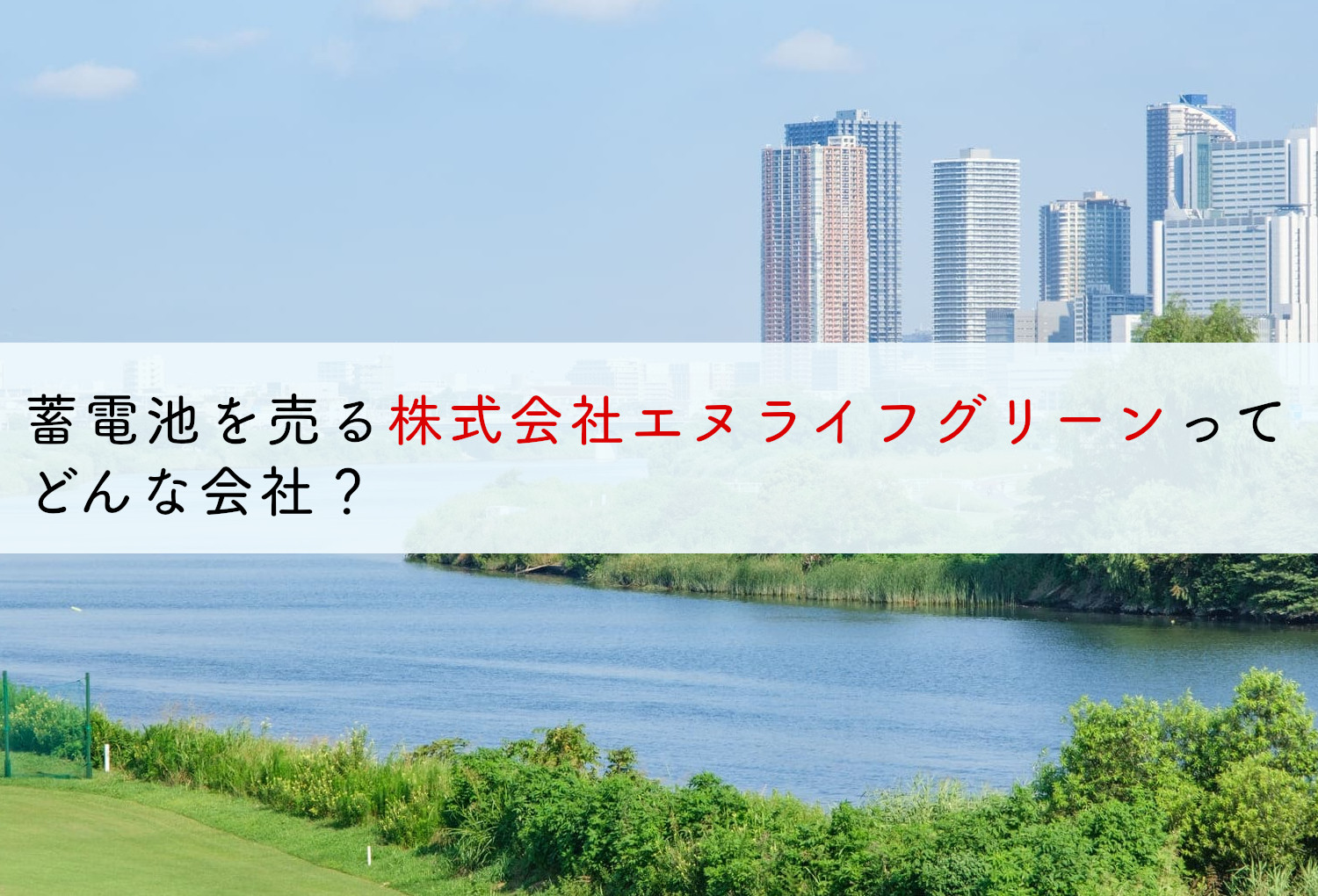







 蓄電池の選び方
蓄電池の選び方






